工程管理は製造工程のQCD最適化:生産管理との関連、課題と解決策を導入事例付きで解説
公開日:2020年03月03日
最終更新日:2025年04月04日

工程管理は、生産管理業務の一つであり、製造現場の「見える化」を実現する手法です。しかし、多くの企業では工程管理において、「生産の進捗がわからない」「計画通りに進まない」「ムダな作業が多い」 などの課題に直面しています。
本記事では、工程管理の基本概念から、生産管理との違い、具体的な進め方を解説し、よくある課題とその解決策をQCDの観点で整理しました。さらに、工程管理で失敗しないためのポイントや、工程管理システムの導入事例も紹介します。
工程管理とは:現場を見える化する手法

工程管理とは、一言でいうと「生産プロセスにおいて、工程ごとの進捗や実績を管理して、現場を”見える化”すること」です。
製造業では、原材料の投入から製品の完成まで、多くの工程を経由します。その中で、工程管理では、次の2点に注目した管理を行います。
- 作業が計画通りに進んでいるのか
- どこで、なぜ、遅れが発生しているのか
適切な工程管理を行えば、進捗の遅れを事前に察知し、適切な対応策の実行が可能になります。
生産管理業務の一つとしての工程管理
生産管理業務の中で、生産プロセスに関する部分を担うのが工程管理です。生産管理は、以下のような多くの業務から構成されており、その中に工程管理も含まれます。
- 需要予測:フォーキャストをもとに生産数量を決定
- 資材調達:原材料・部品の契約・調達
- 生産計画:製造スケジュールの作成
- 工程管理:各製造工程における作業進捗の管理
- 品質管理:製品の品質不良の発生・流出を防止
- 在庫管理:完成品・部品・原材料の適正な在庫維持
工程管理では、生産現場の日常的な管理を行い、生産管理の中で立案した生産計画の遵守が求められます。
生産管理の中で、最も自社で完結しやすい管理業務
生産管理に関わる多くの業務の中でも、工程管理は自社内で完結しやすいプロセスであり、現場主導で改善を進めやすいのが特徴です。
例えば、以下のような改善策は、各現場の工夫だけで実施可能です。
- 作業標準書を作成・展開し、作業品質のバラつきを防ぐ
- 作業者の配置を見直し、負荷を均等化する
- 工程内のボトルネックを特定し、ムダな待ち時間を削減する
工程管理は、製造現場の改善活動(カイゼン)と相性が良く、小さな工夫の積み重ねで大きな成果を生む管理業務と言えます。
生産管理との違い:工程管理はQCDの部分最適化
生産管理では、材料調達から出荷までのQCD(品質・コスト・納期)の全体最適化を目指し、工場全体の統括管理を行います。一方、工程管理では、製造工程ごとのQCD最適化を行い、現場レベルでの管理を徹底する役割を果たします。
以下の表で、QCDの視点における生産管理、工程管理それぞれの役割を例示しました。
| 生産管理の視点 | 工程管理の視点 | |
| 品質(Q) | 製品全体における不良率低減の施策を検討 | 各工程の作業基準を統一し、不良発生を防止 |
| コスト(C) | 原材料仕入れや出荷・運搬に関わるコストを低減 | 作業時間を短縮し、労務費を抑制 |
| 納期(D) | 生産スケジュール全体を調整 | 各工程のリードタイムを短縮 |
特に、生産管理からの目が届きにくい現場では、工程管理による作業進捗・生産効率・工程内品質の管理が強く求められます。具体的には、次のような現場が挙げられます。
- 生産工程が複数に分かれている現場
- 製品ごとに生産工程が異なる現場
例えば、金属加工業や樹脂加工業は、上記条件に当てはまるケースが多く、工程管理の重要性が特に高い業界です。工程ごとの最適化を図ることで、生産のスムーズな流れを確保し、QCDの向上を実現します。
工程管理の進め方

製造工程の管理は、次のようなPDCAサイクルを回して行います。
製造工程ごとの詳細計画を立てる
生産管理で立案した全体の生産計画を基に、各製造工程について詳細な計画を立てます。具体的な実施内容は、以下の通りです。
- 納期情報などをもとに、製品ごとの優先順位を付ける
- 製造工程ごとに、実施スケジュールと作業人員を引き当てる
- 保管場所、リードタイムを考慮して、必要な原材料・部品の発注・納入計画を立てる
詳細な計画を立てることで、やるべきことが見える化され、各工程がスムーズに連携可能となります。また、生産の流れが途切れることなく進められる(整流化を実現した)生産活動が実現します。
また、詳細計画を立てる際には、ボトルネックとなる工程をあらかじめ把握しておくことが重要です。特に原材料や部品の調達がボトルネックである場合、納期遅延リスクに備えた対策も必要です。
進捗状況を管理する
精緻な生産計画があっても、進捗管理は欠かせません。製造工程の進捗遅れやトラブルを早期発見すれば、軌道修正も容易です。しかし、ボトルネックとなる工程では大きな遅れの挽回が難しいケースも多く、重点的な工程管理が必要です。
例えば、半導体製造における基板材料の加工は、次の3つの工程から成り立ちます。
- 切断:大判の基板(パネル)を所定のサイズにカット
- 成形:形状を整え、不要な部分を除去
- 穴あけ:スルーホールやビアホールを高精度で加工
この中でも、穴あけ工程は特に精密な加工が求められ、処理時間や設備負荷の面で、生産全体のボトルネックになりやすいという特徴があります。挽回しやすい切断、成形工程は作業日単位で行い、ボトルネックである穴あけ工程はリアルタイム管理を実施すべきでしょう。
実績データをもとにQCDを評価する
生産実績データをもとに、QCD(品質・コスト・納期)の観点で分析・評価することも、工程管理の重要なステップです。作業者の思いこみではなく、数値データで評価することで、効果的な改善策を講じることも可能となります。
例えば、ある月の基板穴あけ工程における作業実績を集計したところ、次の表の通りであったとします。
製品品番DD012では、計画進捗率、良品率とも、他の4品番と比較して悪い結果となっています。そこで、この品番の作業実績を確認したところ、6回の工具作業のうち5回で、交換直後の作業における良品率の大幅低下が判明しました。このように、実績データをもとに改善点を絞り込めば、有効な打ち手を講じることが可能となります。
改善策を次の計画に反映させる
実績に基づく評価結果から、改善施策を次回以降の生産計画に織り込みます。抽出された改善点をすぐに改善することは難しいため、改善に向けた検証プロセスも計画に含めます。
以下の表は、前述の基板穴あけ工程の改善計画の立案例を示したものです。
今回の改善策として、調整作業の効率化を目的に、調整治具の導入を生産計画に組み込みました。しかし、最適化のためには十分な検証が必要です。そこで、本格導入後は1日あたり1000個の生産を目標とし、その前に2回の効果検証を設定し、検証期間中は1日あたり900個の生産計画としました。
このように、改善策の段階的な導入検証を計画に反映させることで、より確実性の高い生産計画となります。
工程管理における3つの課題

製造現場の工程管理では、様々な課題を抱えているケースが少なくありません。QCD(品質・コスト・納期)の観点から、工程管理でよくある課題を整理していきましょう。
Q:品質ばらつきが大きい
製造現場では、工程管理が適切に行われていないと、同じ製品を作っているつもりでも品質にばらつきが発生します。その原因には、次のようなものが挙げられます。
- 設備の影響:経時劣化により、機械の精度が低下する
- 環境変化の影響:季節変動の影響を考慮した、操業条件の調整ができてない
- 工程内検査の不足:中間工程での品質チェックができていない
このような場合、品質面からも工程管理の強化が望ましいでしょう。設備の稼働状況をもとに、計画的なメンテナンスを実施し、予防保全を徹底することが効果的です。
また、環境変化など、予測困難な要因で出来栄えが大きく変わり、操業条件の調整が必要になるケースもあります。これらの取り組みに加え、工程内でリアルタイムの品質チェックを組み合わせれば、不良発生の予兆を早期検出でき、品質の安定化が図れます。
C:生産効率が上がらない
工程管理が適切に行われていないと、現場の生産効率は改善しません。その主な原因として、以下の3点が挙げられます。
- 進捗管理が手作業:進捗状況を手作業で集計しており、必要な対応が遅れる
- 工程のムダが多い:作業手順や動線が最適化されていない、段取り替えに長時間を要する
- 設備稼働率が低い:稼働率推移が見えず、改善余地を見つけにくい
製造現場ではトラブルが付き物であり、効率的な進捗管理にはリアルタイムでの状況把握が欠かせません。特に生産現場が遠かったり、多拠点にまたがっていたりする場合には、デジタルツールによる一元管理が有効です。
さらに、工程管理をデジタル化すると、各種データが正確に蓄積しやすくなります。これらのデータを分析することで、作業工程や設備稼働率の改善点を絞り込みやすくなります。
D:納期遅延が減らない
生産活動の中で工程管理がうまく機能せず、生産計画通りに進まないことが常態化している現場もあります。このような現場では、納期遅延に伴い、以下のような追加コストの負担も大きくなります。
- 遅れを挽回するために、残業・休日出勤による労務費の増加
- 急いで納品するための高額なチャーター便利用が増え、輸送費が膨張
- 納期遅延ペナルティの支払い
このような作業現場では、工程管理において、次のような問題を抱えているケースも少なくありません。
- 進捗状況の把握が困難:生産の遅れに気づかず、対応が後手に回る
- 作業負荷の偏り:一部の工程に負担が集中し、ボトルネックで生産全体が停滞
- 突発的なトラブル多発:設備故障や部品不足により、生産計画が崩れる
進捗状況をリアルタイムでチェックしたり、設備稼働率のデータ分析による改善施策の検討が望まれます。
工程管理に役立つ3つの方法:メリット・デメリットともに紹介

工程管理では、現場の規模感や目的に応じて、適切な方法を選択します。
なお、時間軸に応じた日程表(大日程計画、小日程計画)の選び方や注意ポイントについては、こちらの記事も参考にしてください。
→日程計画で生産進捗・タスクを見える化しよう!計画立案の方法も具体的に解説
ホワイトボードに工程表を書く
現場で実践できる工程管理として、最も簡単に実践できるのはホワイトボードを活用した工程表です。小規模な生産現場に向いており、リアルタイム性よりもシンプルな工程管理を優先する現場に有効な方法です。
ホワイトボードの最大のメリットは、重要な情報を一目で確認できることです。書き込めるスペースが限られており、必要な情報を絞り込む必要があるからです。さらに、自由度が高く臨機応変に修正でき、その場のメンバーで状況共有がしやすいという特徴があります。
一方で、デメリットとして、記載できる情報量が少なく、過去の実績を残せない点が挙げられます。このため、ホワイトボードで全ての工程管理を実践することは現実的ではありません。
エクセルで工程表を管理する
工程管理として広く使われているのは、エクセルで作成した工程表です。PCで自由自在にカスタマイズできるため、自社に合った形で簡単に工程管理を実践できます。
反面、エクセルの工程表は、変更がリアルタイムで反映できず、過去の実績データ活用が難しいというデメリットもあります。エクセルでは同時編集が難しいため、印刷した帳票に手書きで記入し、後で転記する運用が現実的です。
しかし、この方法では進捗状況がリアルタイムで把握できず、トラブルに対する迅速な対応は難しくなります。さらに、メンバー間で共有するため、エクセルのバージョン管理が複雑となり、データ追跡が容易でないケースも少なくありません。
工程管理システムを利用する
システムを活用して、工程進捗をデジタル管理する方法もあります。特に多品種少量生産や、製造工程が長い現場では、非常に高い効果が期待できます。
工程管理システム導入には費用負担が発生し、システムに合わせた運用ルールの整備、業務フローの見直しも必要となります。しかし、リアルタイムで情報共有が可能であり、データの一元管理も容易です。さらに、自動集計も活用すれば、収集・蓄積したデータを活用しやすいというメリットもあります。
工程管理で失敗しないための4つのポイント

適切な生産管理を行う上で、工程管理を確実に行うことが重要です。ここでは、工程管理で失敗しないための4つのポイントを紹介します。
記録に関するルールを定める
工程管理の基本は正しい作業記録であり、そのためには明確なルールの整備が欠かせません。ルールが不明確であれば、記録の漏れや誤りが発生し、進捗状況の正確な把握が難しくなります。記録ルールを明確化することで、よりスムーズな工程管理が実現します。
記録ルールの策定ポイントとして、以下のような項目が挙げられます。
- 記録フォーマットの統一:記録項目を定め、同じ場所に入力する
- 記入タイミングの明確化:1ロット分の作業完了直後の記入を徹底する
- 作業者と記入者の一致:伝達ミスを防ぎ、作業者情報の追跡性しやすくする
記録方法が簡単であるほど、作業員に浸透しやすくなります。工程管理システムとIoTツールを活用すると、作業実績の自動化や工数削減が可能です。ハンディ端末によるQR・バーコード管理を活用すれば、手書きやエクセル入力と比べて手間を削減できます。RFID技術を使うと、実績登録の自動化も実現できます。
情報の精度を高める
工程管理の記録精度を高めることも重要です。精度が低い場合、適切な判断が下せず、収集したデータを活用できなくなるケースもあります。
例えば、工程管理システムでは、次のように情報精度を高めることができます。
- 作業完了直後に実績登録すれば、工程完了時間を正確に記録できる
- 工程検査データを直接入力し、合否判定を自動化できる
- 作業者ごとに入力権限を設定し、意図しないデータ改ざんを防ぐ
工程管理システムの中には、バーコード読み取り機能を備えたものもあります。このようなシステムでは、登録情報の入力ミスを大きく減らすことも可能です。
工程進捗をリアルタイムで把握する
工程管理のリアルタイム化は、トラブルへの対応を迅速化し、納期遅延のリスクを大幅に低減できます。例えば、リアルタイムの工程管理を導入すれば、製品1個の不良にも即座に対応可能です。しかし、作業日ごとの管理であれば、不良が大量に発生してから気づくため、経営上の悪影響が大きくなりやすくなります。
リアルタイムでの工程進捗管理には、工程管理システムの導入が有効です。さらに、次のような機能を備えたシステムを活用すれば、さらなる効果が期待できます。
- 遅れや不良が発生した場合に、即座にアラートを出す
- 一覧画面で関係者全員が進捗を確認できる
品質・設備トラブルを未然防止する
工程管理を適切に行う上で、品質トラブルや設備トラブルを未然防止するための取り組みも不可欠です。これらのトラブルが発生すると、突発的な生産ラインの停止により、生産計画からの大幅な遅延を招きます。
そのためには、品質検査結果や設備の稼働率を監視し、継続的にデータを蓄積することが欠かせません。蓄積された実績データを分析すれば、得られた品質トレンドから不良発生の予兆を捉えたり、設備の予防保全を適正化することも可能です。さらに、他のデータと組み合わせれば、品質ばらつきの大きな改善策が見つかるかもしれません。
工程管理システムの導入事例

現場の見える化と効率化を加速する工程管理システムは、多くの現場で採用されています。
実際のシステム導入事例を取り上げ、具体的な活用方法を紹介します。
エクセル作業からの脱却で、工程管理工数を削減
ファインセラミックスの製造企業では、紙の作業実績表を手作業でエクセル集計しており、工場全体の工程管理に毎日6時間を費やしていました。
しかし、工程管理システムとハンディ端末の導入により、作業実績を直接システムに記録できるようになり、集計時間を半減。さらに、PCから工程進捗を瞬時に確認できるようになり、リアルタイムな工程管理が実現しました。
詳しい導入事例はこちらで紹介しております。
→【工程管理システム】ハンディ端末を用いた作業記録でエクセル管理の工数削減を実現
バーコードの活用によって、あらゆる現場作業をデータ化
手書き帳票やエクセルで工程管理していた現場では、ミスが絶えず、トラブルの都度、膨大な手間をかけて紙帳票を調査していました。
そこで、工程管理の入口であるロット・品番情報をバーコードで自動入力化し、品番入力ミスを撲滅。さらに、原材料の在庫情報や作業実績登録も電子化し、作業順序間違いや入力漏れも大幅に低減しました。
詳しい導入事例はこちらで紹介しております。
→【生産管理システム】既存システムで手書き・手入力が必要だった作業をシステム化!人的ミスや工数の削減を実現
多拠点での在庫状況・作業進捗の一元管理を実現
国内の4拠点で同じ業務を実施していた企業では、拠点間で管理方法が統一されておらず、非効率な工程管理で悩んでいました。そこで、生産管理システムを導入し、複数拠点での作業進捗・在庫状況の一元管理化に成功。
エクセル管理・手作業による集計から脱却でき、月20時間の工数が削減できました。さらに他拠点の情報をリアルタイムに確認できるようになり、社内の情報共有もスムーズになりました。
詳しい事例はこちらで紹介しております。
→【生産管理システム】在庫・作業進捗の一元管理を推進!スモールスタートで複数拠点の管理方法を統一
22種類の生産管理システムをランキングで比較
初期費用相場や選び方のポイントをチェック
生産管理システムをそれぞれの特徴や初期費用相場などで比較したい場合は、「生産管理システムランキング」も是非ご覧ください。生産管理システムは、自社の製品・生産方式・企業規模などに適したものを導入しないと、得られるメリットが限定されてしまいます。事前適合性チェックや生産管理システムを選ぶ前に押さえておきたいポイントも解説していますので、製品選びの参考にしてみてください。






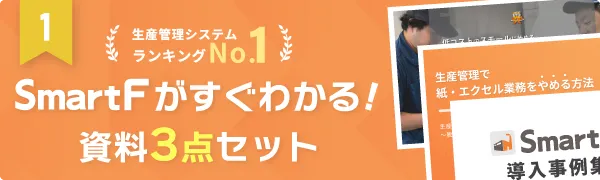

















.jpg)











