製造業向け:エクセル原価管理が向いている企業とは?メリット・デメリット、方法まで解説
公開日:2025年09月29日
最終更新日:2025年09月29日

製造業における原価管理は、収益性向上や無駄なコスト削減に直結する重要な業務です。「うちも原価管理を始めないと」と考え始めた中小企業では、まずエクセルから始めようとするケースが多くあります。
しかし、エクセル原価管理にはメリットだけでなくデメリットもあり、向いていない企業も一部あります。不向きな企業がエクセルで原価管理を行うと、工数が膨大になり、ミスも増えやすくなります。
本記事では、原価管理の基本から目的・重要性、エクセル管理が向いている企業の条件について解説します。具体的なエクセル管理方法や、システムへの移行推奨タイミングも紹介しています。
原価管理とは

原価管理とは、製品やサービスの提供にかかるコスト(=原価)を計画・記録・分析し、適切に管理する業務を指します。特に製造業においては、材料費や労務費、経費など、複数の要素から構成される原価を正確に把握し、最適化することが重要です。
原価管理を徹底することで、収益性の向上だけでなく、無駄なコストの削減や経営の健全化にもつながります。エクセルは手軽に原価管理を始められるツールとして多くの現場で活用されており、コスト意識の浸透にも役立っています。
原価管理の目的
原価管理の主な目的は、製造コストを最適化し、企業の収益力を高めることです。
具体的には、コストの構造を「見える化」し、無駄や非効率を発見・改善することにあります。加えて、原価のデータをもとに価格設定や予算編成などの経営判断に活かすことも重要な役割です。原価管理の目的例は以下のようになります。
- 製品ごとの採算性を把握する
- コストダウン施策を立案・実行する
- 価格設定の根拠をつくる
- 経営判断の材料とする
- 部門間のコスト意識を高める
製造現場の細かなコスト要素を正確に把握し、的確な対策を打つことで、競争力強化や経営の安定につながります。
原価管理の重要性
現代の製造業では、多品種少量生産や納期短縮への対応が求められ、原価管理の重要性は一層高まっています。コスト構造を正しく把握しないままでは、価格競争に巻き込まれた際に利益が圧迫され、事業継続が困難になるリスクがあります。
さらに近年は、原材料費や人件費が上昇し、サプライチェーンリスクも高まっています。このような外部要因にも迅速に対応するには、日頃から原価を細かく管理しておくことが不可欠です。
原価管理を行う方法

製造業で原価管理を行うためには、大きく分けて「エクセルを利用する方法」と「原価管理システムを導入する方法」の2つがあります。それぞれにメリットと注意点があるため、自社の規模やリソースに合わせて最適な方法を選択することが重要です。
エクセルを利用する
エクセルは、原価管理を始める上で最も手軽なツールの一つです。材料費、労務費、製造経費といったコスト項目を一覧表にまとめ、月別・製品別に集計することで、コスト構造を見える化できます。
エクセルの関数やピボットテーブルを活用すれば、集計や分析も比較的容易に行えます。特に、小規模な製造業や、まず試験的に原価管理を導入したい企業にとっては、コストをかけずにスタートできるのが大きな利点です。
ただし、データ量が増えると管理が煩雑になりやすく、人的ミスが起こるリスクもあるため、定期的なチェックとフォーマットの整備が必要です。
原価管理システムを利用する
中長期的に安定した原価管理体制を構築する場合には、専用の原価管理システムを利用する方法が有効です。
原価管理システムは、製造指示、作業実績、在庫管理などの情報と連携しながら、自動的に原価データを収集・集計できるため、人的ミスを減らし、リアルタイムでコストを把握できます。
また、原価の推移分析や予算との比較、異常値のアラート機能なども備えているため、より高度な原価管理ができます。導入には一定のコストと時間がかかりますが、製品ラインナップが多様化している企業や、生産規模が拡大している企業にとっては、長期的な投資効果が見込めます。
エクセルで原価管理を行うメリット
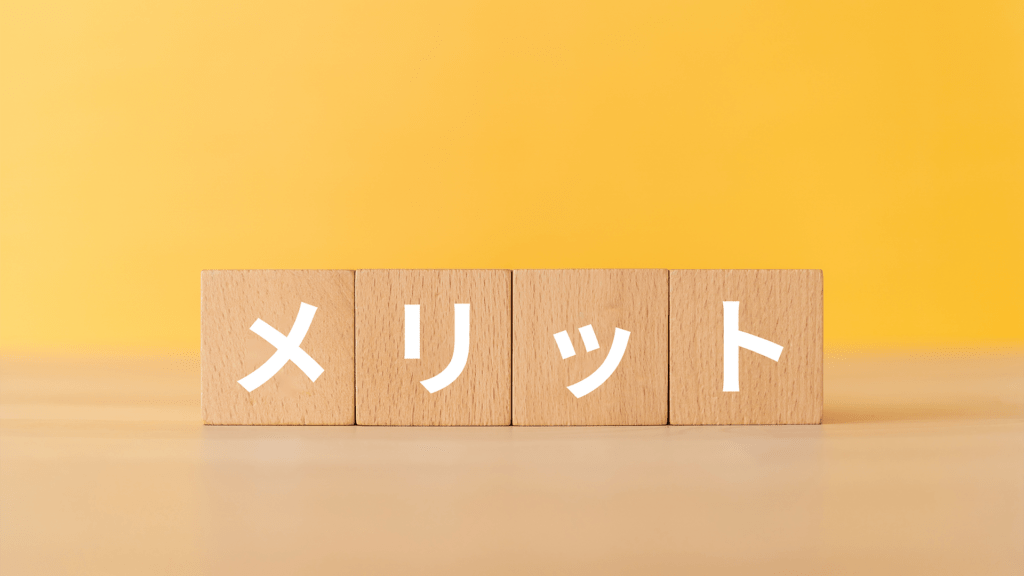
高価なシステムを導入せずとも、エクセルを活用することで一定レベルの原価管理ができます。ここでは、エクセルで原価管理を行うメリットを紹介します。
初期コストがかからない
エクセルは多くの企業に既に導入されているため、追加費用なしに利用できます。高額なシステム導入費用やライセンス料が不要なため、コストをかけずに原価管理ができます。特に中小製造業や、試験的に原価管理を導入したい企業にとっては、リスクの少ない選択肢です。
柔軟にカスタマイズできる
エクセルは自由度が高く、自社の業務内容に合わせたカスタマイズが容易です。製品別・工程別・部門別など、管理したい単位に応じてレイアウトや集計方法を柔軟に設定できます。
また、集計ルールや分析項目を都度見直して変更できるため、業務の変化にも柔軟に対応できるのが特徴です。
データ分析やグラフ化が容易
エクセルには豊富な関数やピボットテーブル機能が搭載されており、データの集計・分析が手軽に行えます。さらに、グラフ作成機能を活用することで、コストの推移や内訳を視覚的に把握することも可能です。これらは報告資料作成や、現場向けのフィードバックにも役立ちます。
使い慣れている人が多い
エクセルはビジネスの現場で広く使われているため、使い慣れている社員が多いのもメリットです。新たなシステム導入時に必要となる教育コストや、操作習得までの時間を抑えられ、すぐに実務で活用できる体制を整えることができます。
特に限られた人員で運用する中小企業にとっては、大きなメリットです。
テンプレートで効率化できる
インターネット上には、製造業向けの原価管理テンプレートが数多く公開されています。これらを活用すれば、一からフォーマットを作成する手間を省き、効率的に原価管理を開始できます。
また、自社用にカスタマイズを加えることで、さらに実務に合ったした管理シートを短時間で構築できます。
エクセルで原価管理を行うデメリット
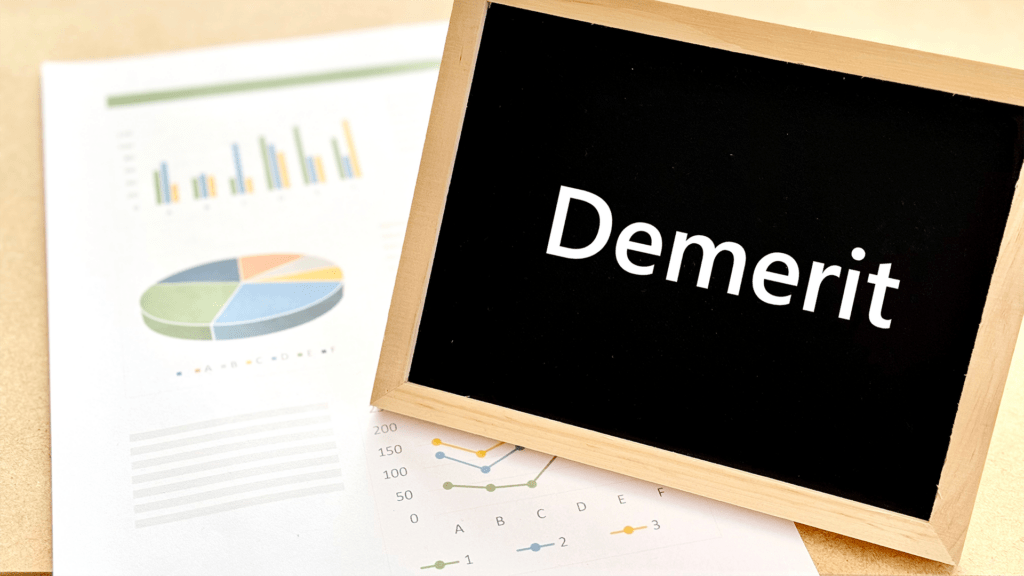
エクセルは手軽に原価管理を始められる反面、一定以上の規模や精度を求める場合には課題も多くなります。ここでは、エクセルで原価管理を行う際に注意すべきデメリットについて解説します。
手作業が多くミスが起きやすい
エクセルによる原価管理は、多くの場合、データ入力や更新を手作業で行う必要があります。このため、転記ミスや計算式の設定ミスが起きやすく、知らないうちにデータに誤りが生じるリスクがあります。
小規模な運用では問題になりにくいものの、製品数や工程数が増えると、ヒューマンエラーによる管理精度の低下が無視できなくなります。
バージョン管理・更新作業が煩雑になる
複数人でエクセルファイルを共有・運用していると、どのバージョンが最新か分からなくなったり、誰がどの修正を加えたのか追跡できなくなることがあります。結果として、更新漏れやデータ不整合が起こり、原価管理そのものが機能しなくなるリスクも高まります。
リアルタイム性に欠ける
エクセルによる管理では、リアルタイムに原価情報を取得・反映するのが難しいという課題があります。現場で発生したコスト情報を手作業で取りまとめ、集計・反映するまでに時間差が生じるため、迅速な経営判断やコスト対策のタイミングを逃してしまうこともあります。
ファイル管理が属人化しやすい
エクセルの原価管理は、特定の担当者が独自にファイルを運用しているケースが多く見られます。担当者が異動・退職した際に、ファイルの管理方法や更新ルールが引き継がれず、ブラックボックス化してしまうリスクがあります。結果として、組織的な原価管理体制の構築が困難になります。
セキュリティのリスクがある
エクセルファイルは手軽にコピー・持ち出しできるため、情報漏洩のリスクもあります。特に、原価情報は企業にとって機密性の高いデータであり、外部流出すれば競争力低下に直結する恐れもあります。アクセス制限や暗号化といった対策が不十分な場合、重大なセキュリティ事故を引き起こすリスクがあります。
エクセルでの原価管理が向いている企業

エクセルによる原価管理は、小規模から中小企業に特に適しています。製品数や工程数が比較的少なく、原価データをシンプルに管理できる環境では、エクセルだけでも十分な効果を発揮します。
原価管理を行う方法でエクセルと原価管理システムのそれぞれが向いている企業の特徴をまとめると以下のようになります。
■エクセル or 原価管理システム それぞれ向いている企業の特長
| エクセルでの原価管理 | 原価管理システムでの原価管理 | |
| 企業規模 | 小規模~中小企業 | 中堅~大企業 |
| 製品数・工程数 | 少ない(製品数・工程数が限定的) | 多い(多品種・複雑な工程管理が必要) |
| 運用体制 | 少人数で管理できる | 専任担当や複数部門での運用が可能 |
| 目的 | まず試験的に導入してみたい | 本格的なコスト最適化を目指したい |
| リアルタイム性 | 重視しない | 重視する |
初期コストをかけずに試験的に原価管理を始めたい企業にとって、エクセルは手軽な選択肢です。
エクセルで原価管理を行う方法

エクセルを使って原価管理を行う場合、計画的に設計・運用することで、より高い効果を得ることができます。ここでは、具体的な進め方をステップごとに解説します。
管理する原価の項目を整理する
まず、管理対象となる原価の項目を整理します。製造業においては、主に「材料費」「労務費」「外注加工費」「製造経費」などが基本項目になります。
これらをさらに細分化し、例えば「直接材料費」「間接材料費」など、実態に即した項目立てをしておくと、後の集計・分析がスムーズになります。最初にしっかりと項目整理を行うことで、管理の抜け漏れを防ぎ、比較・分析の精度が高まります。
原価管理表のテンプレートを作成する
次に、エクセルで原価管理表のテンプレートを作成します。行には製品名や工程名、列には各原価項目(月別、部門別なども含め)を配置し、データ入力しやすい構成にすることがポイントです。
関数やピボットテーブルを活用して、自動集計できるように設定しておくと、作業負担を大幅に軽減できます。また、入力ミスを防ぐために、ドロップダウンリストや入力規則を取り入れる工夫も効果的です。
実績と予算を管理する(予実管理)
原価管理では、実際に発生した原価(実績)だけでなく、事前に設定した予算との比較管理も重要です。予算に対する実績の乖離を把握することで、原価超過や無駄なコストの早期発見が可能になります。
エクセル上で「予算」「実績」「差異」を並べて管理し、差異が発生した場合にはその理由をコメント欄などに記録しておくと、次期の改善に役立てることができます。
原価推移をグラフ化する
月別や四半期別の原価推移をグラフ化することで、コストの変動を直感的に把握できるようになります。エクセルのグラフ機能を使って、例えば折れ線グラフや棒グラフで材料費や労務費の推移を可視化しましょう。
急激な増減や季節変動のパターンが一目で分かるため、コスト増加の要因分析や対策立案に役立ちます。
原価率もあわせて確認する
単純な原価金額だけでなく、売上に対する原価の割合(=原価率)も必ずチェックしましょう。原価率は、「製品別」「部門別」「月別」など多角的に把握することで、どの製品や工程が収益を圧迫しているかを明確にできます。
エクセルでは、「原価 ÷ 売上 × 100」で簡単に算出できるため、原価管理表に原価率計算用の列を設けておくと便利です。原価率の推移をグラフ化すれば、コスト改善活動の成果も可視化しやすくなります。
エクセルでの原価管理で使える関数

エクセルで原価管理を効率よく行うためには、基本的な関数を上手に活用することがポイントです。ここでは、原価管理でよく使われる代表的な関数を紹介します。
| 関数名 | 書式 | 用途 | 使用例 |
| SUM関数 | =SUM(合計したい範囲) | コストの合計を算出する | 材料費・労務費など各項目の合計を出す |
| IF関数 | =IF(論理式, 値が真の場合, 値が偽の場合) | 条件に応じた処理を行う | 原価が予算を超えた場合にアラート表示 |
| VLOOKUP関数 | =VLOOKUP(検索値, 範囲, 列番号, [検索方法]) | 製品コードや工程番号に基づき原価データを参照する | 製品マスタから単価を自動取得 |
| AVERAGE関数 | =AVERAGE(数値1, [数値2], …) | 平均コストを算出する | 複数月の材料費の平均を計算 |
| ROUND関数 | =ROUND(数値, 桁数) | 数値を四捨五入する | 原価や原価率を端数なしで表示 |
| SUMIF関数 | =SUMIF(範囲, 条件, [合計範囲]) | 条件に合うデータだけを合計する | 特定製品だけの原価合計 |
| COUNTIF関数 | =COUNTIF(範囲, 条件) | 条件に合う件数を数える | コスト超過件数をカウント |
| ピボットテーブル | – | データをまとめて集計・分析する | 製品別、月別、部門別などで原価データを自在に集計 |
これら以外にもVBAなどを使えば複雑な演算処理も実施できます。処理したい内容によって柔軟にカスタマイズできることもエクセルでの原価管理の特徴です。
エクセルでの原価管理が難しくなったら原価管理システムの導入を検討

エクセルでの原価管理は、小規模な運用では非常に効果的です。しかし、製品数や工程数、管理項目が増えてくると、次第に限界を感じることが出てきます。具体的には、以下のような兆候が見られた場合、別の手段を検討するタイミングです。
原価管理システムの検討タイミング例
- ファイルサイズが大きくなりすぎて動作が重い
- バージョン管理やデータ更新に膨大な手間がかかる
- 入力ミス・管理漏れが頻発する
- リアルタイムでの原価把握が困難
- 担当者間でファイルの運用ルールにばらつきが出てきた
こうした状況になったら、原価管理専用システムの導入を検討するのが有効です。
原価管理システムを活用すれば、製造現場からのデータを自動で収集し、リアルタイムに集計・分析することができるため、管理精度と業務効率を大幅に向上できます。特に、製品バリエーションが多く、現場のスピードが求められる製造業では、エクセル単独での限界を早めに見極めることが、次の成長につながります。
原価管理システムと同様の機能を含めた生産管理システムなどもあるので、是非自社に合ったシステムをご検討ください。
→ 製造業向け原価管理システム9選!機能や特徴、導入メリット、選び方をまとめて紹介
原価管理もできる生産管理システムSmartF
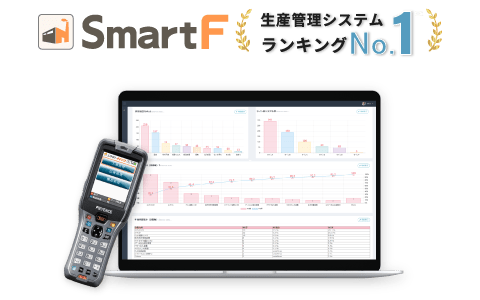
製造業の場合、生産管理システムの原価管理機能を使うという選択肢もあります。生産管理システムSmartFでは、在庫・発注データや生産実績データを一元管理でき、正確な原価管理・原価計算が可能となります。
SmartFの原価管理機能
- バーコード生産実績記録で、工数を自動計算
- 仕入費・外注費・労務費・間接費の4つにわけて自動集計
- 標準原価と実際原価の予実管理
原価計算のためには、在庫・発注管理や工程管理を正確に行う必要があります。しかし、すべての業務を一度にシステム化するのは、現場への負荷が大きくなります。SmartFは、単機能からの段階導入やトライアル導入も可能なので、「まずは在庫管理機能からシステム化してみる」「工数集計から始めてみる」などの段階導入が可能です。
原価管理を目指してスモールスタートした事例
ある化学品業界の製造会社は、原材料価格の変動が大きい中で、正確な原価管理を行うために生産管理システムSmartFを導入されました。導入コストや要件定義の工数が膨らむことを割けるため、まずは在庫管理機能から導入。その時点で、年間3000時間以上の工数削減に成功しています。
在庫管理機能の導入に成功した次は、受注管理や工程管理の機能に拡張予定です。そして、最終ステップとして原価管理まで行っていくスケジュールで運用されています。
今後もSmartFの機能追加を進め、幅広い生産データを一元管理できる生産管理システムとして完成させていく予定です。既に在庫管理にてハンディーターミナルやシステムの運用に慣れることができたので、他の機能もスムーズに導入できると思います。
(中略)
そして、工程管理までシステム化できた後は、アナログ管理では難しかった原価管理まで実現したいと考えています。原材料の価格変動も大きい中、精緻な原価管理にはシステムの力が不可欠です。
導入事例インタビュー記事はこちら:紙・エクセル管理をやめて年間3000時間以上の工数削減!先入先出・期限管理の精緻化で品質管理体制の強化まで実現
原価管理もできる生産管理システムを導入したい方はこちら
原価管理をシステム化すべきかお悩みなら
原価管理をすべきとはわかりつつ、システム導入まですべきか悩まれている企業は多くいらっしゃいます。
そんな担当者向けに、「原価管理システムは必要?現状見える化ガイド」を無料配布しております。
自社の原価管理の成熟度を診断できるセルフ診断シートも付属していますので、自社の現状分析にもお役立ていただけます。





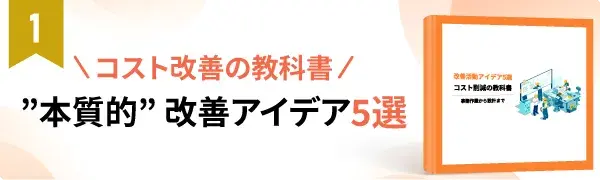

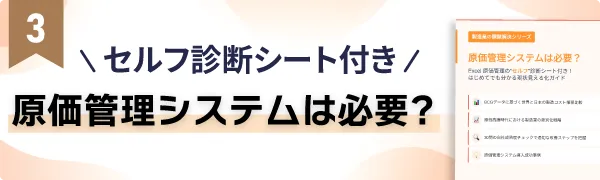


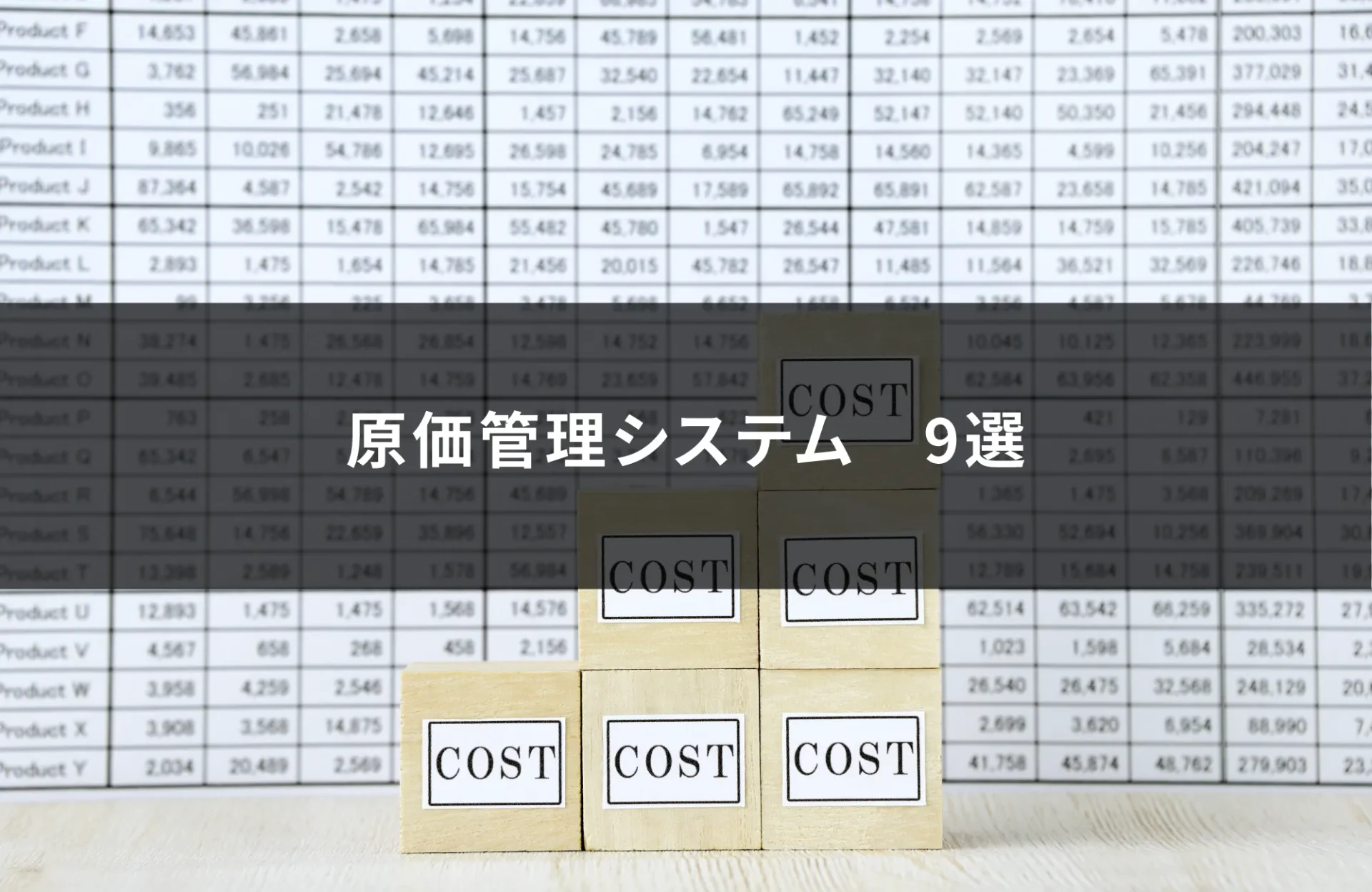



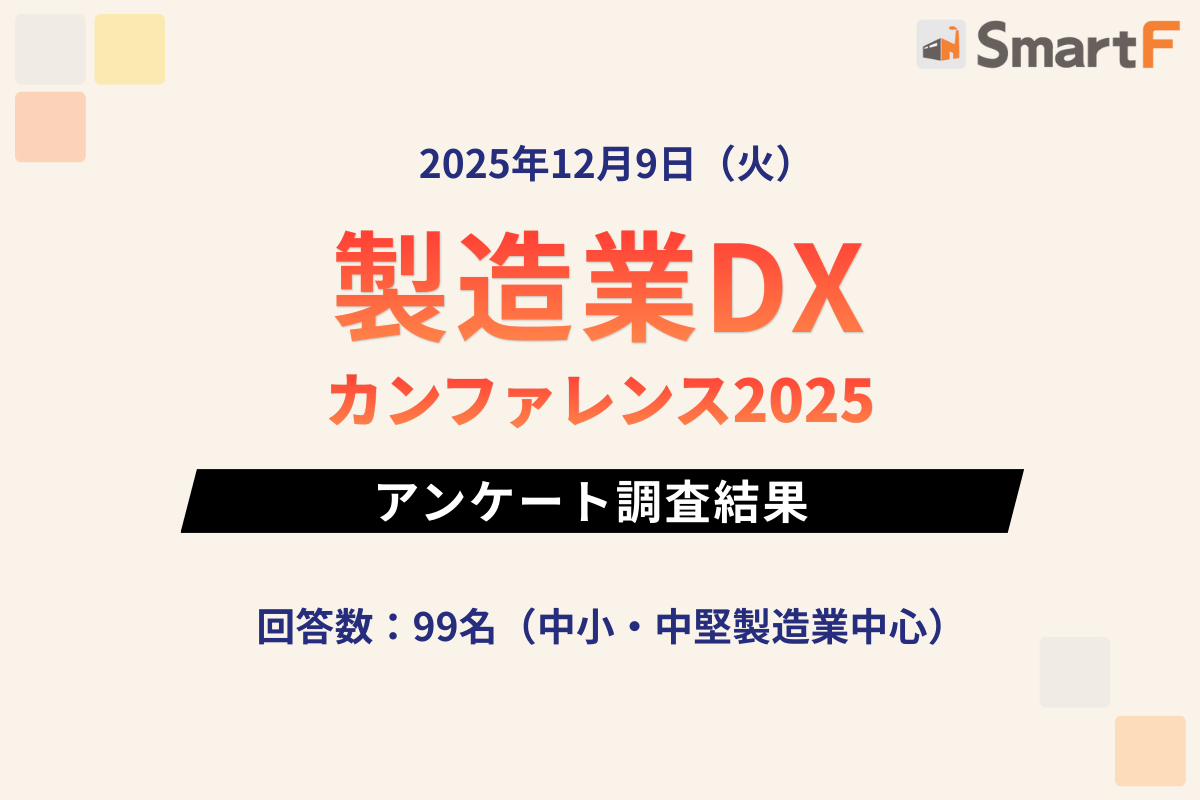




.jpg)







