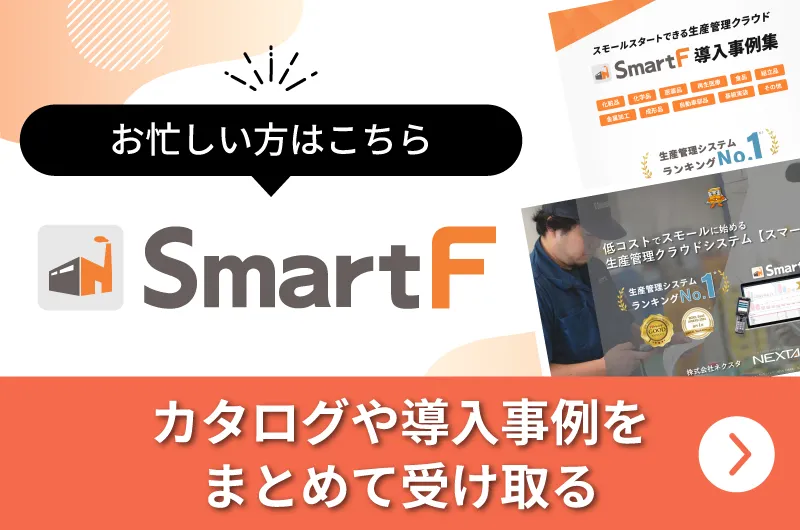クラウド型生産管理システムとは 機能・費用・導入手順について解説
公開日:2020年03月03日
最終更新日:2026年01月15日

以前は生産管理システムが高額で、「中小製造業には導入が難しい」とされていました。しかし、近年では導入費を抑えた「クラウド型」のシステムが登場しています。このおかげで、中小中堅企業も現場DXにチャレンジしやすくなってきました。
しかし、クラウド型の費用以外のメリット、もしくはオンプレミス型の方が向いているケースがあることを知らない方もいるかと思います。本記事では、クラウド型の生産管理システムのメリット・デメリット、失敗しない選び方などをわかりやすく解説します。
クラウド型の生産管理システムとは

クラウド型の生産管理システムは、自社開発ではなく、システム会社が開発したソフトウェアをインターネットを通じて利用する生産管理システムです。
そもそも「クラウド型」とは
ソフトウェアのクラウド型とは、インターネットを通じてサーバーやストレージ、ソフトウェアなどのIT資源を必要なときに必要なだけ利用できる仕組みです。クラウドの特長としては、以下のようなものがあります。
- 初期費用が抑えられる
- インターネットに繋がっていれば場所を選ばずに利用できる
- 定期的にアップデートされる
クラウドは場所を問わず利用でき、リモートワークやデジタル化を支える重要な技術です。また、システムベンダーが新機能追加などのシステムアップデートを行うと、全ユーザーが新機能を使えるようになる点も特徴です。
ちなみに、生産管理システムは「クラウド型」以外に、従来型の「オンプレミス型」というものもあります。
クラウド型とオンプレミス型の違い
オンプレミス型とは、企業や組織が自社内にサーバーやネットワーク機器、ソフトウェアを設置し、自ら運用・管理する形態を指します。「オンプレミス(on-premises)」は「敷地内で」という意味です。
クラウド型とオンプレミス型の違いをまとめると、以下の表のようになります。
| クラウド型 | オンプレミス型 | |
| サーバの管理方法 | ベンダーが所有・管理するサーバを使用 | 自社にサーバを設置して使用。システム導入後のサーバ管理も自社で行う |
| 使用するネットワーク | インターネット経由での使用 外出先からでも利用可能 | 自社のネットワーク内のみでの使用。外出先(自社ネットワーク外)では使用不可 |
| 料金体系の違い | ||
| セキュリティ | ベンダーの対策に依存する | 自社でポリシーを設定し完全管理可能 |
クラウド型は、システム導入時にサーバを設置する必要がなく、初期導入費を抑えることができますが、継続的に月額使用料を支払います。月額使用料は機能の組合せや使用するデバイス数(または使用人数)によって異なります。
一方で、オンプレミス型は、自社の生産方式に合わせたオリジナル仕様を細かく作り込むことができますが、費用は高くなります。また、システムの保守をベンダーに依頼すると保守料金が必要になります。
簡単に言うと、システム販売元が準備したシステムやサーバの「レンタル使用料を支払う」のがクラウド型、システムをサーバごと「丸ごと購入する」のがオンプレミス型です。
クラウド型生産管理システムの主な機能

クラウド型生産管理システムの代表的な機能は、以下の通りです。
生産計画と実績管理
クラウド型生産管理システムでは、生産計画の立案、進捗状況の更新、実績データの収集をリアルタイムで行うことが可能です。この機能により、工程遅延や製品不良などの問題を即座に把握し、迅速に対応できます。
また、計画と実績のデータを蓄積することで、今後の計画精度を高める分析にも活用できます。
在庫・購買・原価管理
部品や資材の在庫状況をリアルタイムで確認でき、過剰在庫や欠品を防止します。
また、購買履歴や仕入価格を一元管理し、原価を正確に算出することで、適正在庫の維持とコスト削減が可能です。さらに、購買計画と生産スケジュールを連動させることで、無駄な発注や納期遅延のリスクを低減します。
工程進捗の可視化とトレーサビリティ
各工程の進行状況をリアルタイムで可視化し、遅れや不良の発生を早期に発見できます。
また、製品ごとの製造履歴や使用部品、検査結果を記録することで、トレーサビリティを確保できます。品質問題発生時には、原因の特定やリコール対応を迅速に行うことができ、リスク管理も容易になります。
他システムとの連携
生産管理システムは単独で完結するものではなく、ERPや会計システム、販売管理システムなどと連携することで、より大きな効果を発揮します。
クラウド型はAPIやCSV、標準連携機能を備えているケースが多く、既存システムとのデータ連携が容易です。これにより、受注情報から生産計画、在庫管理、原価計算、請求までを一貫してデジタル化し、手入力によるミスを削減しながら業務全体を効率化できます。
クラウド型生産管理システムのメリット6つ
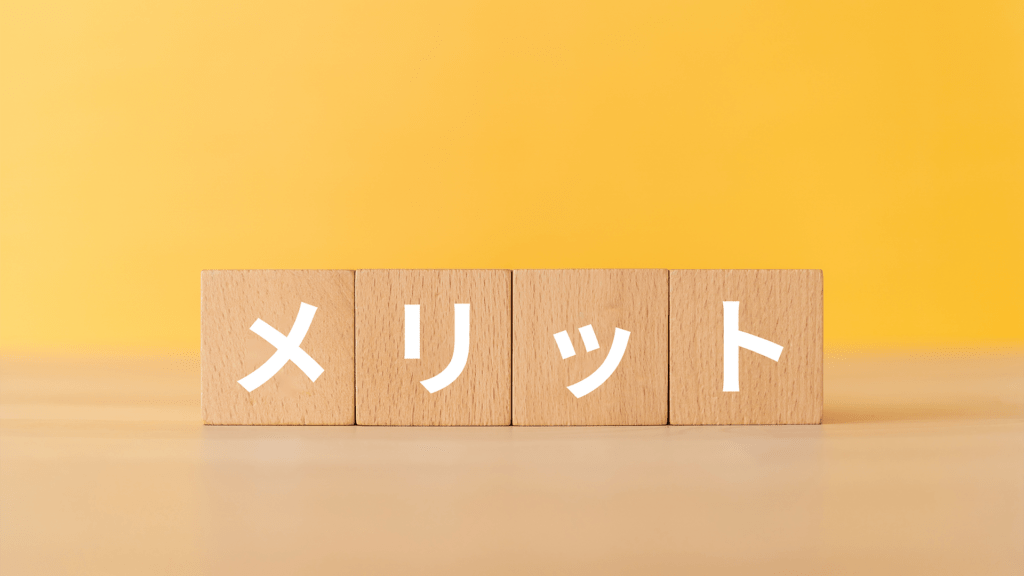
クラウド型生産管理システムには次の6つのメリットがあります。
- 初期費用が安い
- IT専任担当者がいなくても導入しやすい
- 導入スピードが速い
- 複数の拠点からアクセスできる
- 定期的にアップデートされる
- 導入後の拡張性が高い
ここでは、それぞれのメリットが生み出す効果も簡単に説明します。
初期費用が安い
クラウド型の生産管理システムは、導入時にサーバを自社で購入する必要がなく、その分コストを抑えることができます。オンプレミス型システムは、初期費用だけで数100万円〜数1000万円かかる傾向にあるのに対し、クラウド型システムの初期導入費用は数10万円程度に抑えられるケースもあります。
中小中堅製造業など、初期費用に大きな費用をかけることが難しい企業にとっても、クラウド型システムは導入しやすいと言えます。
IT専任担当者がいなくても導入しやすい
クラウド型生産管理システムは、IT専任担当者がいなくても導入しやすいため、特に中小中堅製造業にとっては2つのメリットがあります。1つ目は、オンプレミス型システムで必要になる、以下のようなサーバー保守業務が必要ないことです。
■クラウド型生産管理システムで不要なサーバー保守業務
- サーバやネットワーク機器の監視(常時)
- トラブル発生時の対応(随時)
- サーバ・ソフトウェアのバージョンアップ対応(随時)
- 定期メンテナンス(週1回 / 月1回)
2点目のメリットは、システム導入時の要件定義の負担が少なくなることです。オンプレミス型システムはカスタマイズ性が高いため、要件定義の工数も大きくなります。自社の業務フローに即した要件定義は、IT担当ではない従業員にとっては大きな負荷となります。
クラウド型であれば、カスタマイズなし、もしくは最低限での導入が多くなるため、要件定義の負担は最小限に抑えられます。従業員1人がメインの業務とIT業務を兼任している中小規模の会社などは、業務負荷を加味してクラウド型を選ぶケースも増えつつあります。
参考:生産管理システムの要件定義の負担感
生産管理システムは生産全体を効率化できるシステムであるため、カスタマイズでシステムを構築する場合は要件定義の工数も大きくなります。システムベンダーに要望を出すために、自社のあらゆる製造情報をまとめ上げて整理する必要があり、担当者の負担が大きくなります。
実際に、この工数を避けるために、オンプレミス型ではなくクラウド型の生産管理システムを選ぶ中小中堅企業も少なくありません。
→ 実際の企業(化学品メーカー)の声はこちら
導入スピードが速い
クラウド型は、システムベンダーがすでに用意したサーバーやソフトウェア、ネットワーク環境を利用できるため、導入までの期間が短い点も特徴です。
オンプレミス型では、サーバーの調達や設置、ネットワーク構築、ソフトウェアのインストールなど、導入準備に必要な作業がクラウド型より多くあります。そのため、導入までの期間は半年以上、長ければ1年以上かかることもあります。
一方、クラウド型は半年前後での導入も可能で、急な業務改善や新拠点立ち上げにも柔軟に対応できます。
複数の拠点からアクセスできる
クラウド型の大きな特長が、モバイル対応やリモートアクセス機能です。現場担当者はスマートフォンやタブレットからリアルタイムで情報を確認・入力でき、工場外や出張先からでも生産状況を把握できます。
また、管理者や経営層も、オフィス以外の場所から進捗や在庫をチェックでき、迅速な意思決定が可能になります。この機能により、リモートワークや多拠点間の情報共有がスムーズになります。
定期的にアップデートされる
クラウド型は、ベンダーによる定期的なアップデートで常に最新機能を利用できます。AI関連機能など、新たなIT技術の開発スピードが加速している近年において、これは非常に大きなメリットと言えます。
オンプレミス型では一般的に、バージョンアップのたびに追加費用や作業負担が発生します。追加費用を避けるためにシステム更新を避けていると、レガシーなシステムを使い続けることになり、競争力低下に繋がりかねません。これに対し、クラウド型ではシステム更新は基本的に自動かつ基本無料で行われ、システムの老朽化リスクを回避できます。
また、法改正や業界標準への対応も迅速に行われるため、コンプライアンスの確保にも有利です。
参考:「2025年の崖」問題
経済産業省のレポートでも、既存システムの過剰なカスタマイズによる複雑化・ブラックボックス化について問題提起されています。これらの課題を解決できないままだと、2025年以降に最大12兆円/年の経済損失が生じる可能性があると言われています。この問題は「2025年の崖」と呼ばれています。
導入後の拡張性が高い
生産管理システムによっては、複数の機能を組み合わせたり、後から機能追加することができます。
■クラウド型生産管理システム 導入後の拡張例
- 機能に慣れてから少しずつ拡張(例:在庫管理と工程管理の機能から導入し、それらの運用に慣れたら原価管理や品質管理まで展開)
- 生産状況の変化に合わせて拡張(例:新製品の製造が始まり、期限管理やトレーサビリティ強化が必要になり機能追加)
導入後の機能追加は、対応可能なシステムと不可のシステムがあります。パッケージ内の機能をすべて入れなければいけない生産管理システムもあるので、事前確認が必要です。
クラウド型生産管理システムのデメリット4つ
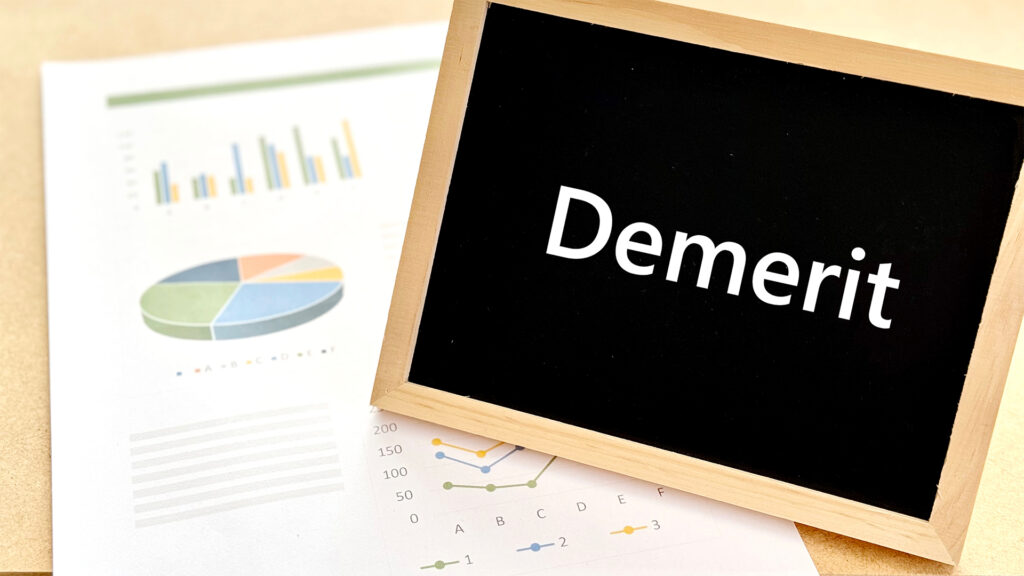
一方で、クラウド型生産管理システムには次の4つのデメリットがあります。
- 細かいカスタマイズが難しい
- 情報セキュリティ対策を自社で管理できない
- データの連携が取りづらい
- ベンダーへの依存が大きい
※導入環境や目的によっては発生しないものも含まれています。
自社の環境や使用目的によってはオンプレミス型の方が適切な選択になることもあります。クラウド型のデメリットを把握したうえで、比較検討することが大切です。
細かいカスタマイズが難しい
提供されるシステム仕様がベンダーによって決められているクラウド型の生産管理システムは、細かいカスタマイズへの対応が難しいです。
自社の生産の流れや工程が特異的な場合、クラウド型の標準パッケージでは対応しきれない可能性があります。とはいえ、自社の運用が特殊かどうかの判断は難しいかと思うので、候補の生産管理システムベンダーに相談することをおすすめします。クラウド型システムによっては、一部個別カスタマイズが可能な場合もあります。
参考:「あえてカスタマイズしない」クラウド型を選ぶケース
新たに立ち上げた製造部門や、スタートアップ企業では、「製造業の標準運用に合わせたい」というニーズで、クラウド型生産管理システムを選ぶケースもあります。
実際に当社でも、「カスタマイズを重ね、自社の独自のやり方でしか製造ができなくなることを避けたい」という理由で、パッケージ型のクラウドシステムを探していたお客様がいます。
→ 実際の企業(ロボット機器製造会社)の声はこちら
情報セキュリティ対策を自社で管理できない
クラウド型は、ベンダーが所有・管理するサーバを利用するため、情報セキュリティ対策を自社で管理できない不安とリスクがあります。
システム選定時に、セキュリティに関してどういった機能を備えているか、また万が一、不正アクセスや情報漏洩があった際にどんな対策を取るのか、などを導入前に入念に確認しておくことが大切です。
また、生産管理システム内のデータに機密情報が含まれていないか、自社のセキュリティ要件を満たしているかも事前にチェックしておくと安心です。
オンプレミス型システムとのデータ連携が取りづらい
既にオンプレミス型のシステムを導入しており、クラウド型生産管理システムとデータの連携を行いたい場合は、サーバが自社と外部の2つに分かれることに注意です。
共通のデータを利用するには、CSVデータを出力して、オンプレミス側のサーバから取り込むといった対応が必要です。
クラウド側のベンダーがどのように対応してくれるか、また自社に新たな工数が増えないか、などを事前に確認しておきましょう。
ベンダーへの依存が大きい
クラウド型は、システムの保守や運用、アップデートをベンダーに一任するため、特定のサービスに強く依存する構造になります。
契約条件や料金体系の変更、サービス終了などのリスクがあるため、将来的なコスト増や乗り換えの難しさが課題となります。また、ベンダー側のトラブルや障害が発生した場合、復旧対応を自社でコントロールできないこともリスク要因です。
こうした依存リスクを軽減するには、サポート体制を入念に確認し、複数ベンダーとの比較検討を行うことが重要です。
クラウド型生産管理システムを選ぶ際の注意点

メリット・デメリットを知ったうえで、クラウド型システムでの選定を進める場合、以下6点をチェックすると導入の失敗を避けやすくなります。
- テスト導入が行えるか
- 自社のネットワーク環境は安定しているか
- 機密情報取り扱いに関する社内ルールは問題ないか
- 既存のシステムと連携できるか
- カスタマイズはどの程度必要か
- 導入支援サポートはあるか
テスト導入が行えるか
クラウド型生産管理システムを導入する際は、テスト導入やトライアルを行えるかどうかを確認しましょう。
下記のような、実際に利用してみないと確信がもてない部分をチェックするために、テスト導入は有効です。
- 生産計画、在庫、進捗管理が業務に対応できるか
- 現場担当者が直感的に使えるか
- 動作が遅くないか
- 既存システムとの連携やCSV出力が可能か
- スマホ・タブレット・ハンディ端末などでも問題なく使えるかなど
今までになかったシステムの導入は、一時的に生産現場に影響します。導入失敗で現場の混乱を招かないように、事前にテスト導入を行えるサービスを選ぶことをおすすめします。
自社のネットワーク環境は安定しているか
クラウド型の生産管理システムは、通信環境が不安定な現場では活用が難しくなります。事務所だけでなく、実際にデバイスを使用する工場内で、安定したインターネット接続を確保できるか確認しておきます。
特に複数拠点や海外工場で利用する場合、専用回線などの回線品質確保が必要です。導入前に現状の通信環境をチェックし、必要に応じて改善策を講じましょう。
機密情報取り扱いに関する社内ルールは問題ないか
自社管轄外のサーバーを利用するというクラウド型サービスの特性上、不正アクセスや情報漏洩のリスクから、クラウド型サービス自体の導入が厳しい企業もあります。
導入を検討しているシステムのセキュリティ強度をしっかりと検討するとともに、社内の情報セキュリティや機密情報取り扱いのポリシーに則っているか確認しておくことが重要です。
既存システムと連携できるか
既に自社で利用しているシステム(ERPや会計、販売管理など)がある場合、検討中の生産管理システムと連携可能かどうかも要確認です。
クラウド型の場合、ベンダーやシステムによって外部連携の対応範囲が異なります。特に自社専用のカスタムシステムや古いオンプレミス環境とのデータ連携は、追加開発が必要になる場合があります。
カスタマイズはどの程度必要か
クラウド型は基本的に標準機能を前提としているため、大規模なカスタマイズは難しい場合があります。
過剰なカスタマイズを求めると、費用が高騰し、アップデートのたびに互換性問題が発生するリスクもあります。そのため、導入前に「どこまで標準機能で対応できるのか」「カスタマイズが必要な範囲はどこか」を明確にし、ベンダーとすり合わせを行うことが重要です。
可能であれば、業務プロセスの標準化も併せて検討しましょう。
導入支援サポートはあるか

クラウド型の生産管理システムの導入を成功させるには、導入支援サポートが必要です。特に、「自社にIT専任担当者がいないから」という理由でクラウド型を選んだ企業にとっては、システムベンダーのサポートの重要性が高いと言えます。
クラウド型システムは月額料金で売上を上げていく仕組みなので、ユーザーがシステムを長く使い続けるためのサポートが手厚いシステムベンダーは多くあります。標準でサポートが付いている場合もあれば、費用によってサポートの手厚さが変わる場合もあるので、事前に確認することをおすすめします。
クラウド型生産管理システムの導入の手順

実際にクラウド型生産管理システムを導入する場合には、以下のような手順で進めるとスムーズです。
| 項目 | 概要 | |
| 1 | 現状分析と課題の明確化 | 現在の生産管理プロセスを分析し、在庫管理や情報共有の課題を明確にする。導入目的を具体化する。 |
| 2 | 要件定義と目的設定 | 必要な機能や予算、運用体制を定義し、導入で達成する目標を設定する。 |
| 3 | ベンダー選定と比較検討 | 複数のベンダーを比較し、機能・コスト・サポート体制を評価する。 |
| 4 | 業務プロセスの再設計 | システム標準に合わせて業務フローを再構築し、手作業を削減する。業務を標準化する。 |
| 5 | 導入計画の策定 | 段階的導入か一斉導入かを決定し、導入までの全体スケジュールを立てる。 |
| 6 | データ整備とマスタ登録 | 製品や部品のマスタデータを整備し、システムに登録する。 |
| 7 | システム初期設定 | アカウントや権限などの初期設定を行う。 |
| 8 | テスト運用(トライアル) | 本稼働前に試験運用を行い、機能や使い方を確認する。 |
| 9 | 社内教育とマニュアル整備 | 操作研修を実施するなど、現場担当者がスムーズに運用できる体制を作る。 |
| 10 | 本稼働と定着化支援 | システムを本稼働させ、運用を安定させるまでベンダーと連携する。 |
重要なことは、システム選定を始める前に、自社の現状分析をしておくことです。自社の現在の生産状況をシステムベンダーに明確に共有できると、より実態に沿った提案を受けやすくなります。
また、上記の代表的なシステム導入の流れの中で、システムベンダーからサポートしてもらえる範囲も確認しておくと安心です。導入支援が充実しているシステムベンダーであれば、業務プロセス再設計や導入計画など、初期の段階から支援してもらえる場合もあります。
中小中堅企業など、自社のリソースが少ない企業は、導入支援が手厚いシステムベンダーを選ぶと、導入が成功しやすくなります。
導入事例から見るクラウド型生産管理システムの効果

実際にクラウド型生産管理システムを導入して得られる効果を、弊社サービス「SmartF」の導入事例から紹介します。多くの導入事例に見られる、クラウド型生産管理システムの導入効果の共通点は以下3点です。
- 紙・エクセルからの脱却による工数削減・属人化解消
- 生産に関する情報の一元管理による効率化
- ハンディ端末とのリアルタイム連携でミス防止
| 業界名 | 改善 |
| 成型品業界30~99人 | |
| 化粧品業界~30人 | |
| 組立品業界100~299人 | |
| 組立品業界~30人 | |
| 金属加工業界~30人 | |
| 金属加工業界30~99人 | |
| 成型品業界300~499人 |
→ その他のクラウド型生産管理システムによる改善事例はこちら
クラウド型生産管理システムのよくある質問
クラウド型生産管理システムについてよくあるご質問をまとめました。
-
導入コストはどのくらいですか?
-
クラウド型の場合、初期費用は比較的低く、月額利用料で始められるプランが一般的です。
費用は「利用ユーザー数や端末数」「導入する機能範囲」「サポート内容」によって異なります。最小限の機能であれば、月額数万円程度からスタートできるケースもあります。詳細な見積りは、要件を整理したうえでベンダーに確認しましょう。
-
導入までにかかる期間は?
-
クラウド型はオンプレミス型に比べてセットアップが早いことが特徴です。
標準機能を利用する場合、3~6か月程度で稼働できることが多いです。一方、業務に合わせたカスタマイズやシステム連携を行う場合は、さらに数か月を見込む必要があります。
-
どんな業種で利用されていますか?
-
食品、化学、医薬品、金属加工、機械製造など、多様な製造業で導入実績があります。
導入を検討する際は、自社の業界に必要な機能(ロット・トレーサビリティ、工程管理、原価管理など)が標準で備わっているか確認することが重要です。
-
ITに詳しくない現場でも使えますか?
-
最近のクラウド型システムは、スマートフォンやタブレット対応、バーコード・ハンディ端末連携などを標準機能として搭載しており、操作も直感的です。ITリテラシーが高くないスタッフでも、短期間の研修で使いこなせるケースが多いです。
-
既存の販売管理や会計システムと連携できますか?
-
多くのクラウド型生産管理システムは、CSVデータの入出力やAPIによるシステム連携に対応しています。販売管理・購買・会計と連携すれば、受注から生産、出荷、請求までの情報を一元化でき、手入力や転記ミスを防止できます。
-
導入後のサポートはありますか?
-
ベンダーごとに内容は異なりますが、多くの場合、初期設定や操作説明、稼働後のサポートを提供しています。チャットや電話、オンライン会議など、リモートでのサポート体制を整えているベンダーも増えています。
後から拡張OK・導入支援が手厚いクラウド型生産管理システムはSmartF

当社ネクスタでは、「スモールスタート」に強みを持つクラウド型の生産管理システム「SmartF」を開発・提供しています。クラウド型システムで現場DXを推進したい、多くの企業に選ばれています。
■クラウド型生産管理システムSmartFが選ばれる理由
- 豊富な機能から、必要最低限の機能に絞ったスモールスタート
- 後から柔軟に機能追加
- 導入支援付きトライアルが利用可能
必要最低限の機能からスモールスタートし、コストを抑えながら継続的な改善ができるため、生産管理システムの段階的な導入が可能となります。実際に、SmartFを選んだ理由をヒアリングした結果、最も多い理由がこの「スモールスタートが可能だったから」です。
さらに、導入支援も手厚く行っています。導入スケジュールやマニュアルの作成、現場運用のヒアリングによるシステム活用の提案など、失敗しないシステム導入を支援しています。トライアル導入時点からサポート担当がつくので、IT担当者がいない企業も安心してご相談いただけます。
クラウド型の生産管理システムを導入したい方はこちら
22種類の生産管理システムをランキングで比較
初期費用相場や選び方のポイントをチェック
生産管理システムをそれぞれの特徴や初期費用相場などで比較したい場合は、「生産管理システムランキング」も是非ご覧ください。生産管理システムは、自社の製品・生産方式・企業規模などに適したものを導入しないと、得られるメリットが限定されてしまいます。事前適合性チェックや生産管理システムを選ぶ前に押さえておきたいポイントも解説していますので、製品選びの参考にしてみてください。



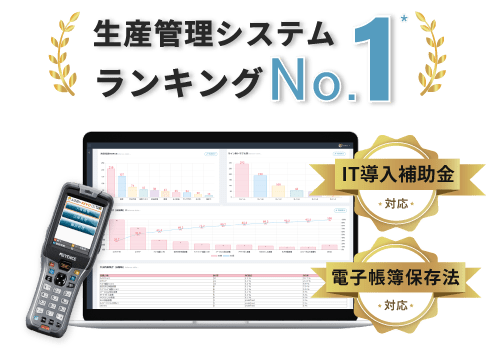





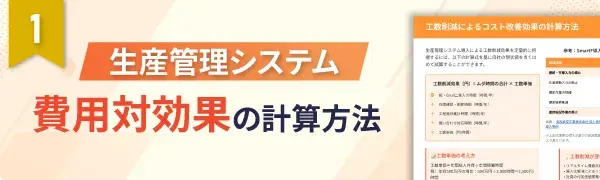




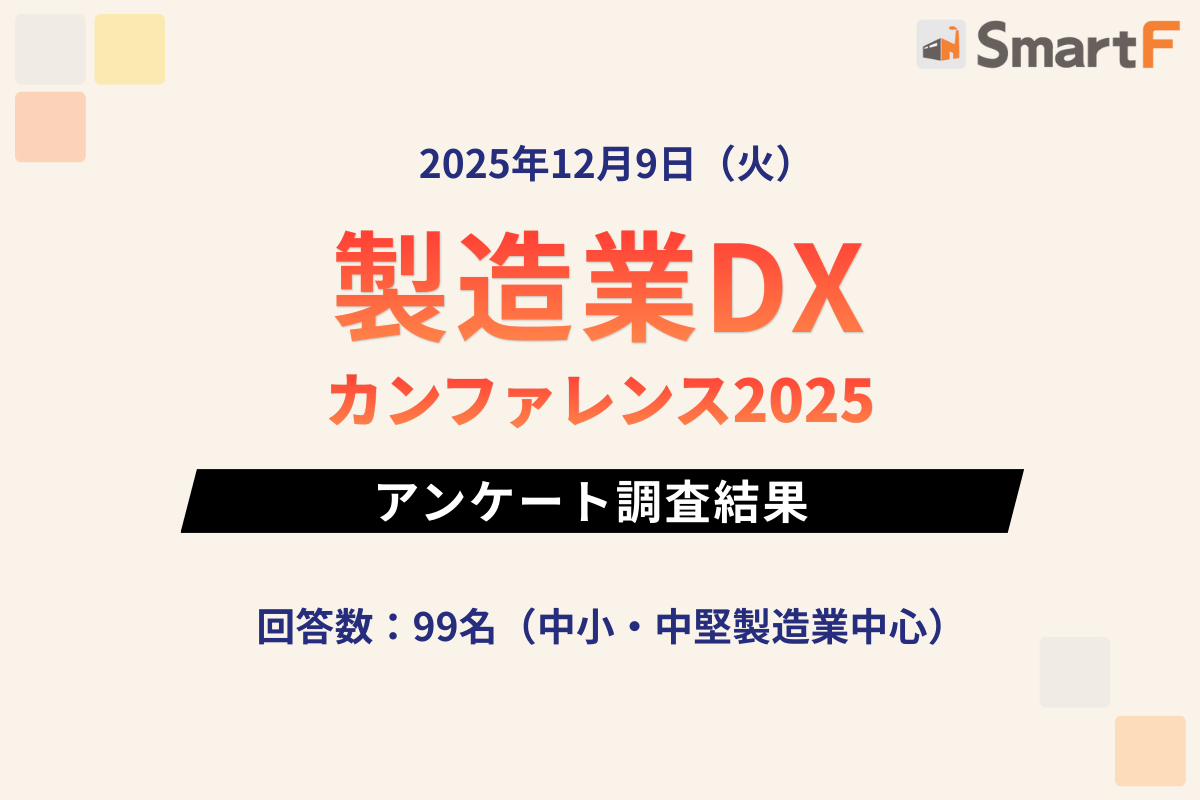


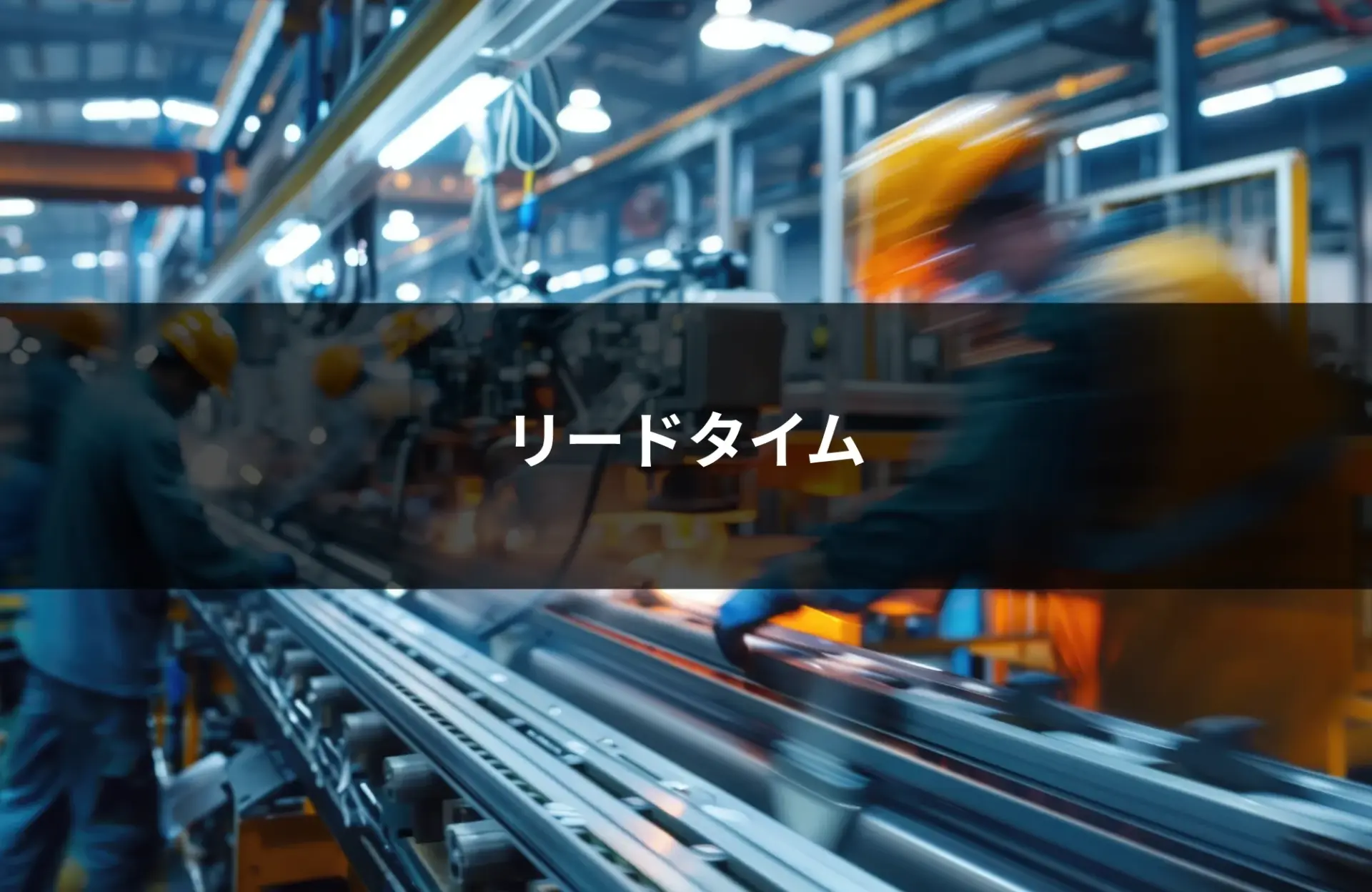


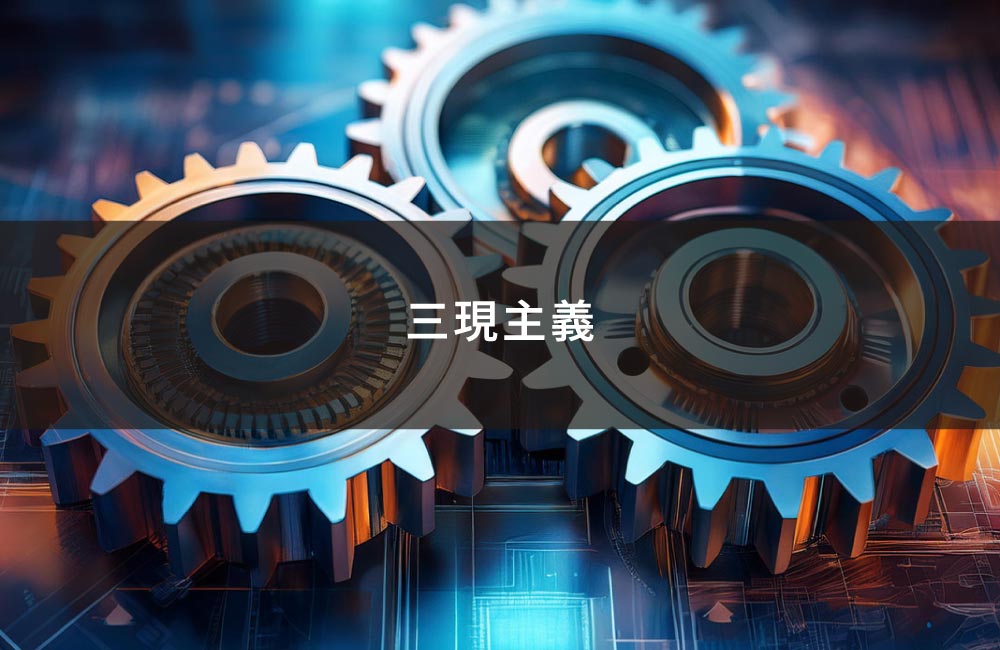
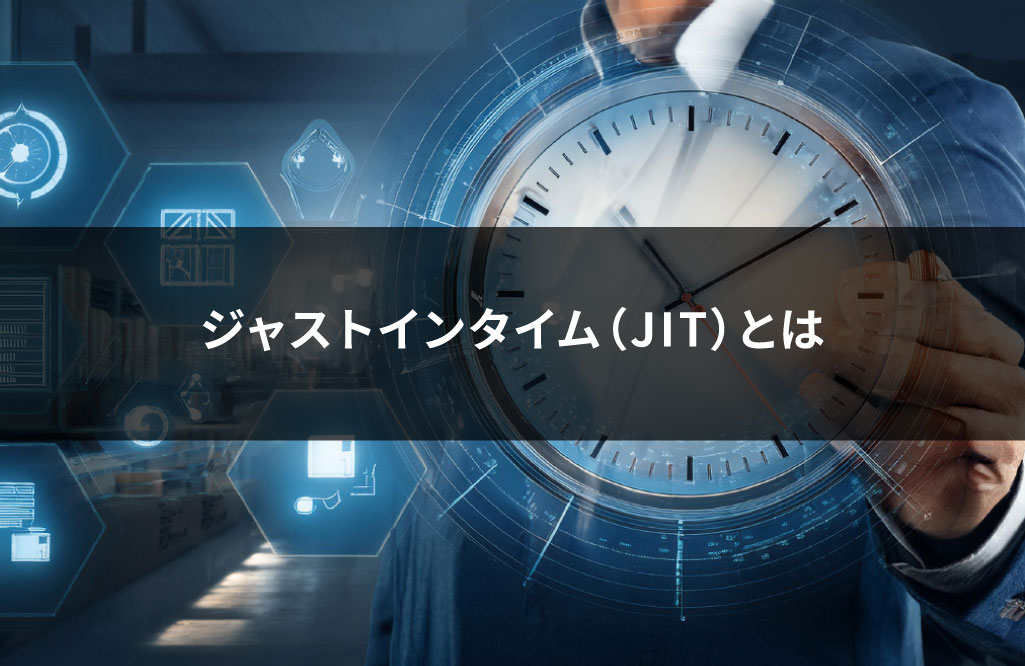





.jpg)