バーコード在庫管理のメリットは?ハンディターミナルorスマホ?始め方から選び方まで徹底解説
公開日:2020年03月03日
最終更新日:2025年10月22日

在庫管理にバーコードを導入すると、紙・エクセルで行っていた業務のミス・手間を削減し、より正確な在庫管理を実現できます。実際に、ハンディーターミナルを活用し、日頃の在庫管理や棚卸しの工数を3分の1圧縮しているという企業の事例もあります。
しかし、実際の導入メリットや端末の選び方、バーコード管理のやり方のイメージが沸かず、検討に踏み切れていない企業の声も耳にします。本記事では、バーコードを活用した在庫管理のメリット・デメリット、端末の選び方から、導入コストを抑える方法まで、徹底解説します。
バーコード在庫管理の3大メリット
手書きや手入力での在庫管理からバーコード管理に移行すると、以下3つの効果が期待できます。
- 入力ミス・入力漏れがなくなる
- 棚卸作業の工数を大幅削減できる
- ロット番号や期限管理などの品質管理もできる
総じて、ミスや手間をなくしながらも、正確な在庫管理が可能となるのが、バーコード管理のメリットです。
入力ミス・入力漏れがなくなる

バーコード管理ではスキャン1つで正確な情報が記録できるため、入力エラーや情報の確認ミスをほぼゼロにできます。
手作業による記録では、ヒューマンエラーが避けられません。文字の読み間違いや書き間違い、入力漏れなどが在庫差異の原因になります。
バーコードを使った在庫管理を活用すると、バーコードをハンディターミナル等でスキャンし、連携しているシステムへ在庫情報を直接更新できるようになります。人的ミスが起きやすい手作業をなくすことで、エラー削減が期待できます。
さらに、入力補助として端末に「登録内容のプレビュー表示機能」や「アラート表示機能」を持たせると、読み間違いも防げます。
棚卸作業の工数を大幅削減できる

手書きやエクセルの在庫管理をバーコードに置き換えると、ミスだけでなく工数も大幅に削減できます。バーコードをハンディ端末で読み取るだけで在庫数を更新できるため、以下のような典型的な在庫管理のムダをなくせます。
- 手書き棚札からエクセルへの転記(二重作業)
- 在庫確認のために現場まで行く手間
特に工数削減の効果を発揮するのは、棚卸しです。従来の棚卸は、棚ごとに製品を目視し、数量をカウントし、紙に記録する……という作業でした。しかし、バーコード導入後は「バーコードをピッとスキャン → 入力完了」の作業を繰り返すだけになります。実際に、バーコードでの在庫管理導入後、1/3の時間で作業が終わるようになった事例もあります。
ロット番号や期限管理などの品質管理もできる

バーコードで管理できるのは、品番や在庫数だけではありません。以下のような情報も、バーコード1つで管理できます。
| 活用例 | 効果 | |
| エリア管理 | 入荷登録時にエリア情報も登録し、システム上で保管場所を管理 | 在庫紛失をなくす |
| ロット管理 | 原材料のロットを登録・追跡 | ロットトレースを強化できる |
| 期限管理 | 原材料の期限を入荷検品時に登録し、製造用に出庫する際に期限切れがないか確認 | 期限切れ原材料の誤使用を防ぐ |
| 生産情報の一元管理 | 完成品の製造日・製造ライン・工程別作業指示をバーコードスキャンで確認 | トレーサビリティ確立で不具合発生等に備えられる |
上記のバーコード管理の特性を活かせば、ロットトレースやリコール対応、期限管理にも応用できます。特に、業界の品質基準でトレーサビリティが求められる、食品業界・医薬品業界・自動車業界等では、必須の品質管理と言えます。
バーコードを使った在庫管理のやり方
バーコード管理は、在庫管理において以下の業務で活用できます。
- 入荷検品
- 入出庫(ピッキング・製造現場への払い出し)
- 出荷管理
- 棚卸し
一般的、かつシンプルな使い方としては、入荷検品時にバーコードラベルを貼付し、在庫を移動する際に同じバーコードで情報を更新していく流れです。現場で常に在庫情報を更新していくため、リアルタイムな在庫管理が実現します。
より具体的な運用方法は、すでに製品にバーコードがある場合と、製品にバーコードがない場合で異なります。
製品にバーコードがある場合

製品にバーコードがある場合、以下のシンプルな流れで導入できます。
- 事前準備:在庫管理システム等に品目マスタ(品番・品名・バーコードなど)を登録
- 現場運用:ハンディターミナルで製品のバーコードを読み取るだけで、品目の情報が自動で呼び出し
ハンディーターミナル等と連動するシステムに、読み取りたい内容を事前登録すれば、バーコード管理を始められます。入出庫数量を都度入力すると、システム上で最新在庫数が自動集計され、リアルタイムに在庫を管理できます。
製品にバーコードがない場合

バーコードがない場合は、バーコードを貼りつける必要があります。しかし、ラベルを1点ずつ貼る手間を割けない企業や、物理的にラベルを貼れない製品(小物、油分が多い、高温でラベルが剥がれやすい等)では、異なる運用が必要です。
バーコードの貼る場所には、以下3通りの貼り方のパターンが考えられます。
| 貼付場所 | 主な用途 | メリット | デメリット |
| 製品本体 (個品ラベル) | 完成品・部品・仕掛品など、品目1点ごと | ◯個品レベルでロット・期限までトレーサビリティ確保◯出庫後や顧客先でも読み取り可◯棚卸差異を最小化できる | △貼付作業が膨大(多品種少量は特に負荷)△ラベルコストが最も高い△貼り間違いが品質事故につながる |
| 保管棚 (ロケーションラベル) | 棚・パレットラック・床番地など | ◯一度貼れば棚替えまで再作業不要 → 最小工数◯ラベル枚数が少ないため、最も低コスト◯「棚→数量入力」方式で棚卸が高速 | △ロケーション変更やレイアウト改造時に貼り替えが発生△同じ棚に異品種を置くと誤スキャンリスク△個品/ロット単位のトレースは不可 |
| 保管容器 (外装ケースラベル) | 折りたたみコンテナ、台車、ダンボール箱 | ◯箱/コンテナ単位で一括読み取り→作業負荷中◯外装が汚れや衝撃を防ぎ、ラベル劣化しにくい◯仕掛品や工程間搬送の識別に便利 | △容器を循環・回収しないと情報が途切れる△ラベル貼替え頻度は棚より高め(都度BOX交換)△共有容器の場合、前品目のラベルが残ると誤読する恐れあり |
製品1点ずつにバーコードラベルを貼ると、個品ごとにトレーサビリティを確立できます。ラベル貼付の手間やコストを割いてでも、品質管理を重視すべき品物に向いています。
バーコードラベルを貼る手間を減らしたい場合は、保管棚・保管容器に貼るパターンも検討できます。上記メリット・デメリットを比較し、どこまで厳密な管理が必要な製品かを検討することをおすすめします。
バーコード種類早見表(JAN/ITF/GS1-128/QR など)
バーコードには100種類以上の種類があり、使い方やルールが異なります。
使用できるバーコードの種類は、使用する端末や在庫管理システムによって異なります。使用するバーコードを自社で選ぶ必要がある際は、以下の早見表を参考にしていただければと思います。
■主要バーコード一覧 早見表
| 種類 | 桁数 | 主な用途 | 補足 |
| JAN-13 | 13 | 市販製品・流通 | ・小売流通業界(スーパーやコンビニのPOSレジ等)で多く使用・世界共通 |
| ITF-14 | 14 | 外装ケース | ・段ボールなどで多く使用 |
| GS1-128 | 可変 | ロット・賞味期限・ロケーションNoなど | ・高度な生産情報の管理に最適 |
| QRコード(GS1QRなど) | 可変 | URL・テキスト・手順書連携 | 作業マニュアル表示にも活用可 |
バーコード・QRコードの違い
上記の早見表の通り、QRコードもバーコードの一種です。食品や日用品に印字されているストライプ柄のバーコードを「一次元バーコード」と呼ぶのに対し、QRコードは「二次元バーコード」と呼びます。
一次元バーコードは、水平(横)方向にのみ情報を持つのに対し、QRコード(二次元コード)は、水平・垂直双方向にデータを持つことができます。

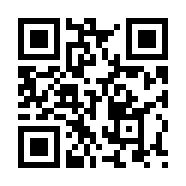
QRコード(二次元コード)のメリット
- バーコードより小さな面積で、より多くの情報を持てる
- 日本語などテキスト情報も対応可能
ロケーション管理の例を見てみます。ロケーション番号で管理する場合は、一次元・二次元どちらのバーコードも使用できます。しかし、製造ライン名の名称でバーコード管理したい場合は、テキスト情報も持てるQRコードを選択する必要があります。
どのバーコードを使うべきか判断できない場合は、在庫管理システムのベンダーに相談すると安心です。同業が多く使用しているバーコードの種類や、自社の運用におけるメリット・デメリットを提案してもらえる可能性があります。
バーコード在庫管理のデメリット

バーコードでの在庫管理のデメリットは、一定のコストが必要となることです。具体的には、ハンディ端末やラベルプリンター、システム導入費用などが必要です。特に中小企業では、この初期投資がハードルになることもあります。
バーコード管理導入のコストを抑えるコツ
以下のような工夫を活用すれば、バーコード管理を無理なくスモールスタートすることも可能です。
- トライアル導入で試す:システムのトライアルや端末レンタルサービスを利用し、1~数カ月の短期間だけレンタル→効果を測定してから本格導入
- スマホ+外付けリーダーで代替:従業員のスマートフォンを活用→端末コストを削減
- 補助金の活用:IT導入補助金や中小企業庁のデジタル化支援など、公的制度を活用
一般的に、ハンディ端末は1台あたり数万〜20万円前後の費用が必要です。初めにレンタルやリースを利用し、使用感に納得してから購入できると、リスクを抑えた導入が可能です。
ハンディ端末のレンタルは、端末のメーカーもしくは在庫管理システムのベンダー経由で申し込めます。トライアル可能な在庫管理システムを先に探し、システムとセットでお試しする方法もおすすめです。
参考:製造業向け在庫管理システム22選!機能や特徴、導入メリット、選び方をまとめて紹介
ハンディターミナル・スマホ・RFID どれを選ぶべき?
バーコード管理ができる代表的な端末は、ハンディーターミナル・スマートフォンです。さらに近年は、RFIDも比較する企業が増えてきています。それぞれメリット・デメリットがあるため、自社の状況や予算に合う端末を選びます。
■ハンディーターミナル・スマホ・RFIDの特徴比較
| 項目 | ハンディターミナル(専用バーコードスキャナ) | スマホ | RFIDリーダー |
| 参考初期費用 | 10~30万円/台 | 1万円前後 | 25万円前後/台 |
| 読み取り方式 | 接触式・1点ずつスキャン | 接触式・1点ずつスキャン | 非接触式・一括読取可能(50~300点/秒) |
| 読み取り距離 | 0~1m | 0~0.8m | 0.1~5m |
| 読み取り速度(人が作業する場合の目安速度) | 4〜10 scan/秒 (トリガー操作+製品を掴む動作が律速) | 1〜3 scan/秒 (ピント合わせ・手振れ・画面確認で減速) | 100〜300 tag/秒(実棚でアンテナ向きを変えながら) |
| 耐久性・防塵防滴 | IP65~67・耐落下1.5m | スマホ側に依存(一般的にIP54以下) | IP54~65・耐落下1.2m |
| バッテリー運用 | 10~14h | 6~10h(スマホ充電に依存) | 8~10h |
| 主なメリット | – 専用機=高速・高精度- 耐久・操作性に優れる- テンキーがあり操作しやすいと感じる人もいる- 長期保守あり | – 最も低コスト- 従業員スマホを活用可 | – 一括読取で棚卸を高速化- 汚れや暗所でも読み取り可- 非接触で衛生的 |
| 主なデメリット | – 導入コストやや高- 専用OS更新が必要 | – スマホ破損・私用利用リスク- 暗めの現場には不向き- 長時間作業で発熱・電池切れ | – 本体・タグ単価が高い- 金属・液体周りに弱い- 伝票や顧客先にタグが不要な場合が多い |
| 導入適合シーン | 生産管理全般(入出庫・工程内実績収集・部品ピッキング等) | 小規模倉庫・臨時棚卸 | 大型倉庫 |
最も低コストに導入できる端末は、スマートフォンです。しかし、ピント合わせのスピードやバッテリーの持ちにデメリットがあるため、取扱点数が少ない小規模倉庫向けです。また、暗所では読み取りが難しいため、光が届きにくいラックがある現場には不向きです。フラッシュを使用すると一定改善されますが、バッテリーの減りも早くなるため、長時間の棚卸しなどには不便かもしれません。
解決策として、スマートフォンに外付けリーダーを付けるという手もあります。しかし、より作業効率を上げるのであれば、製造現場向けに開発されているハンディーターミナルの使用もおすすめです。

ハンディーターミナルは暗めの倉庫でもスキャンが可能で、スマートフォンの3倍ほどの速度で読み取れます。耐久性もスマートフォンより高いので、現場で安心して使用できます。トライアルや長期保証などを利用できるケースもあります。
近年注目されるRFIDは、非接触型で一度に複数のバーコードを読み取ることができ、大量の在庫点数を扱う企業に向いています。例えば、パレットに山積みになった製品も、すべての箱にタグが入っていれば、一度ですべてスキャンできます。
ハンディーターミナル・スマホ・RFIDの選び方
- まずは低コストで試し、追って上位デバイスを検討 → スマホ+外付けリーダー
- リアルタイム高精度+耐久性が最優先 → ハンディターミナル
- 物量が多く一括読み取りが必須 → RFIDリーダー
ハンディターミナルの選び方
ハンディーターミナルを選ぶ際は、使いやすさや機能性を比較し、価格とのバランスを見て比較します。メーカーのサポート対応についても事前に確認しておくと安心です。
具体的な比較ポイントは、以下7点です。
ボタンの押しやすさ
ハンディターミナルには、数字入力やスキャンなどのボタンがあります。ボタンの反応や押しやすさを事前に確かめておくと、購入後に現場から「使いにくい」と言われる事態を防げます。
バーコードの読み取りスピード
ハンディターミナルの機種によっては、バーコードの読み取りスピードが遅いものがあります。少ない製品数の在庫管理の場合は問題ありませんが、数が多い場合、スピードが遅いと全体的な遅れの原因となりかねません。在庫点数が多い倉庫では、特に読み取りスピードを重視することをおすすめします。
耐久性
ハンディターミナルを手に持って作業を続けていると、どうしても落としてしまうことがあります。落下に強い機種も販売されていますので、できるだけそのような機種を選びましょう。現場によっては、防塵や防水などの機能も確認しておくと安心です。
重さ
ハンディーターミナルを長時間使うことが想定される場合は、少しでも軽い機種を選ぶと手や腕への負担が軽くなります。近年は端末の軽量化も進んでいますが、不安な方は購入前に実物を持ってみることをおすすめします。
画面サイズ
たくさんの内容を画面に表示させたい場合は、画面のサイズも重要です。特に高齢の作業者が多い現場では、小さい文字だと読みにくいと感じる人が多くなる可能性があります。なるべく大きな画面の機種を選びましょう。
バッテリーの持ち
多くのスタッフで利用する場合や、棚卸しなどで丸1日ハンディーターミナルを使う可能性がある場合は、電池交換コストも無視できません。バッテリーの持ちも試しておくことをおすすめします。
メーカー対応のスピード
何かトラブルがあった際、メーカーがスムーズに対応できるかどうかも最も重要なポイントです。
「代替え機はすぐに貸してくれるのか?」「トラブル時にしっかり対応してくれるのか?」など、メーカーの対応を確認しておくようにしましょう。
バーコード在庫管理の導入事例

当社でバーコードによる在庫管理を導入された事例をご紹介します。
紙・エクセルの棚卸しをバーコード管理に置き換え、半期で1000時間規模の工数削減
ポンプ製造企業様では、エクセルによる在庫管理を行っていたものの、理論在庫と実際在庫の差異に課題がありました。このため日々の発注に影響が出ていたほか、棚卸しの手間も増えていました。また、棚卸し自体も、紙の棚卸表に記載した内容をエクセルへ転記するという負担が大きい手順でした。
そこで、在庫管理システムとハンディーターミナルを導入し、日々の入出庫管理をバーコード管理により精緻化。リアルタイムに在庫情報を更新できるようになったことで、棚卸差異が大幅削減しました。棚卸し作業も、数量を確認→差異があればハンディーターミナルからシステム上のデータを直接更新するのみに。紙からエクセルの転記などの作業は、不要となりました。
この結果、棚卸しの工数は半年で1000時間規模で削減できました。
詳しい事例はこちら:半年の棚卸工数を1000時間規模で削減!精緻な在庫管理で発注ミス防止やロットトレースも強化
22種類の生産管理システムをランキングで比較
初期費用相場や選び方のポイントをチェック
生産管理システムをそれぞれの特徴や初期費用相場などで比較したい場合は、「生産管理システムランキング」も是非ご覧ください。生産管理システムは、自社の製品・生産方式・企業規模などに適したものを導入しないと、得られるメリットが限定されてしまいます。事前適合性チェックや生産管理システムを選ぶ前に押さえておきたいポイントも解説していますので、製品選びの参考にしてみてください。






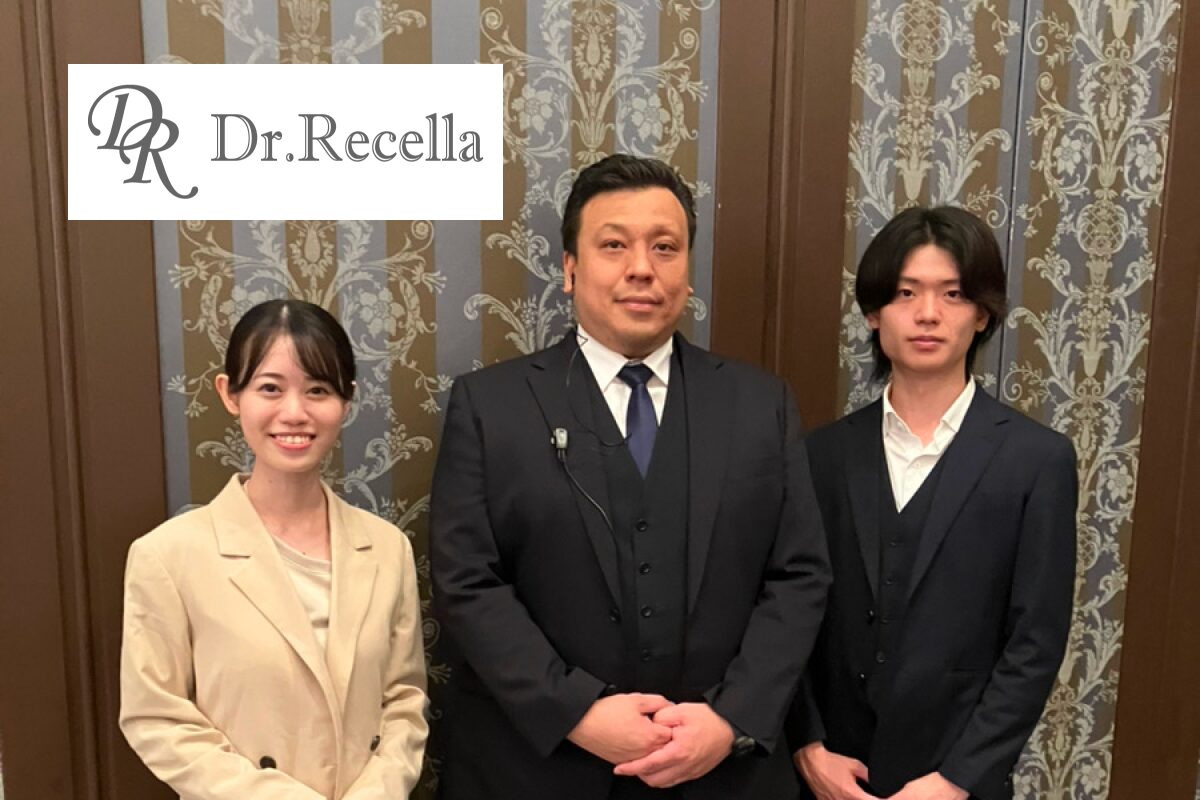

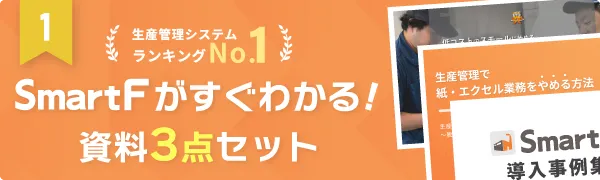

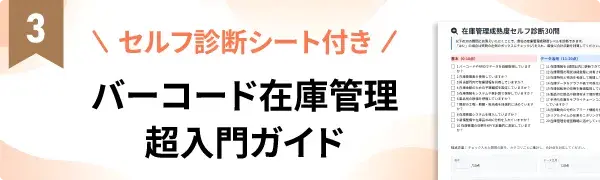









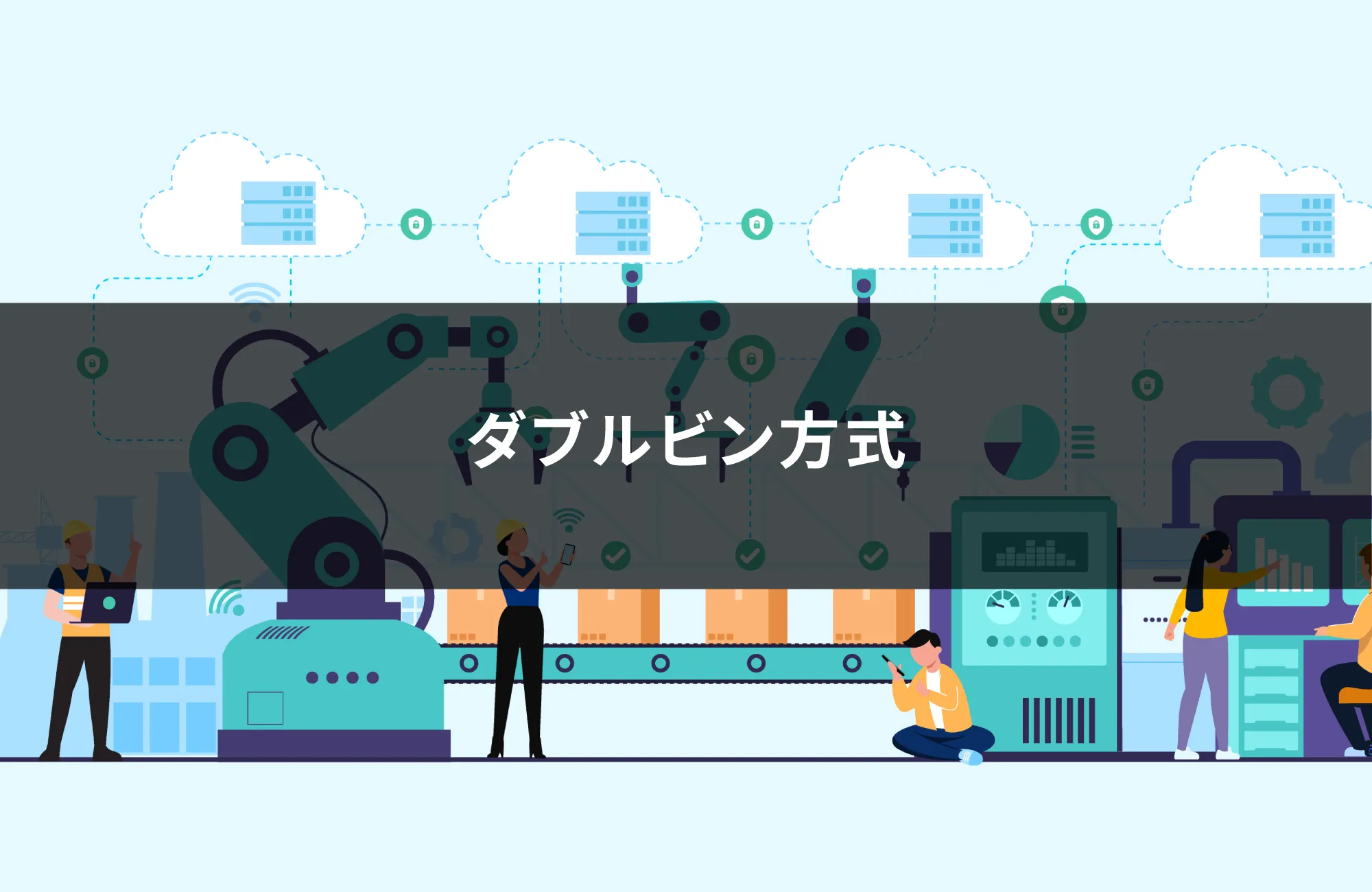




.jpg)











