製造業における工数管理とは?算出方法からエクセル管理の限界、システム活用まで徹底解説
公開日:2020年04月30日
最終更新日:2025年05月01日

製造業において「工数」は、作業にかかった人の時間を数値化したもので、生産性やコストを把握するための重要な指標です。手間をかけずに精度の高い工数管理ができれば、生産計画の精度向上、人員配置の最適化、精緻な原価管理が実現可能となります。
本記事では、工数の基本概念から算出・集計方法について具体的な事例を交えて紹介し、エクセル管理の限界と専用ツール導入を検討すべきタイミングについても解説しました。
工数とは?
工数とは「作業にかかった人の時間を数値化したもの」を指します。人件費や生産効率の管理に欠かせない指標で、コスト管理、生産管理の中で頻出する基本的な考え方です。
作業に必要な延べ時間(作業人員×時間数)
工数とは、実際の作業に関わった人数と、それぞれの作業時間を掛け合わせたもので、延べ時間とも呼ばれます。たとえば、1つの工程に2人が3時間ずつ作業すれば、その工数は「6時間(2×3)」です。このように、「人の時間を積み上げた量」=工数と理解することで、作業の大きさ・負荷が定量的に把握できるようになります。
工数には次のような単位があり、それぞれ以下のような状況で多く用いられます。
- 人時(1人が1時間働いた時間):製造現場の工程改善や日常管理
- 人日(1人が1日働いた時間):顧客に提示する見積もり・工数計画
- 人月(1人が1か月働いた時間):プロジェクト・工場全体の稼働状況・予算管理
作業人員や労務費を見積もるための指標
工数は、人員計画や人件費の見積もりの根拠となる指標として使われます。
たとえば、受注量が増えた際に、作業人員を何人増やすべきか、増員によってどれくらいコストが増えるかを正確に見積もる必要があります。さらに、販売利益を確保するためには、原価構成比率の高い労務費を正しく把握し、製品ごとの原価構成を明確にすることが不可欠です。
工数が活用される具体例:新規受注による増員影響の試算
ここでは、大型の新規受注を受けたケースを想定し、具体的な影響を試算してみました。
- 追加要員:作業員2名
- 1人あたり労務費負担:50万円/月
- 追加労務費合計:100万円/月
また、増員では、経験の浅い作業員が加わるため、製品1個当たりの作業時間が増え、労務費原価の上昇も見込まれます。この増員による工数・生産量・労務費原価の変化は次の通りです。
| 増員前 | 増員後 | |
| 工数(作業員数) | 6人月 | 8人月 |
| 労務費合計 | 300万円 | 400万円 |
| 月間生産量 | 150個 | 180個 |
| 製品1個当たり労務費 | 2.0万円 | 2.2万円 |
この試算結果からは、製品1個あたりの労務費は0.2万円増加する見込みです。そのため、従来品と比較して、新規受注品の販売価格も0.2万円以上引き上げる必要があることが読み取れます。
このように、作業員増員の際には、労務費原価への影響度を考える必要もあります。工数と生産量をもとに1個あたり原価の変動を可視化できれば、適正な価格設定ができます。さらに、人員計画と資金計画を連動させる上でも、工数は重要な管理指標であると言えます。
製造業で工数管理を行う4つのメリット

製造業において、客観的データをもとに工数管理を行うことには大きなメリットがあります。作業工数は製品納期に直結するだけでなく、経営上の重要な意思決定や製造原価管理にも大きく影響するためです。
適正なスケジュール・納期を設定できる
各作業にかかる時間を「工数」として定量的に把握できれば、無理のない生産計画や納期設定が可能になります。もし必要工数が不明確なままスケジュールを立ててしまうと、無自覚に無理な納期設定をしてしまいます。その結果、納期遅延や品質低下のリスクを高めてしまうことにもつながります。
たとえば、製品Xの組立作業には、1個当たり合計20人時かかることが、工数管理によって把握できているとします。この場合、1日あたり4人が対応できるなら、20人時 ÷(4人/日)= 5日間と逆算でき、現実的な生産計画が立てられます。
さらに、詳細な日程計画に必要工数を盛り込んだ工程スケジュール表を作成すれば、より精度の高い工数管理が可能です。一例ですが、以下の4点を前提として、余剰人員が出ないようなスケジュールに落とし込んだものが次の製造工程表です。
- 作業員:3人
- 受注数、1製品当たりの工数単価(人日)から総工数を計算
- 原材料入荷日の翌日から生産開始
- 製品完成後の予備日も考慮し確実な出荷予定日を設定
このように、工数管理ができていれば、ムリ・ムダ・ムラのない生産計画が実現可能です。
作業負荷を見える化できる
工数管理を徹底すれば、作業者ごとの負荷を可視化できます。これにより業務の偏りを早期に発見し、人員配置や業務分担の見直しが可能となります。
製造業において、かつてはベテランの勘や経験を頼りに、現場を管理するケースが多く見られました。しかし、現在は多品種少量生産が主流となり、日々の受注変動や生産計画の変更に対して柔軟に対応することが求められています。
このため、「人がどこで・どれだけ時間を使っているか」を正しく把握し、現状を数値で見える化する工数管理の重要性が一層高まっています。
工程管理の一つとして、各担当者の稼働時間・稼働率の管理が挙げられます。例えば「Aさんは毎日10人時分の作業をしているが、Bさんは6人時分しか作業していない」という状況が判明したとします。この場合、人員配置の見直しなどにより、Aさんの過重労働解消、Bさんの余剰リソース活用を検討できるようになります。
生産管理システムの中には、担当者別の稼働時間・稼働率をリアルタイムで把握できる機能を備えたものもあります。
→マスタ設定とデータ整備をご提案できる生産管理システムはこちら
設備投資の意思決定に役立つ
工数管理は、設備投資の意思決定にも役立ちます。作業工数を分析すれば、どの工程がボトルネックであるかを明確にし、自動化設備導入による工数削減効果を定量的に比較・試算できるようになります。
たとえば、組立工程において、作業の長時間化が常態化し、月間生産量のボトルネックとなっていたとします。この際、工数管理データが蓄積されていれば、自動化設備の導入コストと削減効果を比較し、客観的判断が可能となります。このような判断に使用する場合、以下のような切り口で工数データを整理するとよいでしょう。
- 設備導入前後の現状の作業工数(人時)
- 削減できる労務費(月単位・年単位)
- 設備導入コストの回収期間
製造原価の精度を高める
製造原価の精度を高める上でも、工数管理は効果的です。製品原価の中で、工数は原材料費に次いで構成比率の高い労務費に直結します。したがって、工数の記録が曖昧であれば、製造原価も正しく算出できません。
工数を正確に記録・集計できれば、精緻な製品原価を把握し、利益を見える化することができます。もし、想定よりも利益が少ない場合には、収益性を高めるために改善すべきポイントを考え、具体的なアクションにつなげられます。
さらに、他社で対応が難しい特注品に対して、より適切な販売価格を設定することも可能となります。値付けの根拠となるデータが不十分なまま見積もりを提示し、実は赤字だったという事態も防ぐことができます。
製造現場で工数を算出する方法

現場での工数算出は、工程などの作業単位ごとに作業時間を記録したり、作業者単位で稼働時間を集計する方法が一般的です。注意点も含め、具体的な方法を紹介します。
作業単位をあらかじめ決めておく
工数を正確に記録・集計するためには、どこまでを一つの作業とみなすかを事前に決めておくことが大切です。もしこれが決まっていない場合、次のような問題が生じます。
- 記録する人ごとに記録の切れ目が統一されていない
- 集計時に再分類が必要となる
工数データの信頼性を担保するためにも、事前に作業単位を明確にし、記録フォーマットを作成しておくと良いでしょう。
工程・作業単位ごとの作業時間を記録・集計する
あらかじめ決めた作業単位毎に、それぞれにかかった人数、時間を記録します。これを積み重ねることで、製品1つあたりの累積工数を把握できます。様々な要因で作業時間にばらつきが生じるため、作業日報に組み込んで一定期間記録を取るとよいでしょう。
工数管理に馴染みのない現場では、自由に書いたり、すぐに修正できる紙の作業記録表に各ことから始めるとよいでしょう。記録表のデータをエクセルで集計すれば、自社に合った形での工数の見える化ができます。
一例ですが、ある金属製の組立部品の作業時間を記録し、工数として算出してみました。製造工程は次の4つの工程です。
①材料カット工程:所定寸法にカット・バリ取りする
②穴あけ工程:ボルト止め用の穴を開ける
③組立工程:カットした材料を組み合わせてボルトを締める
④研磨工程::表面を研磨して仕上げる
⑤検品:製品の品質検査(外観・寸法)を行う
⑥梱包・出荷:製品をパレット上で梱包し、出荷する
各製造工程について、製品1個あたりの作業者数、1人あたり作業時間、工数をまとめると、次の表の通りとなります。
| 作業者数 | 1人当たり作業時間 | 工数 | |
| ①材料カット | 1人 | 3時間 | 3.0人時 |
| ②穴あけ | 1人 | 1時間 | 1.0人時 |
| ③組立 | 3人 | 0.5時間 | 1.5人時 |
| ④研磨 | 1人 | 2時間 | 2人時 |
| ⑤検品 | 1人 | 0.5時間 | 0.5人時 |
| ⑥梱包・出荷 | 1人 | 2時間 | 2.0人時 |
| 合 計 | 10.0人時 | ||
上の表より、この組立部品の製造工数は製品1個あたり10.0人時と計算できます。作業員の時間単価を単価3,000円とすると、製品1個あたりの人件費は、以下の通りとなります。
10.0[人時] × 3,000[円/人時]=30,000円
作業者・チーム単位で稼働時間を把握する
製造現場における工数管理では、作業者単位・チーム単位での稼働時間を把握することも有効です。誰がどれくらい時間を使っているのかを細かく記録・分析することで、より精度の高い工数管理が可能です。
特に、作業者・チーム単位での工数管理が望ましいのは、次のようなケースです。
- 作業者ごとに熟練度の差が大きい場合:作業者ごとに作業効率・品質が異なるため
- 同じ作業者が複数工程を担当する場合:工程別の工数算出が難しいため
- チーム作業で生産性を向上させたい場合:個人ごとの作業負担を可視化しにくいため
一例として、ある組立製品の作業について、作業者単位で工数を集計した結果を次の表に示します。
| 作業員 | 担当工程 | 稼働時間 |
| 鈴木一郎 | 材料カット、組立 | 3.5時間 |
| 佐藤英雄 | 穴あけ、組立、研磨 | 3.5時間 |
| 田中三琅 | 検品、梱包・出荷、組立 | 3.0時間 |
| 合計 | 10.0時間 | |
このように、一人で複数工程を担当している場合でも、個別に稼働時間を集計することで、製品単位の工数把握が可能です。
工数算出時によくある課題:段取り・中断時間の集計漏れ
工数を正確に算出するためには、単に作業時間を記録するだけでは不十分です。特に製造現場では、以下のような集計ミスにより、工数管理の精度が大きく下がってしまうケースもあります。
- 付帯業務のカウント漏れ:移動・運搬や、準備・段取り替え時間の見落とし
- 除外すべき時間の漏れ:休憩時間や、他作業のための中断時間の除外忘れ
- 記録精度の悪化:後でまとめて記入することで、記録ミスや主観的な記録が発生
特に紙媒体による記録表やエクセル管理など、手作業で工数集計する際には、上記の集計漏れのリスクが残ってしまいます。工数管理の導入段階では、十分な注意である程度カバーはできるでしょう。しかし、実運用段階へ移行する際には、現場ごとに適したルールを整備する必要があります。
エクセル管理で工数を把握しきれない場面とは
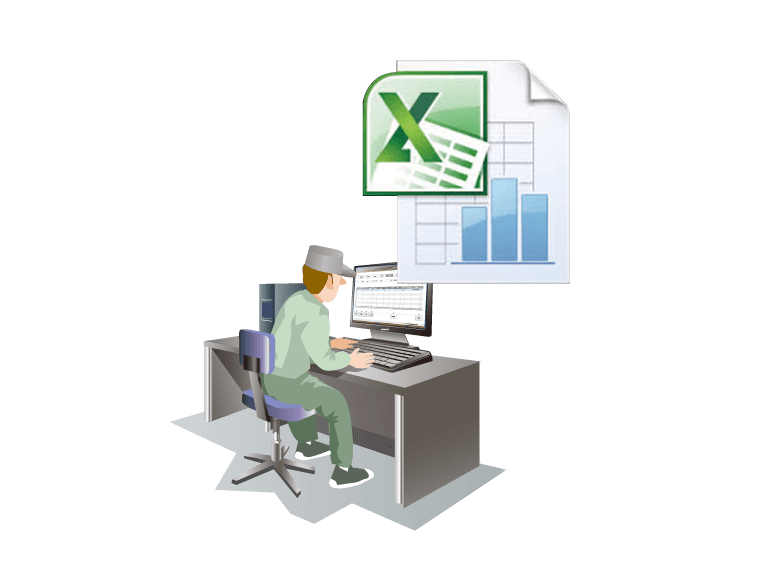
エクセルによる工数管理は、手軽に始められるというメリットがある反面、限界もあります。現場の多品種少量化の加速、人員や事業規模の増加に伴ってオペレーション複雑化が進むと、エクセルでは管理しきれなくなってきます。
特に以下のような課題を抱えていると、エクセルのみで高精度の工数管理は難しいでしょう。
属人管理となっていて、正確な工数が集計できない
エクセル管理では、特定の担当者の独自ルールで工数集計を行うケースが多く、属人化が発生しがちです。これにより、以下のような問題が生じます。
- 入力内容を個人の記憶や判断に任せる部分が多く、ばらつきが出る
- 入力フォーマットや単位が現場ごとに統一されていない
- 担当者が独自に工夫を加えた結果、バージョン管理が煩雑になる
このような状況では、正確な工数データを継続的に管理・蓄積することは困難です。現場の実態と管理データにズレが生じ、現場改善や正しい経営判断を妨げる可能性もあります。
入力ミス・漏れが多く、工数集計の精度が低い
エクセル管理は集計の自由度が高い反面、人の手による入力が前提のため、ミスや漏れが発生しやすいという欠点があります。こうした不正確なデータが積み重なると、全体を集計して得られた工数データの信頼性が大きく下がってしまいます。
また、エクセルへの手入力そのものが面倒、と感じる作業者も少なくありません。このため、特に繁忙期には、後回し記録やまとめて記入が常態化しているケースもあります。こうした現場では、記録漏れ、転記ミス、入力忘れがさらに増え、実態を正確に反映できていない可能性が高いでしょう。
このような問題を放置すると、生産管理・コスト管理の精度が悪化し、通常の生産オペレーションにも支障が出てしまうこともあります。
工数管理ツールの導入を検討すべき状況

エクセル管理に限界を感じ始めたら、専用ツールへの移行を検討するタイミングです。
特に、次のような状況に心当たりがあれば、早めの対応が効果的です。
手作業・属人化から脱却したいと感じたら
属人的な手作業を辞めたくなったときは、専用ツール導入を考えるサインです。
エクセルによる工数管理は、運用初期にはフレキシブルに対応できます。しかし、運用が定着するにつれ、以下のような課題が表面化するケースも少なくありません。
- 手入力での管理に時間がかかる
- 更新ミス・集計ミスが頻発する
- 特定担当者しかデータを把握していない
このような属人化の問題が進行すると、正確な工数データを長期的に維持することが難しくなります。
そこで効果的なのが、標準化されたシステムによる一元管理です。工数管理に特化したシステムだけでなく、工数管理機能の付いた生産管理システムも使いやすいでしょう。生産管理システムなら、生産実績や設備稼働データも同じシステム内で管理できるため、工数管理全般の手作業を大きく減らせます。
工程改善・経営指標に工数を導入するとき
工数データを現場改善や経営指標(KPI)に本格採用したいときも、専用ツール導入を検討したいタイミングです。複雑なオペレーションの中で工数管理が求められるケースも多く、エクセルで適切に管理するのは至難の業とも言えます。
特に、以下のような取り組みを進める際には、工数管理ツールは強力な武器となるでしょう。
さらに、工数管理機能のある生産管理システムであれば、工程別・作業者別・製品別など多角的な集計が可能となり、改善活動が加速します。
データ活用のための情報連携を加速するタイミング
製造部門だけでなく、他部門と連携した改善を加速する際にも、工数管理ツールの導入は効果的です。次のような目的がある場合には、クラウド型のシステムツールが便利です。
- 製造現場と管理部門でリアルタイムに情報共有したい
- 工数データと生産計画・原価管理データを連携したい
- 専用ダッシュボードに自動集計したデータを反映したい
特に管理・間接部門との情報共有では、生産性改善以外の切り口で工数データを集計するケースもあります。具体的には以下のような状況です。
- 製品別・受注案件別に、労務費構成比を比較する
- 顧客別・製品別に、受注単価と工数負荷のバランスを分析する
- 工数ひっ迫による外注化による製造リードタイム短縮効果を試算する
工数情報を生産管理システムで一元管理すれば、受注戦略・人員計画・リードタイム改善など、部門を跨ぐ横断的な改善が加速します。
このように、工数データのリアルタイム集計と情報連携は、企業全体の業務効率を大幅に向上させます。
生産管理システムで実現できる精緻な工数管理とは:メリットとともに紹介

工数管理には、生産管理システムの活用が効果的です。工数管理専用ツールとは異なり、生産管理情報とも紐づけられるため、工数の入力・集計・活用すべての精度が向上します。ここでは、生産管理システムを活用した工数管理で得られるメリットを2つ紹介します。
ハンディ端末・タブレットで、工数入力を自動化
ハンディ端末から現場で直接作業実績を入力することで、工数管理の精度は大きく向上します。特に、生産管理システムを活用すれば、作業者が実績登録した内容をもとに、作業単位の工数が自動集計されます。
これにより、従来のエクセル管理や手書き記録にありがちな、記憶頼りの曖昧な記録や後追い入力によるミスを防止できます。また、システムによる自動集計化により、手作業によるエクセル集計に必要となる膨大な労力も削減されます。正確な工数データが蓄積できるため、製品別原価の算出やスピーディーな粗利分析にも活用可能です。
バーコードスキャンも併用した作業実績登録を行えば、入力ミスも防ぐことができ、簡単かつ確実に工数記録データの蓄積が可能となります。これにより、現場運用の効率化、経営判断に用いるデータの高精度化を同時に実現します。
詳しい事例はこちらで紹介しています。
→【工程管理システム】ハンディ端末を用いた作業記録でエクセル管理の工数削減を実現
担当者ごとの稼働時間に合わせた生産計画の実現
工数データを活用することで、実際の稼働実績に基づいた最適な生産計画が立てられ、現場の生産性が大きく向上します。
従来の生産計画では、作業者を「一律の能力」として仮定し、作業配分を決めるケースが一般的でした。しかし、実際には、担当者ごとに習熟度が異なり、同じ担当者でも作業ごとにスピードや得意分野には差があるものです。個人別の稼働状況を考慮しない計画では、ムリ・ムダ・ムラが発生しやすくなります。
生産管理システムの工数管理機能を使えば、担当者別の稼働時間・作業負荷を正確に把握することができます。これにより、個々の能力や稼働状況に合わせ、現実的な生産計画が立てられます。
たとえば、作業スピードが速い担当者には難易度の高い工程を優先的に割り振り、負荷が集中しすぎている担当者には作業量を適切に調整します。こうした取り組みにより、現在の人員体制であっても、現場全体の生産効率を向上させることが可能です。
22種類の生産管理システムをランキングで比較
初期費用相場や選び方のポイントをチェック
生産管理システムをそれぞれの特徴や初期費用相場などで比較したい場合は、「生産管理システムランキング」も是非ご覧ください。生産管理システムは、自社の製品・生産方式・企業規模などに適したものを導入しないと、得られるメリットが限定されてしまいます。事前適合性チェックや生産管理システムを選ぶ前に押さえておきたいポイントも解説していますので、製品選びの参考にしてみてください。



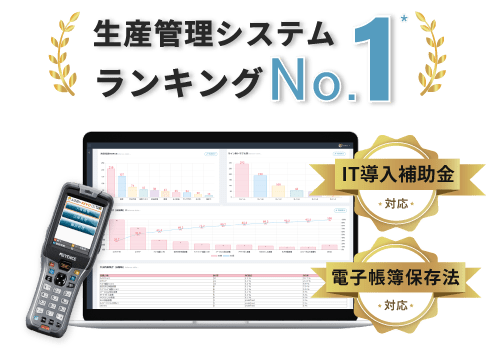





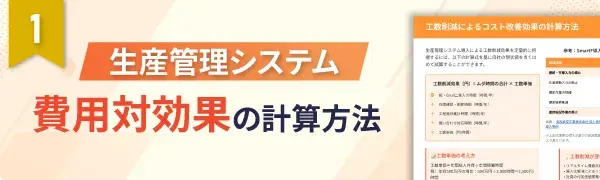
















.jpg)












