製造業の原価管理の基本 利益率向上のために知っておくべき重要性とシステム活用方法
公開日:2025年02月16日
最終更新日:2025年02月17日

製造業における原価管理は、利益率の向上やリスク対策、適切な価格設定のために必要な業務です。特に、原材料の価格変動が大きい近年においては、原価管理の重要性が増しています。
しかし、原価の把握にはこまやかな管理が必要で、正確な原価管理ができている企業は少ないのが現状です。本記事では、原価管理の基本概念や「原価計算」「予算管理」との違いを解説し、具体的な標準原価の設定方法や差異分析、改善への取り組みを紹介します。また、多くの企業が抱える紙・エクセル管理の工数などの課題や、生産管理システムによる改善方法や導入事例も取り上げています。
原価管理とは何か

原価管理とは、製品やサービスを生産・提供する際にかかるコストを詳細に把握し、それを管理・最適化する活動を指します。企業の利益を最大化し、経営の安定化を図る上で重要な役割を果たします。
原価とは
原価とは、製品やサービスの提供に必要な費用を指します。さらに原価は、以下2種類があります。
- 製造原価:製造にかかったコスト
- 売上原価:特定期間に売り上げた商品の仕入れや製造にかかったコスト
売上原価は、主に小売業で用いられます。製造業の場合、売上原価のなかに製造原価が含まれるような関係となりますが、製品の利益率などの計算には製造原価を用いるケースが多いです。
製造原価の3つの分類方法

製造原価には、以下3つの分類方法があります。
- 形態別:材料費・労務費・経費
- 製品との関連別:直接費・間接費
- 変動の有無別:固定費・変動費
製造業で製造原価を求める際は、形態別の「材料費・労務費・経費」を合算します。これらの費目の具体的な内容は、以下の通りです。
- 材料費:製造に直接使用されるコスト(原材料、資材、消耗品など)
- 労務費:作業者の賃金(賞与や福利厚生費なども含む)
- 経費:上記2つに分類されない費用(設備の減価償却費、水道光熱費など)
また、上記3つの分類は、さらに直接費・間接費に分けることができます。
製造直接費
- 直接材料費:製品の一部を構成する原材料(主資材)
- 直接労務費:製造に直接関わった作業者の賃金
- 直接経費:上記2つに分類されず、製造に直接関わった費用(外注加工費など)
製造間接費
- 間接材料費:製造に用いたが使用量が計測できない費用(潤滑油、溶接用ガス、消耗工具など)
- 間接労務費:製造に間接的に関わった従業員の賃金(品質管理担当など)
- 間接経費:上記いずれにも分類されず、製造に間接的に用いた費用(設備の減価償却費、水道光熱費など)
これらの要素を把握することで、製品ごとのコスト構造を明確化できます。
似た用語との比較
原価管理と似ており、混同されやすい言葉に「原価計算」や「予算管理」などがあります。
「原価計算」との違い
原価管理と原価計算は密接に関連していますが、目的が異なります。原価計算は、製品ごとの原価を計算するための手法で、過去のデータを基に計算されます。一方、原価管理は、計算された原価を基に、コスト削減や改善策の立案・実行を行うプロセスを指します。すなわち、原価計算は原価管理の一部であり、計算結果を活用して管理活動を進めることが原価管理の本質です。
「予算管理」との違い
「予算管理」は、企業全体や部門ごとの年間予算を設定し、それに基づいて収支を管理するプロセスです。一方、原価管理は、製品やサービス単位のコストに焦点を当てています。原価管理と予算管理は補完的な関係にあり、原価管理で得られたデータは、予算の精度向上や計画的な経営判断に役立ちます。
原価管理が重要な理由
原価管理を徹底することは、製造業の経営の根幹を支える重要な要素です。原価を詳細に把握・管理することで、財務や経営においてさまざまなメリットを得ることができます。
財務諸表の作成に必要
原価管理は、正確な財務諸表の作成に直結します。特に製造業では、製品ごとの原価を適切に計算することで、損益計算書や貸借対照表における在庫評価の精度を高めることが可能です。これにより、税務申告や投資家への情報開示において信頼性を確保できます。
利益率の改善・向上につながる
原価を詳細に把握することで、製造コストの構造を見直し、無駄を排除できます。例えば、製造工程の効率化や材料費の見直しを通じて、利益率を向上させることが可能です。さらに、継続的な原価管理を行うことで、長期的な利益体質の強化が図れます。
原価変動のリスクに備えられる
原材料の価格変動や労務費の上昇といったリスクに対して、原価管理を徹底することで早期に対応策を講じることができます。例えば、価格交渉や代替材料の選定など、コストの安定化に向けた施策を実施する上で、原価データが重要な基盤となります。
製品価格の決定に役立つ
製品価格を適切に設定するためには、正確な原価情報が欠かせません。原価を基にした価格設定を行うことで、適切な利益率を確保しつつ、市場競争力のある価格の検討が可能になります。
原価管理の具体的な方法

次に、原価管理を効果的に実施するための具体的な手法について解説します。
標準原価を設定
標準原価とは、理想的な条件下で製品を製造する際に発生すると想定される原価を指します。この標準値を設定することで、実績原価との比較が可能となり、コスト削減の余地を明確化できます。標準原価を適切に設定するためには、過去のデータや市場動向を考慮した詳細な分析が必要です。
原価計算
原価計算は、実際に発生した原価を正確に計算するプロセスです。これには、直接費用の集計だけでなく、間接費用を各製品に配賦する手法も含まれます。製造業では、製品ごとの原価を詳細に把握するため、作業別や部門別に分けて計算することが一般的です。
差異分析
差異分析とは、標準原価と実際原価の差異を分析し、その原因を特定するプロセスです。例えば、原材料費が標準より高かった場合、その原因を調査し、適切な改善策を講じることが重要です。このプロセスを繰り返すことで、原価管理の精度を高められます。
改善
原価管理の最終的な目的は、コスト削減や業務効率化を通じた改善にあります。差異分析の結果を基に、製造工程の改善や仕入れ先の見直しなど、具体的なアクションを起こすことが求められます。これにより、継続的なコスト削減と利益率の向上が可能となります。
製造業での原価管理でよくある課題
製造業での原価管理において、特に多くの企業が直面する問題について詳しく解説します。
専門知識が必要
原価管理には専門的な知識が必要とされます。特に、間接費用の配賦や差異分析には計算能力や経営知識が求められます。そのため、経験の浅い担当者では適切な原価管理が難しい場合があります。
実績が正確に集計できていない
正確な原価データの収集は、原価管理の基盤です。しかし、多くの企業では、実績データの収集が不十分であるため、正確な原価計算が困難です。この課題を解決するには、データ収集の仕組みを整備する必要があります。
紙やエクセルでの管理で工数が膨大
紙やエクセルを使った原価管理には、多大な工数がかかります。特にデータ量が多い場合、人為的なミスが発生しやすく、作業の効率性が低下します。しかし、製造業では、紙やエクセルでの原価管理を行っている中小・中堅企業が今も多くあります。
効率的な原価管理にはシステムが必要

効率的な原価管理を実現するためには、システム化が不可欠です。製造業では、原価管理機能付きの生産管理システムを導入することで、製造原価の一元管理が可能になります。
生産管理システムでの原価管理は、特に材料費と労務費のリアルタイムな管理に役立ちます。
- 材料費:在庫・発注管理で仕入単価をデータ管理
- 労務費:デジタル作業日報で各工程の工数を作業者ごとに集計
例えば、発注数量によって単価が異なる材料や、分散購買で発注先が複数ある材料も、生産管理システムで管理できます。労務費についても、作業者ごとに作業開始・終了を登録するだけで、工数集計を自動化できる生産管理システムがあります。
これらの原価データ管理は、紙・エクセルで行うには複雑で、集計に多大な工数がかかります。生産管理システムで、日頃の発注や進捗管理を通して原価データを収集しておけば、必要なデータを簡単に抽出し、分析に活用できます。
このように、生産管理システムを活用すると、原価管理に必要な実績データ収集や差異分析が自動化され、作業効率が大幅に向上します。また、リアルタイムで原価を把握できるため、迅速な経営判断が可能です。
生産管理システムで原価管理を実現した事例
ある企業では、生産管理システムでの原価管理を実現し、正確な製造原価の把握や粗利分析が可能になりました。さらに、通常の製造分と商品開発のための研究開発費が明瞭にわかるようになったことで、商品開発のスピード向上というメリットも得られました。
その企業では、在庫管理は月次棚卸のみでリアルタイムに行えておらず、工数集計も行えていませんでした。そこで、生産管理システムによるリアルタイム在庫管理と工数集計を導入し、原価管理のシステム化に成功しています。
詳しい事例はこちら:製品別原価管理・粗利分析が可能に!商品開発の予算化による開発スピード向上もできる体制に
原価管理をシステム化すべきかお悩みなら
原価管理をすべきとはわかりつつ、システム導入まですべきか悩まれている企業は多くいらっしゃいます。
そんな担当者向けに、「原価管理システムは必要?現状見える化ガイド」を無料配布しております。
自社の原価管理の成熟度を診断できるセルフ診断シートも付属していますので、自社の現状分析にもお役立ていただけます。





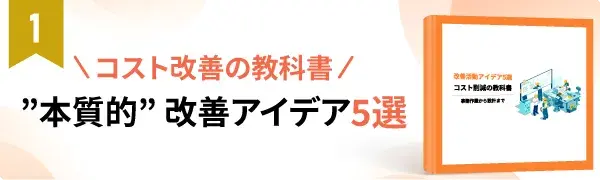

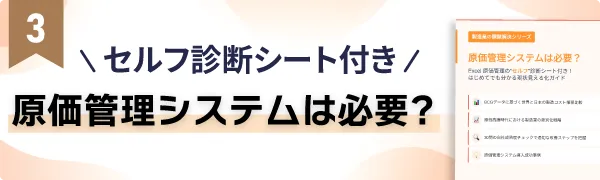


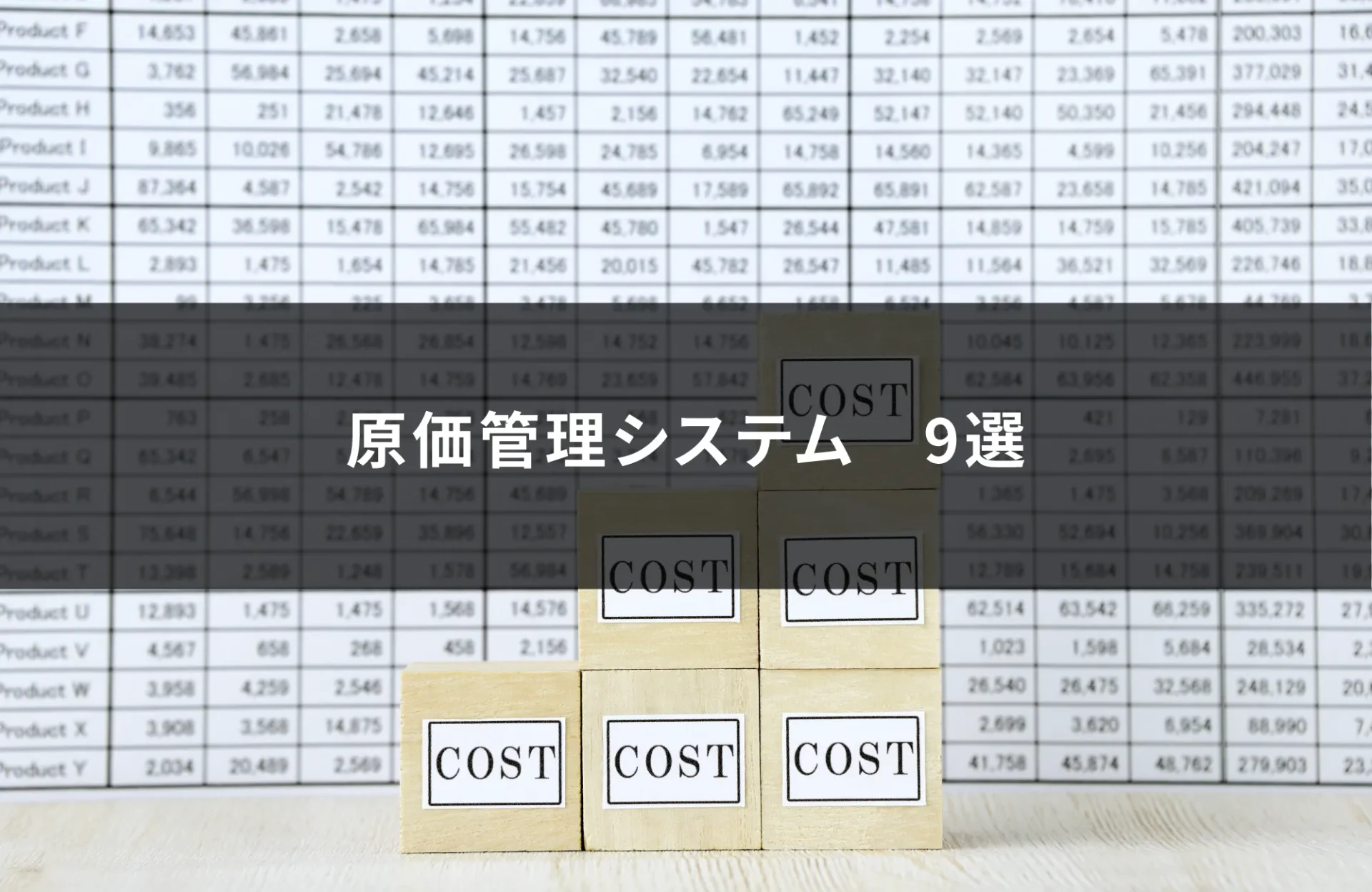




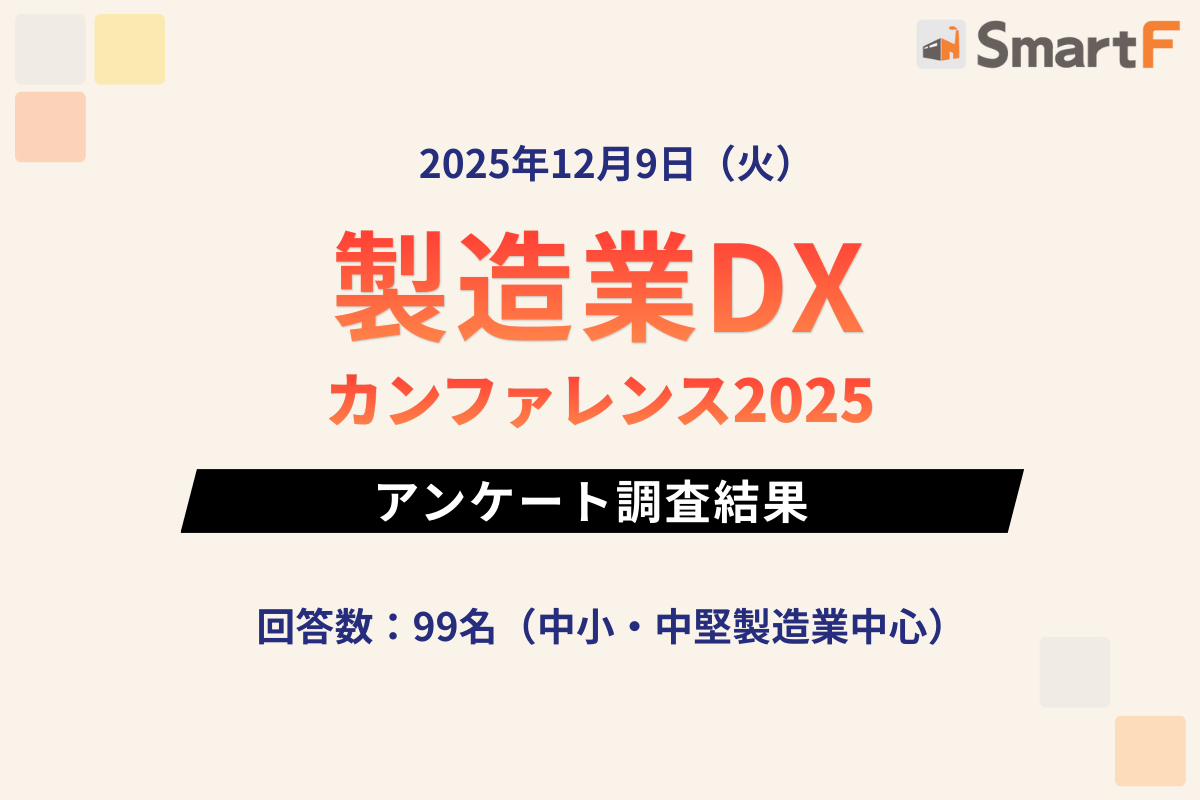




.jpg)






