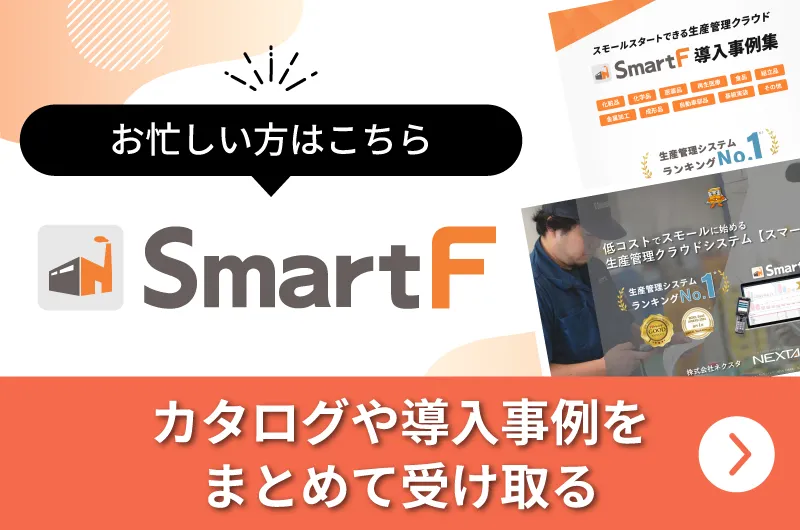中小企業・小規模製造業者向け|生産管理システムの条件と選び方 失敗しないための導入方法
公開日:2020年03月03日
最終更新日:2025年12月16日
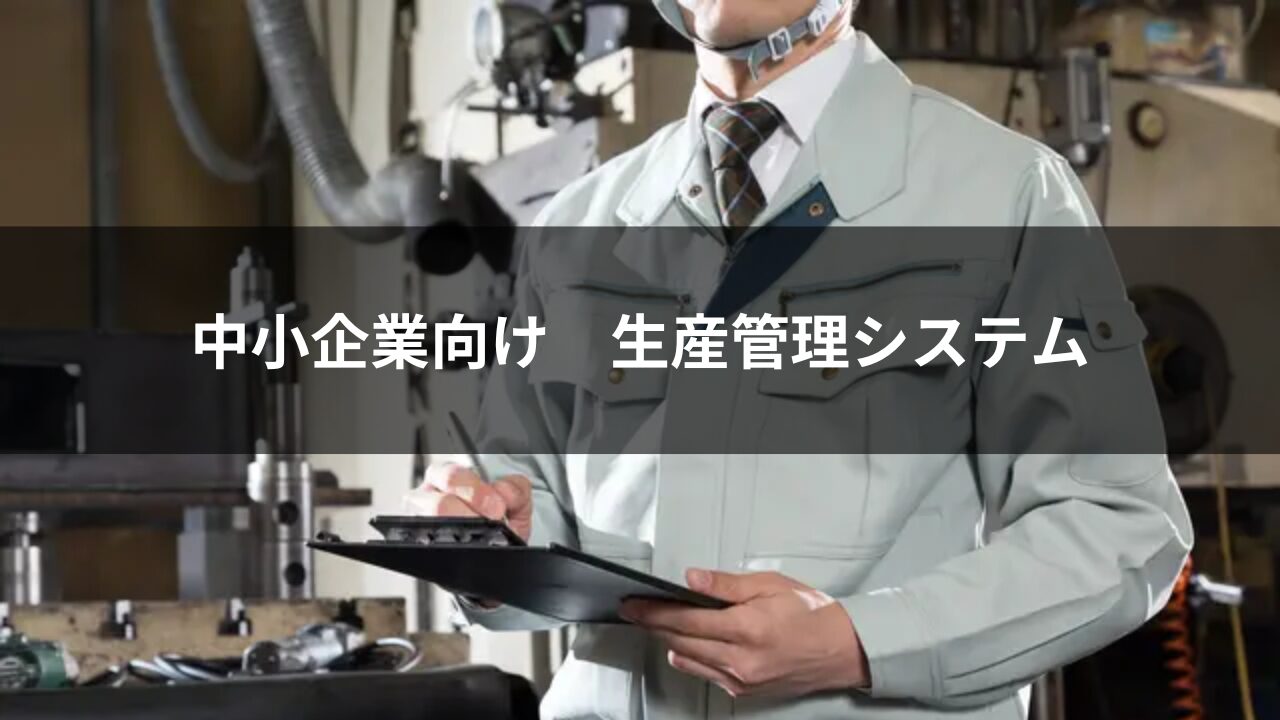
生産管理システムには、非常に多くの種類があります。そのため、中小企業や小規模製造業者では、どれを導入すればいいのかわかりづらいかと思います。
「実際にどんなパッケージシステムを選べばいいのか?」
「何に気をつけて選べばいいのか?」
本記事では、具体的に上記2点について理解できるよう、小規模または中規模製造業者が生産管理システム導入に失敗しないための知識を詳しく解説します。
中小企業・小規模製造業向けの生産管理システムとは

中小企業向けの生産管理システム、もしくは中小企業が導入に成功しやすい生産管理システムの特徴は、以下3点です。
- 低価格かつ必要な機能が揃っている
- 必要な機能のみの導入に対応
- 導入サポートが充実
大手企業に比べて、製造業DXに割ける予算が少ない中小企業にとって、生産管理システムが低価格であることは重要です。特に、必要な機能に絞って利用できる生産管理システムは、予算を抑えた導入がしやすいといえます。さらに、導入サポートが充実していると、IT専任担当者がいない企業でも、ベンダーの手厚いサポートを受けながら導入を進められるため、システムが現場に定着しやすいメリットがあります。
クラウド型・オンプレミス型 どちらにすべきか
生産管理システムの導入形態には、大きく分けてクラウド型とオンプレミス型があります。結論からいうと、中小企業・小規模製造業には、クラウド型が向いているケースが多いと言えます。「低コストでシステムを始めたい」「社内にIT専任担当がいない」といった、多くの中小企業の状況・ニーズに合うからです。
| 項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 安価な傾向(数十万円~) | 高額な傾向(数百・数千万円~) |
| 導入期間 | 短期間 | 長期間 |
| カスタマイズ性 | 低い場合が多い | 高い |
| 運用・保守 | ベンダーが担当 | 自社で担当(専門知識が必要) |
| アクセス | インターネット環境があればどこでも | 社内ネットワーク内 |
| データ管理 | ベンダーのサーバー | 自社のサーバー |
| セキュリティ | ベンダーのセキュリティ対策に依存 | 自社でコントロール |
今まで生産管理システムといえば、自社用にカスタマイズするオンプレミス型システムが主流でした。しかし、数百万円や数千万円規模の初期費用が必要なため、中小・小規模製造業にとっては導入が難しい状況でした。クラウド型が登場したことで、数十万円の初期費用+月額課金(サブスクのようなイメージ)から生産管理システムが提供できるようになり、中小企業の検討ハードルが大きく下がりました。
また、中小・小規模製造業と大手企業のもう一つの違いは、IT専任担当の有無です。オンプレミス型システムは、自社でサーバー管理等が必要となるため、サーバー運用・保守の担当者が必要です。また、自社向けにフルカスタマイズするためには、システムベンダーとの細かい要件定義を行うため、ITに詳しい担当者なしでは大きな負荷となります。
クラウド型の生産管理システムは、サーバー保守はベンダー側が行い、パッケージ内の基本機能での運用が可能なので、IT専任担当がいない中小・中堅企業でも導入が可能です。
しかし、クラウド型はオンプレミス型よりカスタマイズの自由度が低い場合があります。そのため、自社がやりたい運用が可能かどうかは、事前に確認が必要です。
導入サポートの充実の重要性
中小企業や小規模製造業において、生産管理システム導入の鍵を握るのは「導入サポートの充実度」です。IT専任の担当者がいない、もしくは現場でシステムに慣れていないケースが多い中小企業では、システムベンダーのノウハウ提供が必要だからです。
実際に、多機能なシステムを導入したものの使いこなせず、結局従来の紙やエクセルでの管理に戻ってしまうという中小製造業の企業も少なくありません。どれだけ高性能なシステムであっても、現場のスタッフが使いこなせなければ、そのメリットを最大限に享受できません。システムベンダーによる手厚い導入サポートがあれば、操作方法のレクチャーはもちろん、個別の業務フローに合わせた設定支援なども並走してもらえます。
導入後のサポートもあれば、トラブル時の迅速な対応など、導入後の運用をスムーズに進めるための支援も期待できます。導入を検討する際は、システムの機能やコストだけでなく、ベンダーのサポート体制が自社の状況に合うかも十分に確認することが重要です。
具体的なシステム例(3社)
中小企業・小規模向けの生産管理システムの例をいくつかご紹介します。
■SmartF(スマートF)

SmartFは、株式会社ネクスタが販売しているクラウド型の生産管理システムです。受注から出荷までの一連の機能から、必要なものだけを選んで導入することで、低コストでのスモールスタートが可能です。また、トライアル時点から導入支援担当がつくため、IT専任担当がいない中小・小規模製造業も安心して導入できます。
各工場が抱える問題を解決できるよう、複数のモジュール機能の中から必要なものだけを選んで導入することが可能です。 それにより、イニシャルコストやランニングコストをかなり抑えることができます。 また、現場の生産管理システム運用に対しての慣れに合わせて、徐々にバージョンアップすることができます。
■TECHS

TECHSは、株式会社テクノアが販売している中小製造業の業務に特化したパッケージソフトウエアです。
この生産管理システム自体は、「コストの削減」「利益体質の実現」「経営力の強化」といったコンセプトを持っています。
また、「個別受注型機械・装置業向け」「多品種少量型 部品加工業向け」の2種類のパッケージがあります。
■Factory-ONE 電脳工場

Factory-ONE電脳工場は、株式会社エクスが販売している生産管理システムで、下記のような特徴があります。
生産計画の立案から受注・出荷・手配計画(MRP手配/製番手配)・発注・受入・在庫・負荷・進捗・原価に至るものづくり情報を総合的に管理し、工場経営を強力に支援します。生産管理システムでありながら、請求・売掛・入金、仕入・買掛・支払など販売管理機能も標準装備した生販一体型のシステムとなっている。
中小企業・小規模製造業ではどんな業務から生産管理システムを導入すべき?

中小企業・小規模製造業が生産管理システムを導入する際、まずどの業務から着手すべきか悩ましいかと思います。システムには多様な機能が搭載されていますが、自社にとって何が必須かは、各製造業者の状況によって異なります。
一般的に、小規模製造業で最初にシステム導入を検討する機能としては、在庫管理機能と工程管理機能が挙げられます。これらの機能は、生産効率の向上やコスト削減に直結しやすいため、導入効果を実感しやすいと言えます。現在の生産業務における課題と、これらの傾向をもとに、まずシステム化する業務を検討することをおすすめします。
在庫管理機能
在庫管理機能は、中小中堅製造業において生産効率向上とコスト削減に直結する重要な要素です。中小中堅企業では、限られたリソースの中で効率的な生産体制を確立する必要があり、製品の余剰生産による廃棄ロスや、在庫不足による生産ラインの停止、納期遅延といった問題は、事業継続に大きな影響を与えかねません。
生産管理システムで在庫管理機能を導入できると、以下のような業務効率化が可能です。
- リアルタイムな在庫状況把握
- 在庫適正化
- 発注の精度向上
- 欠品・過剰在庫の防止
- 棚卸工数の削減
紙・エクセルと、生産管理システムの在庫管理の最大の違いは、リアルタイムに在庫状況が見えるようになることです。紙・エクセルだと、現場の入出庫と情報更新にタイムラグがあるため、最新の在庫数の把握が難しくなります。「エクセルの在庫管理表では実在庫がわからないので、現場に都度見に行っています」という声も多く聞きます。この手間をなくすことで、発注ミスが減り、常に適正在庫を保ちやすくなります。
適正在庫を保てるようになると、欠品による機会損失や高値調達、過剰在庫による保管コスト圧迫も回避できます。これらにより、製造現場全体の生産性が向上し、経営の安定化に大きく貢献することが期待できます。
特に中小中堅製造業では、大企業のような大規模なシステム投資が難しい場合が多いかと思います。費用対効果の高い在庫管理機能から導入を検討することが、効率的な生産管理システム導入の第一歩と言えるでしょう。
工程管理機能
工程管理は、生産現場の課題をいち早く発見し、改善するために不可欠です。多くの中小企業が直面する納期遅延やコスト増加といった課題は、工程管理の不備に起因することが少なくありません。
生産管理システムの工程管理機能を活用すると、以下の効率化に繋がります。
- 各工程の進捗状況をリアルタイムに可視化
- 作業日報のデジタル化
- どこで生産遅延が発生しているのか、その原因は何なのかを瞬時に特定
- 蓄積した生産実績データを改善活動に活用
例えば、特定の工程で生産遅延が発生したとします。紙・エクセル管理だと、現場に見に行かないと遅延状況を即座に把握できません。工程管理機能でリアルタイムに生産状況を把握できれば、遅延状況をすぐに把握できます。生産調整もシステム上で簡単に可能です。これにより、問題が深刻化する前に対応できるため、納期遵守や品質安定化にもつながります。
また、生産データがシステム上に蓄積できる点も重要です。生産遅延の今後の対策を立てる、もしくはより生産性を上げる改善活動をする際、いずれも生産データの現状分析が必要です。紙やエクセルだと情報を集約する手間が別途必要ですが、生産管理システムであれば生産実績データを簡単に作成できます。
特に中小中堅製造業では、限られたリソースの中で最大限の生産性を追求する必要があります。中小製造業が今後生き残っていくためにも、工程管理による生産性向上は重要だと言えます。
原価管理(拡張フェーズ)
在庫管理・工程管理のシステム化が実現すると、次のステップとして原価管理のシステム化も検討できます。
原価管理機能を利用すると、製品ごとの正確な原価を把握し、適切な販売価格の設定やコスト削減のポイントを特定できるようになります。在庫管理機能で材料費、工程管理機能で労務費のデータを収集できるようになると、製品原価管理も可能となります。
これらの原価内訳を詳細に分析することで、無駄なコストの発生源を突き止め、利益率向上に繋がります。中小企業の場合は、取引先への値上げ交渉の根拠材料としても、日頃の原価管理データが役立ちます。
負荷管理(拡張フェーズ)
負荷管理機能とは、設備や人員の稼働状況を可視化し、生産能力と実際の負荷を比較できる機能です。工程管理機能で生産進捗を見える化し、さらに生産負荷も見えるようにすることで、より効率的に生産計画を最適化できるようになります。
中小企業・小規模製造業が生産管理システムを導入する際の4つの注意点

中小企業・小規模製造業で生産管理システムを導入する際には、以下4点を考慮する必要があります。
- 社内ニーズを満たすシステムを選ぶ
- 生産形態にあったシステムを選ぶ
- 自社で使いこなせそうか検証する
- 拡張性のあるシステムを選ぶ
これらの要素を考慮せずに導入を進めると、システムが形骸化したり、かえって業務効率が低下したりするリスクがあるので注意が必要です。
社内ニーズを満たすシステムを選ぶ
生産管理システムを選ぶ際には、自社が抱えている問題点や課題点を明確にする必要があります。なぜなら、解決したい課題によって、選ぶべきシステムや優先すべき機能が変わってくるためです。
例えば、在庫管理に課題を抱えている場合は、リアルタイムで在庫状況を把握できる機能や、適切な発注をサポートする機能が充実したシステムが候補になります。一方で、工程管理の方が課題感が大きい場合は、各工程の進捗状況を可視化し、遅延の原因を特定しやすいシステムが望ましいでしょう。
具体的な業務フローの棚卸方法として、紙やエクセルで管理している帳票類や伝票の流れ、作業日報などの確認をおすすめします。実際にシステムベンダーとの打ち合わせでそれらを見せると、担当者とも業務の流れを共有しやすく、より良い提案を受けやすくなります。
生産形態にあったシステムを選ぶ
生産管理システムを選ぶ際には、自社の生産形態(例:個別受注生産、多品種少量生産、繰り返し生産など)に合致しているかどうかも重要です。
もし自社の生産形態とシステムのタイプが合っていない場合、システムを導入したにもかかわらず、かえって業務効率が低下するリスクが生じます。例えば、以下のような余計な手間やコストが発生し、システム導入のメリットを十分に享受できなくなってしまいます。
- システムに業務を合わせるために既存の生産プロセスを見直す必要が生じる
- システムでカバーできない部分を別のツールで補完したり、手作業が増えたりする
例えば、個別受注生産を主とする中小企業が、大量生産向けに特化したシステムを導入したとします。この場合、個別の部品管理や納期調整の機能が不足し、結果的に手作業での管理が増え、かえって業務が煩雑になることが考えられます。自社の生産形態を明確にし、それに最適な機能を持つシステムを選ぶことが、失敗しない生産管理システム導入の鍵となります。
自社で使いこなせそうか検証する
中小・小規模製造業で生産管理システムを導入する際は、自社で使いこなせるかどうかも確認します。機能が過剰すぎないシステムや、トライアル導入に対応しているシステムがおすすめです。
無駄なコストを抑え、現場の負担を最小限にするには、必要最低限の機能が揃ったシンプルなシステムを選ぶことが重要です。高機能なシステムは魅力的ですが、全ての機能を使いこなせる企業は多くありません。中小・小規模製造業では、以下のような導入失敗例もよく見受けられます。
<よくある導入失敗例>
- 必要以上に機能が多いシステムを高い費用で契約してしまう
- 機能の多さが操作の複雑さにつながり、現場作業者の負担を増やす原因となる
また、導入前のトライアル導入が可能なシステムを選ぶことも効果的です。特に、現場作業者が問題なく操作できるか、システムで対応できないイレギュラー運用が発生した場合はどう対応するかなど、具体的な状況を想定して検証することが重要です。ここで不安を解消した状態で本格導入すれば、システム導入後も定着しやすくなります。
拡張性のあるシステムを選ぶ
機能の拡張性がある生産管理システムは、以下2点のメリットから中小企業・小規模製造業に向いていると言えます。
<拡張性のあるシステムが中小企業に向いている理由>
- 中小企業が成長するにつれて新たに必要となる機能追加にも対応可能
- 必要最低限の機能で導入し、基本運用に慣れた後に機能を徐々に追加するという「段階的な導入」が可能
近年の製造業では、市場ニーズの変化や新規事業への参入など、イレギュラー対応や業務内容の変化がより頻繁に起こり得ます。そのため、一度導入した生産管理システムに、機能の追加や仕様変更が必要となる可能性も高くなります。変化に対応できない、つまり拡張性の低いシステムを選んでしまうと、その都度コストや手間をかけてシステムを再選定・移行しなければなりません。
また、段階的な導入ができる点も、中小企業の導入負担を減らせるというメリットがあります。生産管理システムを導入すると、現場での業務に変更が伴います。そのため、一度に多くの機能を導入すると、現場からの反発が起きやすくなります。「在庫管理から始め、現場が慣れたら工程管理も導入してみる」のように、少しずつ機能拡張できるシステムを選ぶと、システム導入が成功しやすくなります。
特にクラウド型の生産管理システムには、必要な機能だけを段階的に追加できる、柔軟な課金体系を持つものがいくつかあります。ただし、システムの機能拡張ができないパッケージソフトもあるので、システムベンダーに事前確認することをおすすめします。
参考:補助金・税制優遇活用のメリット・デメリット
生産管理システムの導入には、補助金や税制優遇制度の活用も有効です。今まで実施されてきた制度を例に上げると、IT導入補助金・ものづくり補助金・DX投資促進税制などがあります。
補助金などの制度を利用することで、初期費用や運用コストの負担を軽減できる可能性があります。しかし、これらの制度の申請には以下のデメリットがあることも、申請前に知っておく必要があります。
<補助金や税制優遇を活用したシステム導入のデメリット>
- 複雑な手続きが必要
- 導入タイミングは公募スケジュールに合わせる必要があり、審査に時間がかかる傾向
- 審査の結果、採択されない場合や減額となる場合あり
- 受給後も、実績報告や監査などの継続的な対応が求められる場合あり
補助金の活用を検討する際は、メリットとデメリットを十分に理解し、自社の状況に適した制度を選ぶことが重要です。
中小企業・小規模製造業での生産管理システム導入手順

具体的に、中小製造業が生産管理システムを導入する手順は、大きく分けて以下4ステップあります。
①目的要件を考える
生産管理システムの導入の成功は、導入前の現状把握と課題整理にかかっています。
特に考えなければならないのは以下3点です。
- 生産現場での現状の運用を確認し、整理する
- 何が自社の問題点や課題なのかを整理し、その上で解決したい優先度を決める
- 導入する時期、ターゲットコストを設定する
この3つを行うことにより、自社にとって最適な生産管理システムを見つけ、コスト・工数削減や現場の混乱を最小にすることが可能となります。
②導入テスト(トライアル)を行う
生産管理システムは、説明を聞くだけでは自社の課題を解決できるか、現場にフィットするかどうかを判断するのが難しいものです。だからこそ、導入前テストやトライアルを行うことが不可欠です。
導入テストでは、特に以下の3点を確認します。
- 実際の生産に合わせてシステムを動かしてみて、問題なく運用できるか
- 現場作業者が問題なく操作できるか
- システムで対応していないイレギュラーな運用があった場合、どう対応するか
もし、導入テストやトライアルができないシステムを検討する場合は、業務フローを明確にベンダーに伝えたうえでデモ運用を見せてもらうなどの方法を取ります。
③本導入
選定した生産管理システムを本格的に導入する段階では、以下3つの
- 各種マスタの作成:既存の部品表や工程データなどをシステムにマスタ登録
- 運用フローの作成:業務フローが変わる部分の精査・マニュアル作成
- 操作説明の実施:システムやIoT端末の使用方法を説明
これらの準備作業は、導入サポートがあるシステムベンダーであれば支援を受けられます。IT専任担当者がいない中小企業にとって、これらのデータやフローを正確に整備するのは大きな業務負担になります。ベンダーの支援があれば、安心して導入を進められるうえに、システムに慣れるまでの期間の短縮も期待できます。
④導入後の効果測定
生産管理システムの導入から約3〜6か月を目処に、その効果を測定することをおすすめします。
特に中小企業は、限られた人数で現場を回しているケースが多いため、システム導入による業務の変化で一時的に大きな負荷がかかることがあります。現場協力のお陰で多くの業務改善ができたことを伝えることで、社内PRや現場のモチベーションアップに繋がり、長期的なシステム運用の定着に繋がります。
具体的な効果測定の方法としては、まず「生産性の向上」を定量的に評価することが挙げられます。
<生産性の定量的な評価例>
- 2日かけて行っていた棚卸しが、1日で終わった
- 特定の工程にかかる時間が、月10時間短縮した
- 生産ラインの稼働率が、5%改善した
次に「コスト削減」についても検証します。例えば、在庫管理機能の導入により、過剰在庫が減少し、保管コストや廃棄ロスの削減に繋がっているかを確認します。また、発注精度の向上により、緊急発注による割高な仕入れが減少したかなども、具体的な数値で把握できます。
<コスト削減効果の検証例>
- 過剰在庫の減少で、在庫金額が100万円減った
- 原材料の誤使用がなくなり、平均300万円の廃棄ロスがゼロになった
さらに、「ミスの削減」も重要な評価指標です。手作業でのデータ入力や情報共有によるヒューマンエラーがどの程度減少したか、品質不良率の変化なども確認することで、システムの導入が品質向上に貢献しているかを測ることができます。
これらの効果測定を行うことで、システムの導入が期待通りの成果を出しているかを客観的に評価できます。もし期待通りの効果が出ていない場合は、運用の見直しや追加の機能導入など、改善策を検討するきっかけにもなります。導入効果を定期的に測定し、改善を繰り返すことが、生産管理システムの成功には不可欠です。
生産管理システムでありがちな失敗パターンと回避策チェックリスト

当社が数多くの生産管理システム導入に携わる中で、よく見聞きしてきた失敗パターンを以下にまとめました。回避方法もまとめたので、ご活用ください。
| ありがちな失敗パターン | 回避策(具体行動) | |
|---|---|---|
| 1 | 目的が「コスト削減」だけで曖昧 | 数値目標を段階的に設定(例:バーコードスキャン活用率 95%→在庫圧縮‑10%) |
| 2 | 現状の生産工程が不明瞭なままシステム検討 | 現場ヒアリングや帳票の現物を集めて、業務フロー図を作成 |
| 3 | コスト試算が初期導入費用だけ | 3~5年のトータルコスト(月額費用・サポート費用など含む)でシミュレーション |
| 4 | 機能・価格だけでシステム選定 | セキュリティ・アップデート頻度・サポート体制などを総合的に評価 |
| 5 | カスタマイズ前提でベンダー丸投げ | カスタマイズが増えるほど、費用や要件定義の手間が増大→なるべく標準機能での運用ベンダーと相談すると業務標準化にも効果的 |
| 6 | 運用ルールが属人化し再びカオス化 | 権限・承認フローをシステムで設定し、各担当者ごとの役割を明確化 |
中小企業・小規模製造業向け生産管理システムならSmartF
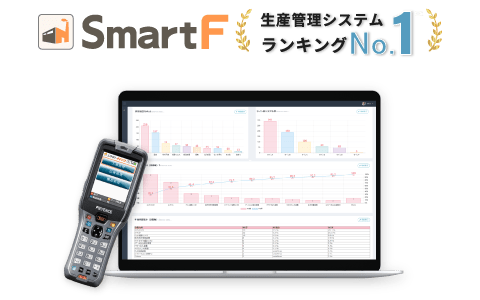
中小企業や小規模製造業の皆様に最適な生産管理システムをお探しなら、「SmartF(スマートF)」がおすすめです。
「SmartF」はクラウド型システムであり、機能数や初期費用を抑えて導入できることから、多くの中小・小規模製造業者に選ばれています。まずは在庫管理や工程管理といった重要な機能からスモールスタートし、段階的に機能を拡張していきたい企業におすすめです。
さらに、導入支援付きトライアルも可能で、IT専任担当者がいない企業でも導入に成功しています。
■SmartF:中小企業の導入事例(一例)
- 成型品業界/会社規模30~99人:1人あたり売上1.4倍!脱アナログ・脱属人化で棚卸工数は1/10に圧縮、欠品や出荷遅れはゼロに
- 化学品業界/会社規模100~299人:紙・エクセル管理をやめて年間3000時間以上の工数削減!先入先出・期限管理の精緻化で品質管理体制の強化まで実現
- 組立品業界/会社規模30~99人:在庫管理のシステム化に成功!リアルタイムな在庫管理で年間100万円の在庫削減
中小製造業向け「生産管理システム」を導入したい方はこちら
22種類の生産管理システムをランキングで比較
初期費用相場や選び方のポイントをチェック
生産管理システムをそれぞれの特徴や初期費用相場などで比較したい場合は、「生産管理システムランキング」も是非ご覧ください。生産管理システムは、自社の製品・生産方式・企業規模などに適したものを導入しないと、得られるメリットが限定されてしまいます。事前適合性チェックや生産管理システムを選ぶ前に押さえておきたいポイントも解説していますので、製品選びの参考にしてみてください。



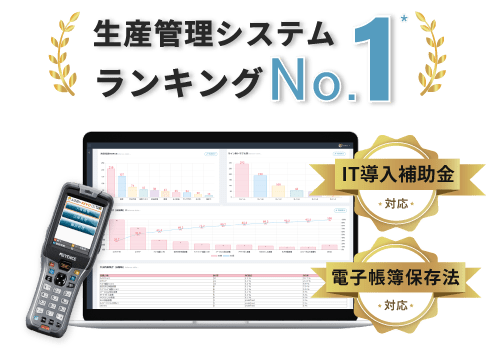





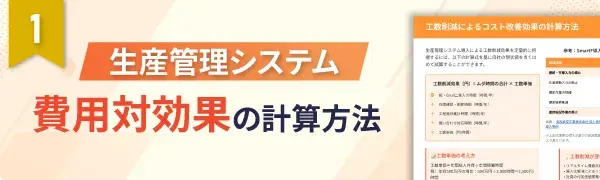






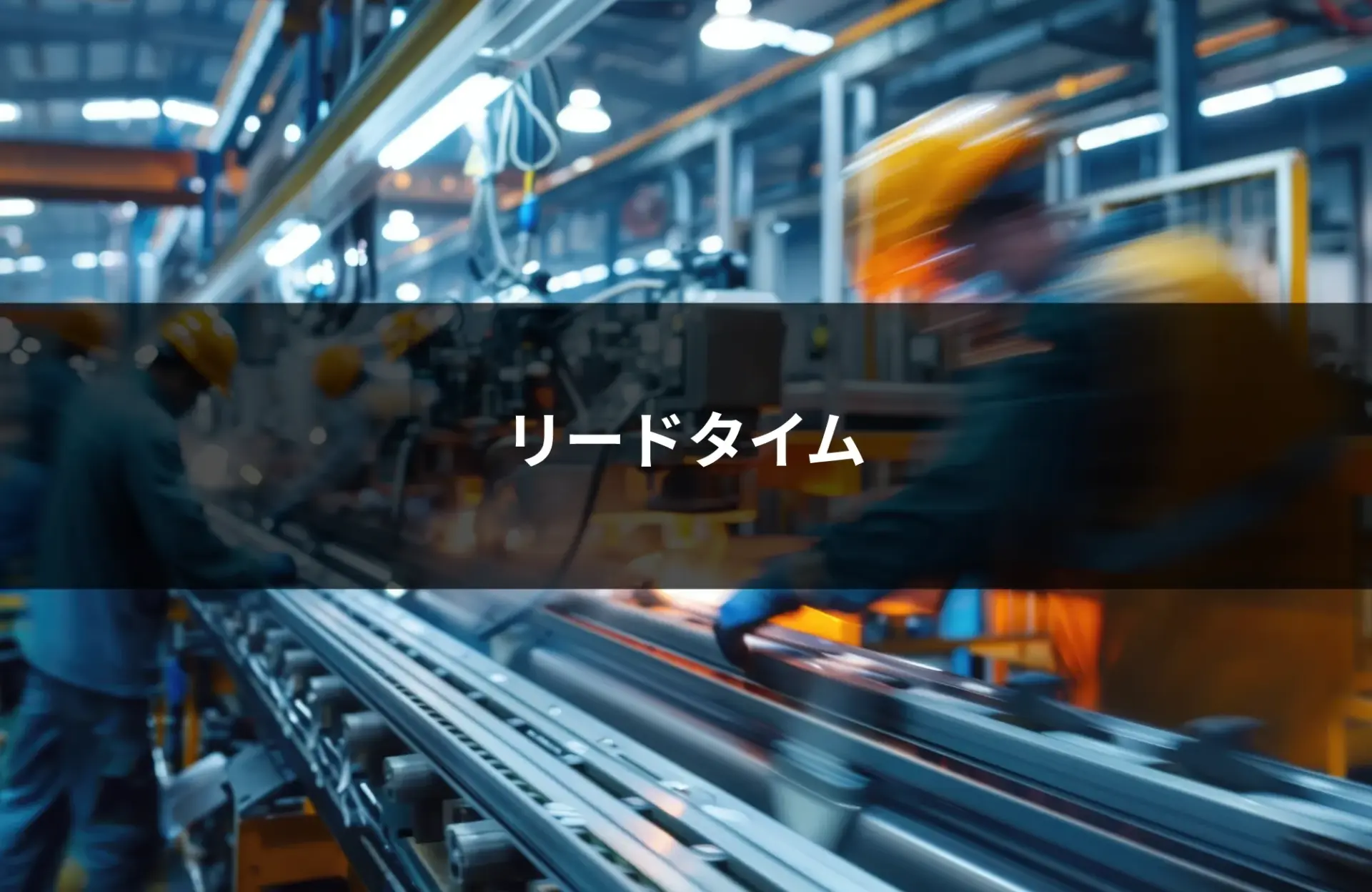


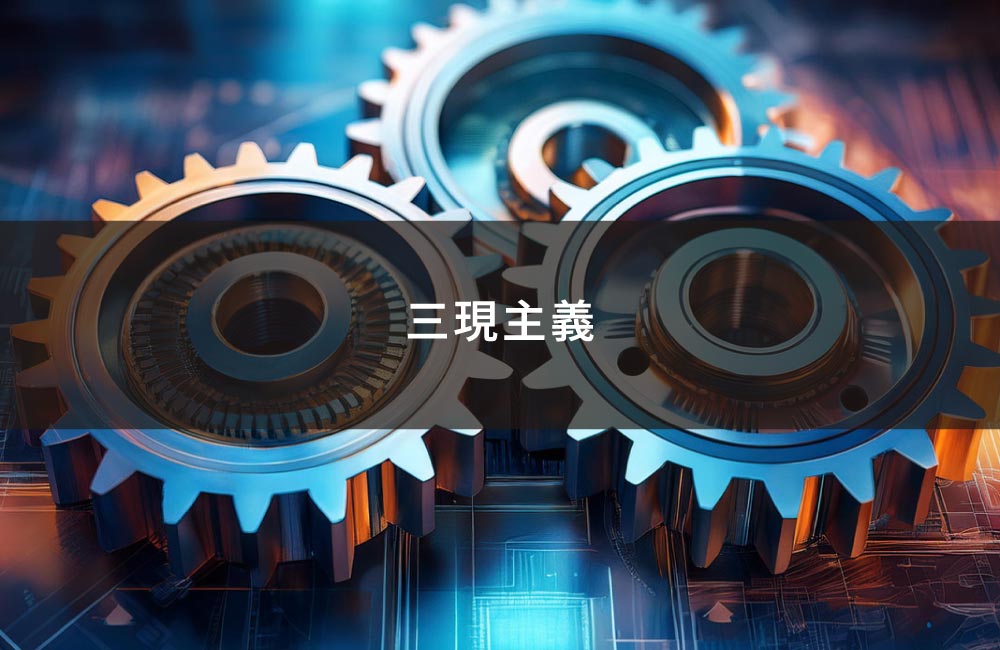
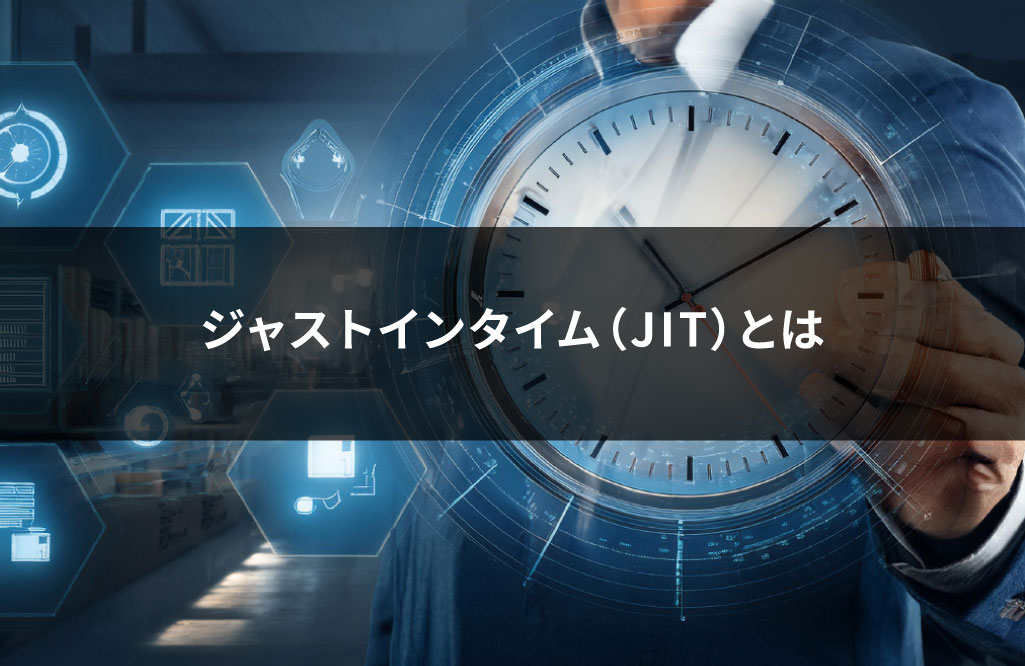







.jpg)