サプライチェーンリスクに立ち向かう!複雑化する供給網で企業が取るべき対策とは?
公開日:2025年02月07日
最終更新日:2025年02月07日

グローバル化の進展により、製造業を取り巻くサプライチェーンリスクはかつてないほど高まっています。自然災害や感染症、政治的不安、経済変動、さらにはサイバー攻撃まで、多岐にわたるリスクが事業運営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、これらのリスクとその影響について具体例を交え解説しました。さらに、これらのリスクに対して、製造業が取り組むべき対策について詳しく紹介します。
サプライチェーンリスクとは何か
サプライチェーンリスクは、企業が製品やサービスを顧客に届けるまでの過程で直面する潜在的な問題を指します。予測できない多種多様な要因によって引き起こされ、事業に甚大な影響を及ぼすものもあります。
グローバル化によるリスクの増加
グローバル化の加速トレンドは、製造業のサプライチェーンリスクが大きく増加する要因の一つです。グローバル化に伴い、サプライチェーンが地理的に広域化し、ステークホルダー(利害関係者)も増大の一途をたどっています。その結果、供給経路の複雑化をもたらし、次のような観点でリスクが高まっています。
- 規制・関税:関係国家が多くなり、政治的影響を受ける確率が高まる
- 品質管理:産地・企業が多様化し、製品・原材料の品質ばらつきが大きくなりやすい
- 物流:輸送距離が長くなり、遅延が生じやすくなる
リスクが及ぼす影響の範囲
サプライチェーンリスクが実際に発生すると、企業の運営全般に広範な影響を及ぼします。想定される主な影響範囲は次の通りです。
- 企業内部への影響:生産活動の停止・遅延、製品コスト増、品質低下
- 取引先への影響:取引停止、サプライチェーン全体への波及
- 顧客への影響:納期遅延、販売価格の上昇
- 企業ブランドへの影響:製品供給や品質問題による顧客・投資家・社会からの信用失墜
これらは、最悪の場合、企業の競争力や市場シェアの低下に繋がるケースもあります。
製造業における主なサプライチェーンリスク

サプライチェーンを寸断・遅延させるリスク要因は多種多様であり、容易に予測できるものばかりではありません。ここでは、具体的なサプライチェーンリスクについて、実際に起きた事象と関連付けて解説します。
自然災害や感染症拡大
洪水、地震、台風といった自然災害や、パンデミックによる感染症拡大は、サプライチェーンに対する重大な脅威です。これらの災害は、工場や物流拠点の機能不全を招き、サプライチェーンの断絶による社会混乱に繋がる可能性があります。最近の自然災害・感染症拡大の例とその影響は次の通りです。
| 名称 | 概要 | 製品群への影響 |
| タイ洪水(2011年) | 大規模洪水が工業団地を直撃 | HDD(ハードディスク)の不足に伴う価格急騰自動車部品供給停止により、トヨタ・ホンダの生産縮小 |
| 熊本地震(2016年) | 地震により、半導体工場が被災 | ソニーの半導体工場が一時操業停止し、スマートフォン向け部品が不足半導体不足が自動車メーカーにも波及し、一部車種で生産遅延 |
| 新型コロナウイルス感染症(2020年~) | 世界的なパンデミックにより、ロックダウンや物流の停滞が発生 | 電子部品や衣料品などの供給が世界的に不足医療品・マスクの需要が急増し、供給が追いつかず混乱世界中の海上輸送が混乱・遅延し、物流コストが大幅増加 |
こうしたリスクは、事前想定に基づく対策が不十分な場合、迅速な対応が難しいことを露見しました。
政治的・社会的不安
貿易戦争、テロや暴動などの政治的・社会的な不安定さも、生産活動をはじめとしたサプライチェーンに直接的な障害をもたらします。
例えば、2018年から顕在化した米中貿易摩擦では、貿易戦争によりハイテク製品を始めとした関税引き上げや輸出制限が発生。これによって、中国産シェアの高かった半導体製品の調達コストが急騰し、サプライチェーンを中国以外に移転する動きが加速しました。
経済危機や価格変動
経済危機や資源価格の変動は原材料のコストや供給の安定性に直接影響を与え、サプライチェーン全体を混乱させます。
国・地域の金融不安は取引先の倒産による製品供給の寸断を招き、急激な通貨下落は輸入コストの急騰に繋がります。また、原油や金属など価格の急変は、製品コスト・物流コストに大きく波及します。
実際に、 2008年のリーマンショックでは、アメリカで発生した金融危機が世界経済全体に波及しました。その結果、多くのサプライヤーが倒産して製品供給が途絶したり、原材料の価格が乱高下して企業が調達計画を立てにくくなったりしました。
サイバーセキュリティへの攻撃
企業の情報システムやデータが外部から侵入され、製造・物流・取引先との連携に障害が発生するサイバー攻撃への脅威は増加の一途をたどっています。具体的な脅威には以下のようなものがあります。
- IoTやクラウドサービスの活用による、オンライン上のシステム・デジタルデータ
- セキュリティの脆弱な取引先のシステム経由での侵入
- システムを人質にとり、身代金を要求(ランサムウェア攻撃)
実際に、2022年にはトヨタ自動車のサプライヤーがサイバー攻撃を受け、システム障害を引き起こしました。この障害はトヨタ全体の生産管理システムにも影響を及ぼし、国内のトヨタ全工場が1日間も操業停止する事態となりました。
このように、サプライチェーンの一部におけるサイバーセキュリティの脆弱性は、サプライチェーン全体に波及する重大なリスクです。
品質に対する意識の異なるサプライヤー
サプライチェーン拡大に伴い、品質に対して意識レベルの異なるサプライヤーとの取引を余儀なくされるケースも少なくありません。地理的制約や物量確保の面で有利であったとしても、製品の品質低下につながるリスクがあります。規格外品の納入は、最終製品の品質不良発生リスクを高め、生産停止となることがあります。
このため、企業はサプライヤーとの厳格な品質仕様を取り決めるとともに、定期的な監査を通じて納入品の品質維持担保に努める必要があります。
製品輸送におけるリスクの高まり

直接的に製品に関わるサプライチェーンリスク以外に、物流における問題も近年リスクが高まっています。
2021年には大型コンテナ船がスエズ運河で座礁し、運河が約1週間封鎖。これにより欧州とアジアを結ぶ船舶輸送が途絶え、自動車部品、衣料品、電子部品など、多くの製品の輸送スケジュールが大幅に乱れました。また、物流の停滞に伴い、世界経済に約600億ドル規模の損失が発生したと言われています。世界の物流ネットワークが特定の重要ルートに依存している脆弱性を浮き彫りにしました。
また最近では、運航スケジュールの遅延防止やコスト削減のために、日本への寄港を取りやめる「抜港」も大きな課題になりつつあります。グローバル化に伴う貨物量の増加を背景として、コンテナ不足や運賃高騰などの国際物流の混乱が続いており、日本企業の輸出入に影響を及ぼしています。
こうした事例は、供給網の多様化や在庫管理の見直しなど、事前のリスク対策の重要性が強まっていると言えます。
発注者側が取るべき基本的な対策

次に、このようなサプライチェーンリスクに備えるため、発注側でとれる主な対策を見ていきます。
リスクアセスメントの実施
サプライチェーンのリスク対策の第一歩は、リスクアセスメントです。サプライチェーン全体を俯瞰し、潜在的なリスクを特定し、それぞれのリスクの発生確率や影響度を評価します。これにより、最も許容できないリスクに対して優先的に対策を講じることができます。
リスクアセスメントは定期的に見直し、市場環境の変化の反映も行います。こうした取り組みは、ISO9001(要求事項6.1リスクおよび機会)やIATF16949(要求事項6.1.2.1:リスク分析)などの品質マネジメントシステム(QMS)の国際規格でも要求されています。
BCP(事業継続計画)策定
BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、リスクアセスメントで特定されたリスクに直面した際に、事業継続のために取るべき対応をまとめた計画書を指します。
製造業では、サプライチェーンにて問題が起きた際に、速やかに代替手段を採用できないケースも多いです。このため、あらかじめ代替策について評価したり、緊急時にもスムーズに対応できる組織体制を整備したりすべきでしょう。BCPを策定することで、リスクに対する事業への悪影響を減らすことができます。
拠点や仕入先の分散
製造業におけるBCPでは、拠点や仕入先を複数の地域やサプライヤーに分散させることが一般的です。
調達先の複社購買化により、原材料メーカーの経営判断などによる供給リスクを抑えられます。また、原材料や自社製品の製造拠点が散在していれば、地政学的リスクや自然災害の影響があっても一定の製品供給が可能となります。
契約時のリスク分担の明確化
サプライチェーン上でのトラブル発生時の責任範囲や対応方法を契約書で明示することで、迅速な対応と混乱の回避に欠かせません。
契約書には、自然災害などの不可抗力によるリスクとその対応を明確にし、納期遅延、品質不良、価格変動などのトラブル発生時の対処方法を具体的に記載します。こうした明確な契約時の合意は、トラブル発生時の混乱を最小限に抑え、法的紛争に発展するリスクも減らせます。
組織的なセキュリティ体制の構築
サイバー攻撃や情報漏洩リスクは近年高まっており、サプライチェーンにおける組織的なセキュリティ体制の構築は必須対応事項です。具体的には次のような対応が求められます。
- セキュリティポリシーの策定:企業全体で統一したセキュリティ方針を定める
- 技術的対策:ウィルス対策ソフトを導入し、定期的なデータのバックアップを実施する
- セキュリティ教育:フィッシングメール識別方法など、セキュリティ意識を向上させる
- インシデント対応計画の策定:初動対応をマニュアル化し、緊急連絡網を整備する
このようなセキュリティ体制は、サプライチェーン全体のリスク耐性の改善に繋がります。
サプライヤーとの継続的なコミュニケーション
サプライヤーとの継続的なコミュニケーションは、サプライチェーンにおけるリスク管理において欠かせない要素です。サプライヤーと密な情報共有を行っていれば、リスクや問題を早期発見し、迅速な対応が可能となります。
定期的な情報交換の場を設けたり、クラウドシステムを活用してリアルタイムで情報を共有したりするのも効果的でしょう。こうした取り組みを継続することで、サプライチェーンの安定性が向上します。
運用管理のチェック強化
在庫管理、物流、製造プロセス、品質管理など、サプライチェーンにおける運用管理を継続的に監視・評価することも重要です。定期監査によって、運用上の課題を早期発見することができ、異常を未然に防ぎ、リスクを最小限に抑えることができます。
特に、品質や納期などの重要な情報は常時モニタリングし、異常があれば速やかに検知され、迅速に対応する仕組みが維持できるようにします。
システム管理によるリスク対策の効率化
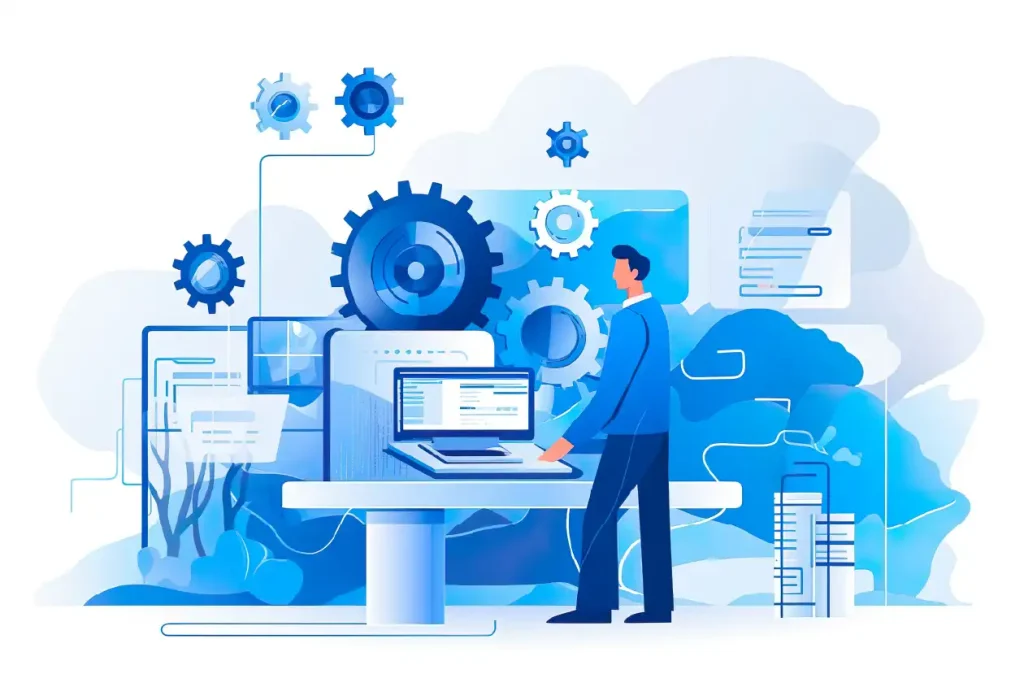
サプライチェーンリスク管理を効率化するためには、システムを活用した管理方法が効果的です。ITツールやクラウドサービスを活用することで、情報の一元管理や可視化が進み、リスク対応の迅速化が可能です。
サプライヤー管理のシステム化
サプライヤー管理のシステム化は、サプライチェーンにおいて効率的なリスク管理を実現する有効な手段です。
専用のソフトウェアやプラットフォームを活用すれば、サプライヤーの契約内容、納期、品質などの一元的管理が容易となります。これにより、問題発生時に速やかに必要な情報を参照できます。
また、サプライヤーごとの状況をリアルタイムで確認できるため、リスクの早期検出が可能です。その結果、サプライチェーン全体の透明性が向上し、管理業務が効率化されます。
クラウドサービスを活用したリスクの可視化
クラウドサービスの利用により、サプライチェーンにおけるリスクを容易に見える化できます。各サプライヤーの在庫状況や輸送状況をオンラインで把握し、異常が発生した際に迅速にアラートで情報共有することができます。
システム導入にあたり初期コストが課題となるケースも多いですが、サブスクリプションモデルの活用で初期費用の圧縮が可能なケースもあります。
サプライチェーンのリスク管理の第一歩である「在庫の見える化」をクラウド型システムで実現した事例はこちら:
【在庫管理システム】在庫の見える化と年間1000時間以上の工数削減に成功!
システム連携による情報の一元管理
発注業務やサプライヤー管理において、個別に利用しているシステムの連携が実現できれば、情報の一元管理には有効です。
ERPシステムやSCMシステムでは、在庫状況や調達計画、発注履歴などの情報を一つのプラットフォームで管理可能なため、業務効率が大幅に向上します。
一方で、これらのシステムの改修は高額であることも多く、導入へのハードルが高いケースもあります。生産管理システムで他システムと連携させることで、安価な一元管理が実現できます。
リアルタイムで在庫の動きと販売管理システムを連動させた事例はこちら:
【受発注/在庫管理システム】在庫管理の一元化と属人化の課題を一挙に解決!ミスほぼゼロで顧客満足度向上
22種類の生産管理システムをランキングで比較
初期費用相場や選び方のポイントをチェック
生産管理システムをそれぞれの特徴や初期費用相場などで比較したい場合は、「生産管理システムランキング」も是非ご覧ください。生産管理システムは、自社の製品・生産方式・企業規模などに適したものを導入しないと、得られるメリットが限定されてしまいます。事前適合性チェックや生産管理システムを選ぶ前に押さえておきたいポイントも解説していますので、製品選びの参考にしてみてください。




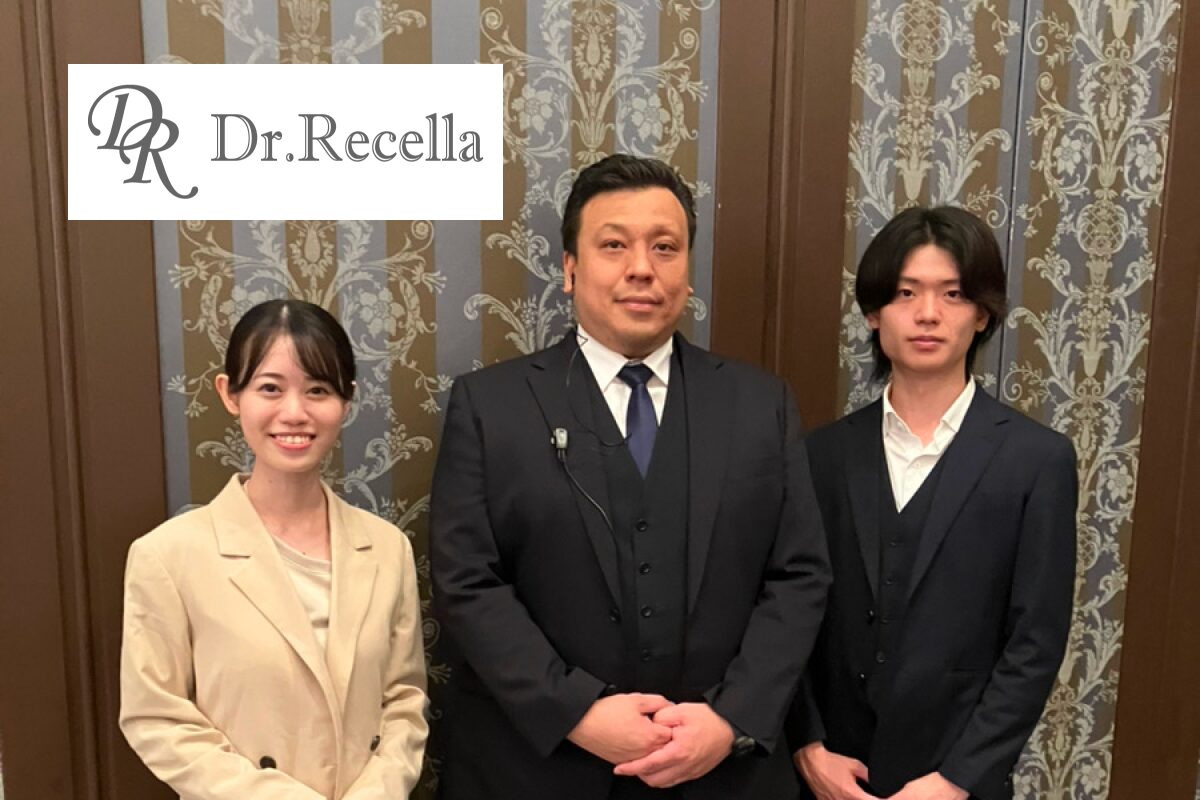

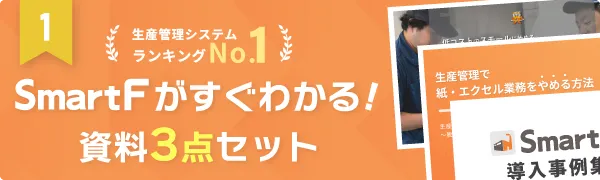





.jpg)


















