【具体例付き】製造業の人手不足解消:IT技術活用で生産性と労働環境を改善
公開日:2025年05月26日
最終更新日:2025年07月02日

製造業では人手不足が深刻化し、生産効率や品質、企業の将来性にも大きな影響を与えています。本記事では、人手不足の背景から、経済産業省が示す解決策、さらにクラウド型システムを活用した具体的な成功事例を紹介します。中小企業にも導入しやすい初期投資が比較的安価なデジタルツールを活用し、人手不足の現場の課題を、どのように乗り越えていくか、その解決策のヒントを探ります。
製造業における人手不足の現状と背景

近年、日本の製造業は、深刻な人手不足に直面しています。その背景には、少子高齢化による労働人口の減少に加え、若者を中心とした人材の流動化や、製造業自体に対するネガティブなイメージが関係しています。このような要因が重なって人手不足となり、企業の生産性や競争力に影響を与えています。
少子高齢化による労働力の減少
日本では少子高齢化が急速に進行しています。15歳から64歳の生産年齢人口は1995年の8716万人をピークに年々減少し、2023年には7395万人となっています。この傾向は今後も加速し、2070年には4535万人まで減少すると予想されています)参考:令和6年版 高齢社会白書(全文))。
これにより、多くの産業で人手不足が問題となっています。製造業においても状況は深刻で、製造技術者(開発を除く)の有効求人倍率は2.12と、平均の1.22を大きく上回っています(参考:一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分)について)。
また、現在の製造業において、若年層の入職者が減少する一方で、定年退職するベテラン社員は増加しています。このため、現場の技術継承や製品品質の維持に支障をきたしています。この流れは今後も続く見込みであり、企業は人材確保戦略の見直しを迫られています。
人材の流動化
現代の労働市場では、終身雇用から転職を前提としたキャリア構築へと価値観が変化しています。また若年層は、働き方や勤務地を考えて就職先を選択する場合が多く、製造業に入職しても他業種に転職するケースが増えています。加えて、都市部と地方での雇用格差やリモートワークの普及もあり、リモート勤務できない現場作業が必要な製造業は、人材が定着しにくい状況です。
こうした人材流動性の高まりに対し、企業側は柔軟な雇用制度やキャリアパスの整備が求められています。
製造業に対する負のイメージの定着
製造業は「きつい・汚い・危険(3K)」というイメージが根強く残っており、若年層や女性の就職希望者に敬遠されやすい要因の一つとなっています。また、IT業界やサービス業に比べて技術革新の進みが遅いという印象もあり、将来性への不安を感じる人も少なくありません。
このような負のイメージは、企業努力による環境改善やデジタル技術の導入で変えていく必要があります。職場の魅力向上や広報活動も、今後の採用活動において重要なポイントです。
人手不足が与える製造業への影響

人手不足は、単なる労働力減少という問題にとどまらず、製造業の根幹に関わる様々な問題に影響を与えます。生産効率の低下、企業競争力の低下に始まり、現場従業員の労働負担増加や離職率の上昇、さらには製品品質の低下や事業継続すら困難になるケースもあります。このような問題を未然に防ぐためにも、早急に対策を講じる必要があります。
生産効率の低下
必要な人員が確保できない状況では、生産工程に遅れが生じやすくなり、生産ラインの稼働率が低下します。現場では複数の業務を一人でこなす場面が増え、手戻りやミスが発生しやすくなります。
また、ベテラン社員の退職により、今まで問題なく稼働していた工程がボトルネックとなる場合もあります。結果として、納期遅延やコスト増加が起こり、顧客からの信頼を損ねるリスクも高まります。
企業の競争力低下
グローバル市場においては、製品品質や価格だけでなく、短納期での生産や柔軟な対応力も重要な競争要素です。人手不足により、これらの要求に応えられなくなると、顧客からの信用を失い、受注が減少し、市場シェアを失うことにつながります。
さらに、イノベーションに割けるリソースも不足し、新しい技術や製品の開発が滞ることで、企業の成長が鈍化してしまう恐れがあります。
従業員の労働負担の増加
人手不足の現場では、従業員1人当たりの業務量が増加し、長時間労働が常態化する傾向があります。これにより、従業員のモチベーション低下や体調不良を引き起こしやすくなり、最悪の場合、過労などの労働災害やメンタルヘルスの問題に発展する可能性もあります。
このような負のスパイラルに陥ると、さらに人材が流出していく事態になります。
離職率の増加
人手不足により、過度な業務負担を抱えたり、働いている会社に対する将来性への不安から、退職をする人は数多くいます。離職率が高まると、採用活動の負担も増加し、採用後の教育コストもかかり、企業の経営資源が浪費されます。
また、離職率が多い=ブラック企業というイメージが付きまとうため、求人を出しても応募が来ないといったことになり、採用活動の難易度も上がります。
製品品質の低下
経験や技能が不足した従業員による作業ミスや、過重労働による注意力低下が常態化すると、製品品質の低下や不良率の増加を引き起こします。品質トラブルは顧客からの信頼を損なうだけでなく、リコールやクレーム対応などで多大なコストが発生します。
このようなトラブルは、企業にとって致命的なダメージとなることがあります。実際に、重大な品質問題を引き起こし、莫大な負債を抱えて経営破綻した大企業も存在します。
後継者不足による事業撤退や倒産
中小製造業においては、熟練工の高齢化とともに後継者不在が深刻な問題となっています。事業承継がうまく進まず、技術や取引先との関係が継続できない場合、廃業や倒産に追い込まれるケースも少なくありません。
日本の製造業の9割以上は小規模・中規模企業のため、地域経済や業界全体への影響も避けられず、日本のものづくり力そのものが揺らいでいると言えます(参考:令和5年12月13日「中小企業の企業数・事業所数」中小企業庁)。
経済産業省が示す製造業の人材不足の解決策=DX推進と人材確保

製造業の人手不足を解決するためには、単なる労働力の補充だけではなく、業界全体での革新的な取り組みが必要です。経済産業省は、デジタル技術の活用(DX)を中心に、IT人材の育成や外国人材の活用を推進しています。
デジタル技術の活用・DX推進による生産性向上
製造業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は、単に効率化を目指すだけでなく、人材不足を補完するための重要な手段です。AIやIoT、ロボティクスを活用した自動化・省力化により、少ない人数でも高い生産性を維持することが可能になります。
例えば、AIによる予測分析を活用すれば、生産計画の最適化や設備の故障予兆を早期に発見することができ、現場作業員の負担を軽減することができます。これにより、限られた人員での対応が可能となり、人手不足の問題を部分的に解決することができます。
また、クラウドベースの生産管理システムを導入することで、情報の一元化やリアルタイムでのモニタリングが実現し、作業員はより効率的に作業を進めることができます。これにより、業務のムダを省き、生産性を大きく向上させることができます。
IT人材の育成
製造業におけるデジタル化を進めるためには、IT人材の確保と育成が不可欠です。現在の製造業では、IT技術を活用したシステムや機器の運用が求められており、そのための専門知識を持つ人材が不足しています。
そこで経済産業省は、企業が積極的にIT人材を育成するための支援を行っています。具体的には、産学連携による研修プログラムや、業界特化型のITスキルアップ研修などが推進されています。
これにより、従業員は新しい技術を習得し、デジタル技術を活用した生産性向上を実現できるようになります。また、IT人材の育成が進むことで、製造業内でのデジタル人材の不足を解消し、業務のデジタル化が加速することが期待されます。
外国人材の活用
日本の労働市場における人手不足を解消する手段の一つに、外国人材の登用があります。製造業では、特に人手を必要とする工程が多いため、外国人労働者の積極的な受け入れが進んでいます。
製造業における外国人労働者数は、2008年の19.3万人から増加傾向です。2020年の新型コロナウイルス感染症の影響で一時減少しましたが、2023年には55.2万人と15年で約2.8倍となっています(参考:2024年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告))。
外国人材を活用することで、製造現場に新たな視点や技術を取り入れることができ、業務の多様化や生産性の向上が期待されます。また、外国人労働者の雇用を通じて、国際的な視野を持つ企業文化が育まれ、グローバル競争力が高まることにもつながります。これらの施策を通じて、製造業の人手不足を解決し、持続可能な発展を支える基盤が整備されていくことが期待されています。
製造業DXのメリットは、人手不足解消以外にも多い

デジタルツールを徐々に導入し、DX化が進むと、人手不足以外にもさまざまなメリットがあります。単なるIT化にとどまらず、生産現場の効率化、人材育成、労働環境の改善、さらには経営レベルでの意思決定スピードの向上も期待できます。
以下では、製造業におけるDX推進によって得られる具体的なメリットを詳しく見ていきます。
工数削減による少人数運用の実現
従来の製造現場では、多くの作業が人手に依存していたため、作業員の確保が必要不可欠でした。しかし、IoTセンサーやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)、AIによる工程監視・予測を導入すると、多くの作業の自動化や工数削減が実現します。これにより、少人数でも安定した生産体制を維持できるようになり、人手不足に悩む中小製造業にとっては大きな武器となります。
一例として、設備の稼働データをもとに保全タイミングを自動で予測すれば、常時人が監視する必要がなくなり、作業の集中化と省力化が実現します。生産性の向上だけでなく、コスト削減にもつながる重要なメリットです。
参考記事:予知保全とは?予防保全や予兆保全との違い、メリットを解説<導入事例付>
知識のベータベース化による技術継承
ベテラン従業員の経験やノウハウの多くは属人的に管理され、ブラックボックス状態になりがちです。DXを進めることで、これらの暗黙知をデジタルツールを活用して「見える化」できます。
たとえば、作業手順を動画やモーションキャプチャで記録し、誰でも同じ手順を再現できるようにすれば、見て覚えるより技術継承がしやすくなります。また、トラブル対応事例や改善履歴などを蓄積することで、現場での良否判断もしやすくなります。作業者が変わっても同じ基準で再発防止でき、品質の安定化につながります。
このように、知識をデータベース化していくことで、世代交代が加速する中でも継続的に技術力を維持できるようになります。
非熟練者の即戦力化
これまで製造業では、新人や非熟練者が戦力となるまでに長い訓練期間を要していました。DXを活用すれば、作業手順のデジタル化などにより、短期間で作業に習熟できる環境が整います。
例として、作業指示や品質管理をデジタル化し、新人作業者でも手順を見ながら作業できる体制を作れば、早期に現場で活躍できるようになります。また、リアルタイムでフィードバックできるシステムを導入すれば、さらに早く作業を習得できる環境が整います。
こうした支援により、未経験者であってもすぐに現場で活躍できるようになり、人材育成にかかる負荷を軽減します。
採用競争力の向上
DXを推進し、最新のデジタルツールを活用している職場環境を整備することで、若い世代にも魅力的な職場としてアピールできるようになります。
具体例は、紙ベースの作業報告を廃止してタブレット入力に変更したり、AIによる工程改善に取り組んでいることを採用時に伝える等です。「時代に合った企業」「働きやすい」といった印象を持ってもらうことで、結果として、優秀な人材の確保につながります。
労働環境向上による離職率低下
DXは業務の効率化だけでなく、従業員の働きやすさを高める効果もあります。たとえば、作業負荷の高い業務を自動化することで肉体的負担が軽減されます。ほかにも、紙の作業のデジタル化により、事務作業の手間も削減されます。
また、DX化を進めるITツールには、労働時間の見える化に効果があるものもあります(工程管理システムなど)。労働時間が明確になると、労働時間の適正管理が可能となり、サービス残業の防止にも貢献します。さらに、作業環境の快適化や安全管理システムの導入によって、事故やヒューマンエラーのリスクも低減します。こうした取り組みをすることで、従業員の満足度向上と定着率の改善につながり、離職率の低下に寄与します。
データ活用による意思決定の迅速化
製造業において、日々発生する膨大な現場データを活用することが、迅速かつ的確な意思決定をする上で重要となります。データに基づく意思決定は、人の勘や経験に頼らない客観的な判断が可能となり、経営判断ミスを減らすことも期待できます。
例えば、DXによって生産状況をリアルタイムで監視できるようになれば、異常の早期発見や工程のボトルネックの特定が容易になります。適切な処置の判断も迅速に可能で、ライン停止などの重大な異常を未然に防ぐ事ができます。
また、各製造工程における生産状況の確認、在庫状況を見える化することで、突発的な製造依頼にもすぐに対処できるようになります。また、AIを用いて将来の需要予測を行うことで、精度の高い生産計画や材料調達につながります。
まずはデジタルツールを「小さく」導入し始めることが重要
製造業のデジタル化は、一気に大規模なシステムを導入すると失敗しやすくなります。まずは「小さく」導入し始めることが、DX成功の鍵です。
大規模なシステムをいきなり入れると、業務の進め方も大きく変わり、現場の負荷が大きくなります。運用に慣れる助走期間が不十分だとミスも発生しやすく、最悪の場合「システムが使いにくい」と現場で活用されなくなるケースもあります。少しずつデジタルツールを取り入れれば、少しずつ運用を変えていくため現場への負荷が少なくなります。また、業務効率が徐々に改善され、着実に成果を感じることができます。
近年では、中小企業でも手軽に導入できるデジタルツールやクラウドサービスが増えており、これらを利用することで、業務の効率化を目指す企業が増えてきています。企業規模に応じて適切なツールを選ぶことで、無理なくデジタル化が進みます。
低リスクでシステム導入するならクラウド型

小さく導入できるシステムの形態の代表は、クラウド型のシステムです。以下の点から、システム導入リスクを抑えたい企業や、大規模なシステム導入が難しい中小製造業にも向いています。
■クラウド型システムのメリット
- 初期費用も抑えて導入できる
- 必要なときにスケールアップできる
- システムに不慣れな現場作業員が多い場合も、少しずつ慣れることができる
- システムの運用・メンテナンスを自社で行う必要がない(IT専任担当がいなくても運用しやすい)
コスト・リスクを双方抑えて導入できるクラウド型の製造業向けシステムは、近年増加しています。中小企業でも手軽にデジタル化を進められるようになりつつあり、人手不足解消の手助けとなります。
参考:生産管理システムのクラウド型とは|特徴と製品選定のポイント
クラウド型生産管理システムでの課題解決事例

現場向けシステムの中でも、特に導入効果を感じやすいものの一つが生産管理システムです。クラウド型の生産管理システムを導入することで、製造業の現場で発生しているさまざまな課題を解決する事例が増えています。以下では、実際の課題解決事例をいくつかご紹介します。
手書き・エクセル業務をなくし1人分の省人効果を得た例
成形品製造企業では、手書きで記録した作業日報をエクセルに打ち込み管理していました。製造工程が長くなれば、日報の枚数や項目が多くなり、まとめるために膨大な時間と労力がかかっていました。クラウド型生産管理システムを導入することで、月間約100時間の時間削減と省人化を実現しました。
事例の詳細はこちら:手書き&エクセル入力がゼロに。1人の省人効果+迅速な生産調整で生産性向上
経験則に頼らないピッキング作業を実現した例
組立品製造企業では、在庫確認を必要に応じて電話で確認しており、手間がかかる上に正確性に欠ける状態でした。また、倉庫内のピッキング作業は従業員の記憶に頼る部分が大きく、まれにミスが発生していました。クラウド型生産管理システムを導入することで、在庫管理をリアルタイムでできるようになりました。また、ピッキング作業もハンディターミナルを用いることで、ミスなく効率的にできるようになりました。
事例の詳細はこちら:在庫管理の一元化と属人化の課題を一挙に解決!ミスほぼゼロで顧客満足度向上
棚卸工数の削減で現場作業員の負荷を減らした例
化粧品製造企業では、原料取り違え・誤投入による損失額が年間数千万円に及んでいました。また、半期決算の棚卸しでは、工場を全停止させた連休中に1チーム3人体制で4、5日かけて行っており、現場の負荷が大きい状況でした。生産管理システムを導入することで原料の取り違え・誤投入が無くなり、これらが原因の損失額が0になりました。工場を全停止させない循環棚卸も可能となり、現場の負荷を大きく削減しました。
事例の詳細はこちら:誤使用・誤投入0件、年間損失額の数千万円が0円に!ハンディ端末で工数削減・属人化解消も成功
1人しかできなかった発注業務の分担を実現した例
医療・医薬品製造企業では、原料の発注時にエクセルで作成した生産計画から将来在庫数を計算する作業が必要でした。クラウド型システムを導入し、生産計画データをシステムに取り込むことで、将来在庫を自動計算する運用を実現しました。その結果、発注業務がシステム上で一元管理されるようになり、これまで属人化していた発注業務が複数人で分担できるようになりました。
事例の詳細はこちら:将来在庫の自動計算で発注の負担・工数を削減!生産計画と在庫を紐づける管理を実現
22種類の生産管理システムをランキングで比較
初期費用相場や選び方のポイントをチェック
生産管理システムをそれぞれの特徴や初期費用相場などで比較したい場合は、「生産管理システムランキング」も是非ご覧ください。生産管理システムは、自社の製品・生産方式・企業規模などに適したものを導入しないと、得られるメリットが限定されてしまいます。事前適合性チェックや生産管理システムを選ぶ前に押さえておきたいポイントも解説していますので、製品選びの参考にしてみてください。


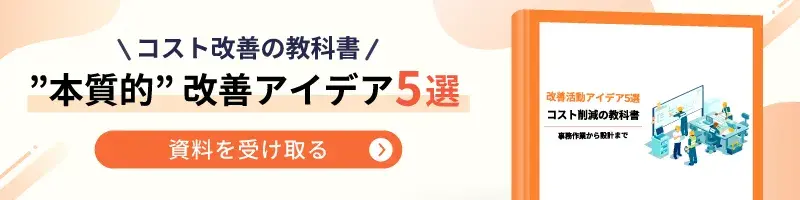



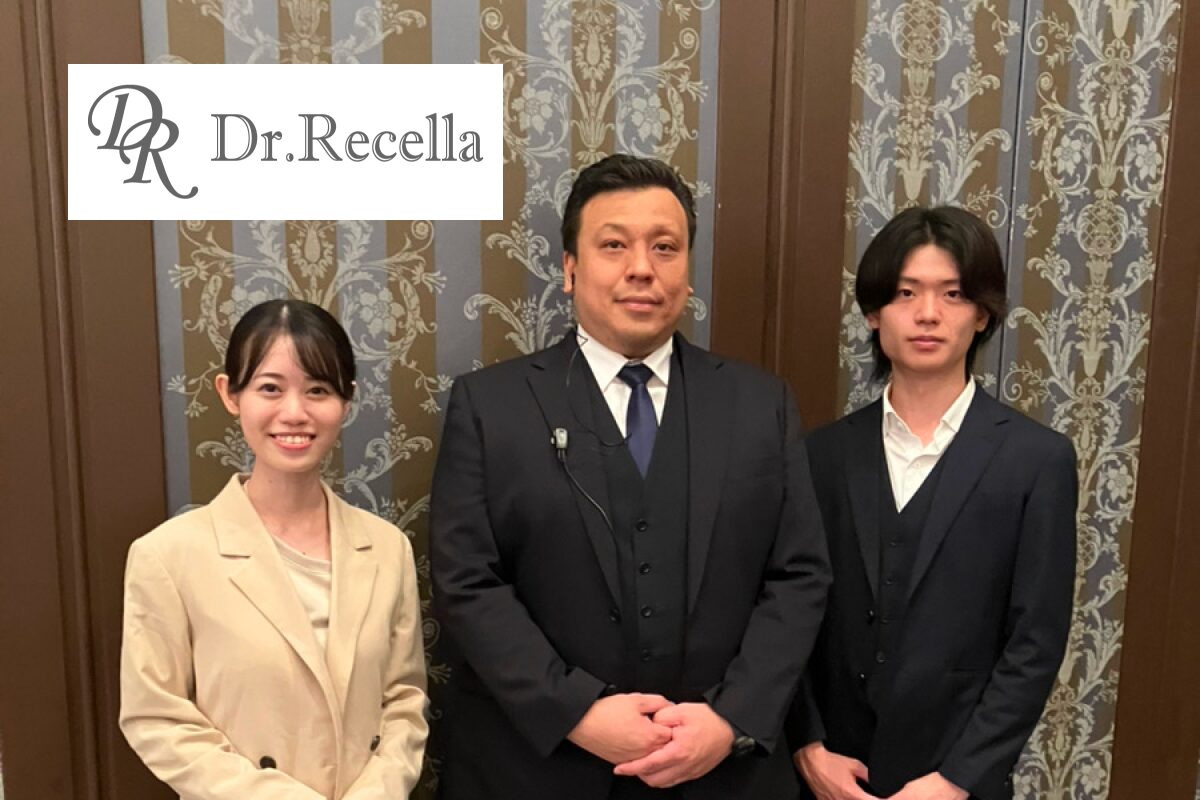
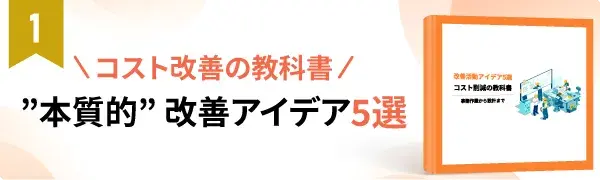









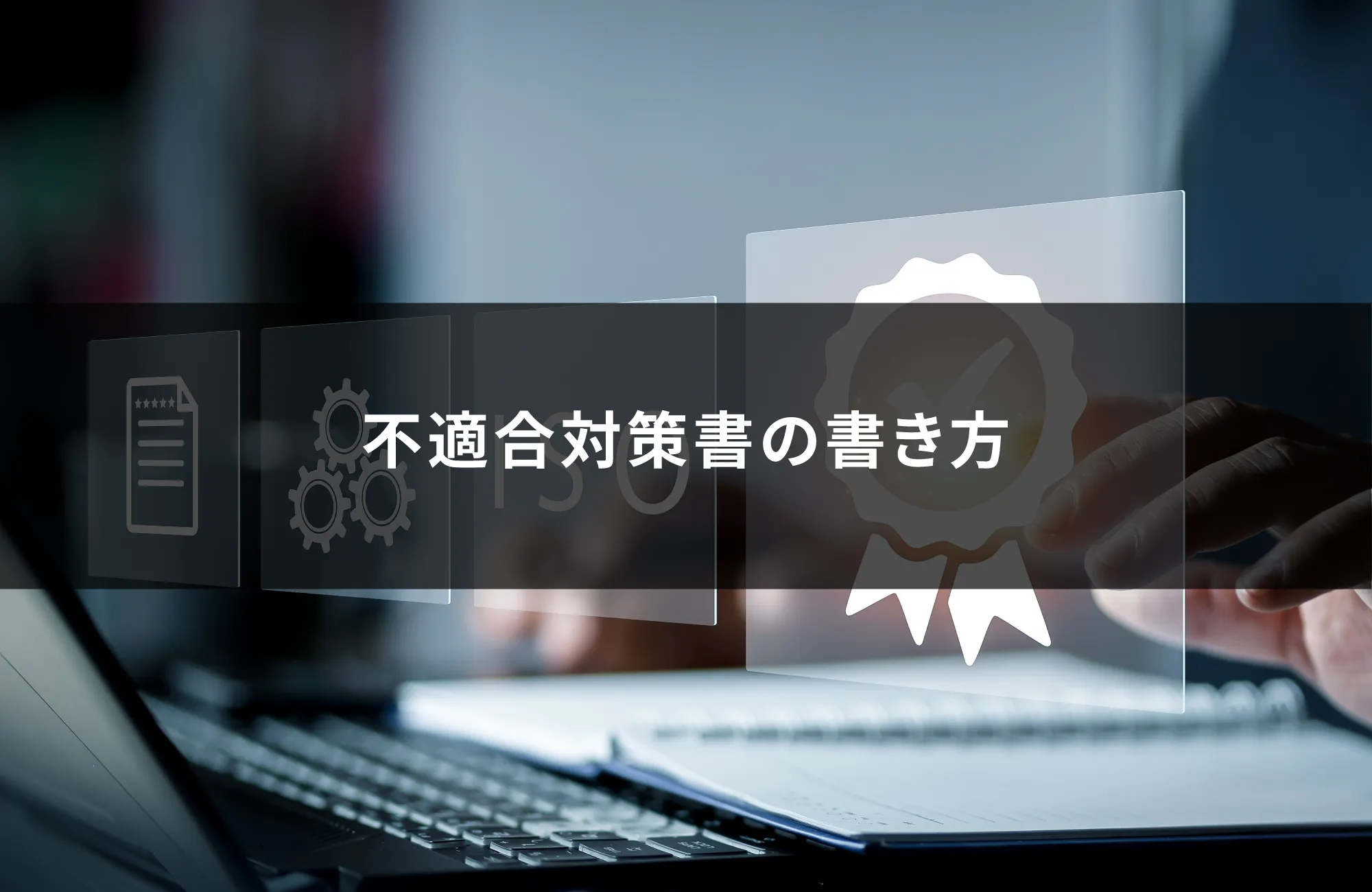





.jpg)









