製番管理とは?MRPとの違いをメリット・デメリット比較で解説 システム化に成功した事例も紹介
公開日:2023年09月20日
最終更新日:2025年02月01日

製番管理とは、受注案件ごとに「製番」を割り振り、部品や工程を製番に紐づけて管理する方法です。多品種少量生産や個別受注生産向きで、古くから多くの中小・中堅企業で活用されてきました。量産向けのMRPとは、対象的な印象を持っている人もいるかもしれません。
従来、小規模な製造企業では、紙やエクセルによる製番管理が一般的でした。しかし、近年は多品種少量生産のニーズが高まり続け、生産管理システムによる工数削減を行う企業も増えてきました。
本記事では、製番管理とMRP、その他の類似用語(ロット管理・シリアル管理・追番管理)との違いを解説します。後半には、生産管理システムによる工数削減の成功事例を紹介します。
製番管理とは?
製番管理とは、受注(オーダー)ごとに「製番(製品番号)」という一意の番号やコードを割り当て、製品情報を一元管理する仕組みです。受注案件ごとに製番を振り、各工程や材料などをすべて製番に紐づけて生産計画や在庫の情報を管理するため、トレーサビリティを確保しやすい管理方式です。主に、多品種少量生産や個別受注生産に用いられます。
製番管理とMRPの違いを比較:効果的な使い分け方は?
製番管理と対象的な生産管理手法に、MRP(資材所要量計画)があります。これらは対象的な特徴があり、向いている生産方式が異なります。MRPと製番管理を比較すると、それぞれのメリット・デメリットがよくわかります。
| MRP(資材所要量計画) | 製番管理 | |
| 向いている生産方式 | 見込み生産(量産品など) | 個別受注生産(多品種少量品など) |
| 管理方法 | 需要予測に基づく生産計画・在庫情報・BOMから部品の所要量や手配タイミングを計画 | 受注ごとに製番を付与し、製番ごとに工程や部品を手配・管理 |
| 在庫管理・発注管理 | 共通品番の部品は、複数生産での使用(引当)やまとめ発注が可能 | 製番ごとに必要な部品のみ発注 |
| メリット | ・スケールメリットで発注単価を下げやすい・製造リードタイムを短縮しやすい | ・複雑な在庫管理が不要・製造原価が把握しやすい・トレーサビリティの確保が容易 |
| デメリット | ・需要予測や複雑な在庫管理が必要 ・原価管理やトレーサビリティ確保の難易度が高い | ・発注ロットが少ないため、製造原価は上がりやすい ・受注後に部品手配をするため製造リードタイムは長くなりやすい |
MRPのメリット・デメリット
MRPは、需要予測をもとに前もって資材発注を行うため、見込み生産に向いています。共通部品はまとめて発注するため、ボリュームディスカウントを受けられる可能性が上がり、発注単価を抑えやすい管理方法です。生産計画に合わせてタイミングよく発注資材が届くようにコントロールできれば、製造リードタイムを短縮できるメリットもあります。
しかし、需要予測が外れると在庫の過不足が起きやすく、在庫管理や原価管理の難易度が高いというデメリットもあります。例えば、ある部品を3種類の異なる製品向けに使用している場合、3製品いずれの生産計画にも足りる数量・タイミングを予測し、発注する必要があります。需要変動が起きた場合、うまくリカバリーできないと過剰在庫や欠品になりかねません。さらに、もし発注時期や数量によって単価が異なる資材があれば、各製造ごとの製造原価の管理は非常に複雑になります。
製番管理のメリット・デメリット
対して製番管理は、受注に対して製番を付与してから、製番ごとに資材発注や工程管理を行います。製造に必要な部品は都度手配するため、在庫管理の必要もありません。製造原価の把握も簡単なうえに、製番単位でトレーサビリティも確保できます。
ただし、受注のたびに部品を小ロット発注すると、発注単価は上がりやすくなります。また、同じ部品でも製番が異なると共有できないため、製造中のロスなどで部品が足りなくなったとしても、他製番の部品は原則使えません。部品の融通が効かないという点では、欠品や過剰在庫のリスクがあります。さらに、受注後に部品手配や製造が始まるため、製造リードタイムも長くなりがちです。
製番管理とMRPを併用するケースもある
特徴が異なる製番管理とMRPを併用する方法も、大きく分けて2パターンあります。
最も多いやり方は、製番管理をベースに、一部の汎用的な部品のみMRPで手配する方法です。例えば、金属加工・組立品などの業界では、ボルト・ナット・ワッシャーなどを共通部品として在庫しつつ、基本は製番管理による受注生産を行うケースがよくあります。
もう1つは、厳格なトレーサビリティを求められる客先向けのみ製番管理を行い、それ以外はMRPによる管理をする方法です。代表的な例は、官公庁向けのみ製番管理を行うケースです。
その他の用語との違い
他にも、製番管理と混同しやすい用語があるので、それぞれの違いを解説します。
製番管理とロット管理の違い
製番管理が受注単位に製番を付与するのに対し、ロット管理では製造ロットごとにロットを付与し、トレーサビリティを確保します。製造ロットが同じ=同じ条件下で作られ品質も同等だという考えで、ロット単位で品質管理するイメージです。
例えば、製品Aを100個、1件の注文として受注したとします。製番管理の場合、この100個の生産に対して製番が付与されます。しかし、製品Aの最小製造ロットが300個であれば、この300個に対してロット番号を付与します。先に出荷した100個も、残りの製品在庫200個も、ロット番号は同じです。
ロット生産も製番管理と同じく、多品種少量生産に向いている生産方式です。製番管理との一番の違いは、受注生産だけでなく見込み生産にも活用できる点です。
参考:ロット管理とは メリットや導入方法、トレーサビリティのためのシステム導入も解説
製番管理とシリアル管理の違い
製番管理より、さらに厳密にトレーサビリティを行う方法がシリアル管理です。シリアル管理では、製品1つ1つに対してシリアル番号(固有番号)を採番します。
例えば、製品Bを100個作る場合、製番管理では100個に対して同じ製番を振ります。しかし、シリアル管理だと、100個すべてが異なるシリアル番号を持つことになります。
シリアル管理を活用している製造業の代表例は、自動車です。自動車には国際規格のVINコード(車台番号)と呼ばれるシリアル番号が付与されており、リコール対象となる自動車の特定ができる仕組みとなっています。
製番管理と追番管理の違い
製番管理と似た言葉で、追番管理という管理手法がありますが、製番管理とは全く異なるものです。
追番管理とは、製品の生産計画数・生産実績数の累計数を「追番」とし、日々の生産進捗を管理する手法です。
例えば、毎営業日100個ずつ製造する予定の製品があるとします。日々の完成数だけを見ていると、予定より遅れている日もあれば、予定より多く作れた日もあるように見えます。しかし、追番管理にて生産計画・製造実績数を「累積」で見ていくことで、日々の進捗を把握しやすくなります。
以下のようなグラフにすると、より進捗が見えやすくなります。
製番管理は紙とエクセルで十分なのか?
製番管理は、日本で古くからあるシンプルな管理手法です。そのため、個別受注生産のみ行う、生産数が少ない中小企業であれば、紙とエクセルでも管理できる可能性はあります。
しかし、近年は顧客ニーズが複雑化し、さらに多品種少量生産を求められる傾向にあります。その中で競争力を付けていくには、より付加価値の高い製品を生み出したり、管理工数を圧縮したりする必要があります。
一般的に、生産管理工数の圧縮には「生産管理システム」が役立つと言われています。しかし、製番管理中心の企業の場合は、製番管理に対応可能かどうか、導入実績があるかを確認する必要があります。なぜなら、多くの生産管理システムは、初めに製品や部品の「品番マスタ」を作る必要があるためです。受注のたびに品番が変わる製番管理には、この使い方しかできない生産管理システムはフィットしません。
しかし、製番管理に対応できる生産管理システムを導入すれば、管理工数を大きく圧縮できる可能性があります。
生産管理システムで製番管理の工数削減を実現した事例

ある企業では、通常品として使用する標準品以外は在庫せず、受注案件単位で部品調達していました。この管理をエクセルで行っていました。
しかし、リードタイムが長い海外品では、複数案件の部品をまとめて発注しなければならない場合もあり、複雑な案件管理が必要でした。取扱品目が増えるにつれて工数がさらに膨らみ、システム化の検討を始めました。
大手ERPパッケージから安価な在庫管理システムまで、幅広く検討したものの、「初めに品番マスタを作り、都度手作業で品番を直す必要がある」と言われていました。それでは工数削減は見込めないと、見送りが続いていました。
そんな中、受注のたびに自社で作成していたBOMデータと、連携して使える生産管理システムを発見。品番マスタを都度作る必要なく、今までの運用を残したまま、システム管理を実現しました。
詳細はこちら:
脱・複雑で属人的なエクセル在庫管理!受注案件単位の在庫管理はそのままに、業務標準化や工数削減、ミス削減まで実現
22種類の生産管理システムをランキングで比較
初期費用相場や選び方のポイントをチェック
生産管理システムをそれぞれの特徴や初期費用相場などで比較したい場合は、「生産管理システムランキング」も是非ご覧ください。生産管理システムは、自社の製品・生産方式・企業規模などに適したものを導入しないと、得られるメリットが限定されてしまいます。事前適合性チェックや生産管理システムを選ぶ前に押さえておきたいポイントも解説していますので、製品選びの参考にしてみてください。



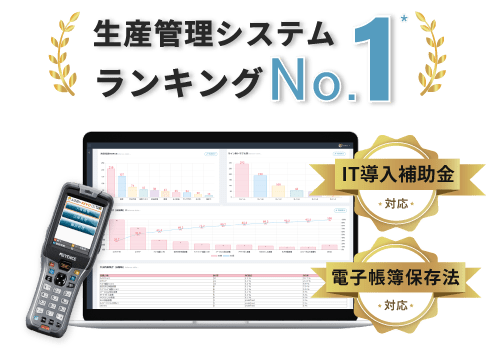





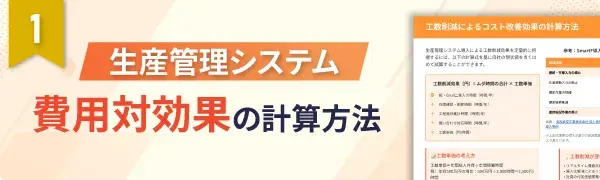






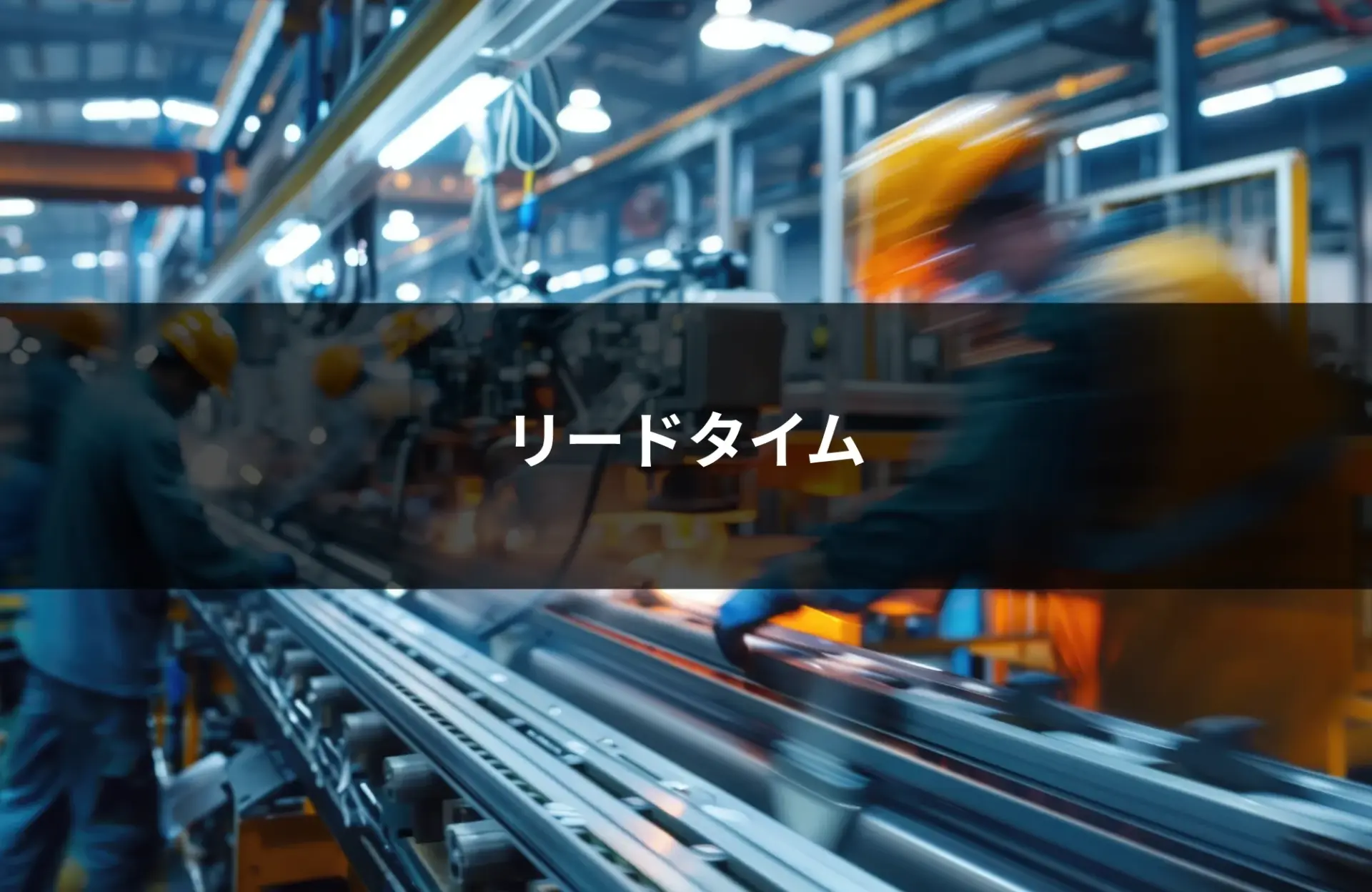


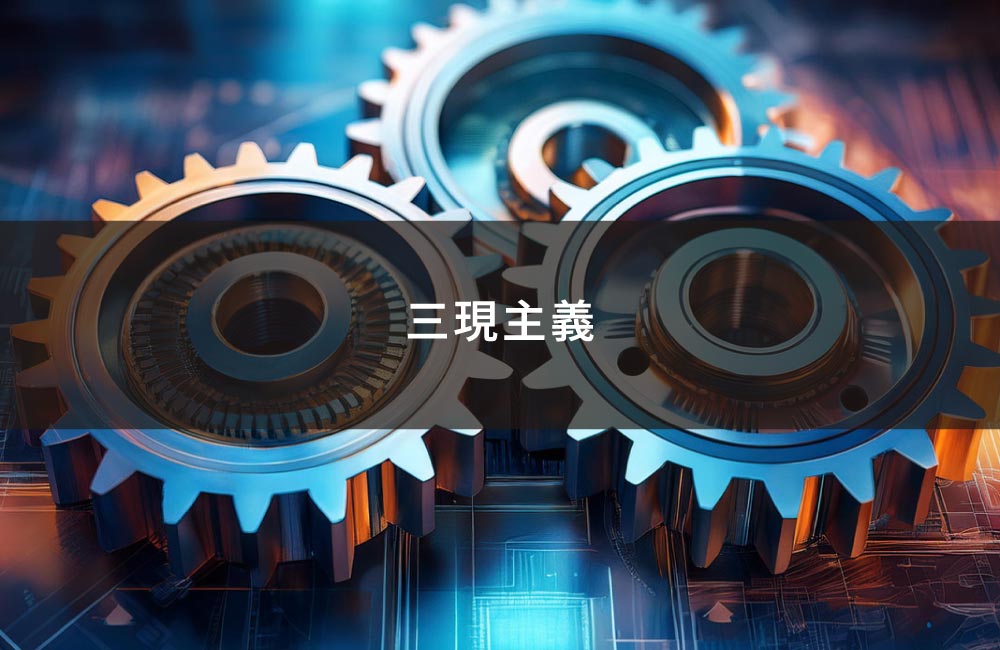
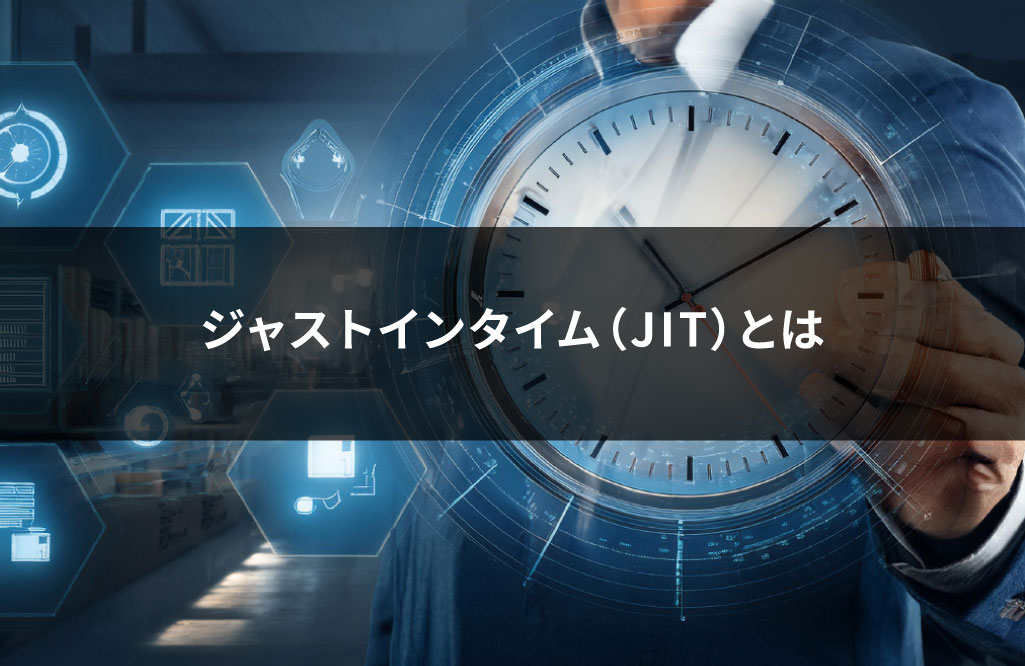







.jpg)











