バーコード管理×生産管理の費用対効果とは デメリット克服方法・成功事例まで解説
公開日:2023年04月03日
最終更新日:2025年05月12日

バーコード管理を導入すると、生産管理の紙・エクセル業務をなくし、ミス・工数の削減、属人化の解消などが期待できます。事前に、導入手順やバーコード管理のデメリットの回避策も知っておくと、失敗せずに導入できます。
当記事では、バーコード管理の重要性やQRコード・RFIDとの違い、費用対効果(ROI)のシミュレーション例まで解説します。導入検討に必要な、投資回収目安や成功事例まで紹介していますので、参考にしていただけると幸いです。
バーコード管理の仕組み
バーコードとは、バーとスペースの組み合わせによって数字や文字を表現したものです。ハンディターミナルやバーコードリーダーなどのスキャナ(光学認識装置)を使い、中身の情報を読み取ることができます。
ちなみにバーコードには、一次元バーコードと二次元バーコードがあります。一般的に「バーコード」と聞いて思い浮かべる、ストライプ柄のものは一次元バーコードです。
二次元バーコードは、QRコードとも呼ばれるものです。水平方向と垂直方向にデータを持っているため、二次元バーコードと呼びます。
当記事では、バーコード管理の重要性やQRコード・RFIDとの違い、費用対効果(ROI)のシミュレーション例まで解説します。導入検討に必要な、投資回収目安や成功事例まで紹介していますので、参考にしていただけると幸いです。
生産管理でなぜバーコードを活用すべきなのか?

バーコード管理は、「在庫が合わない」「工程進捗が見えない」といった現場の悩みを、最小投資で改善できる施策です。
生産管理では、最適な品質・原価・納期でものづくりが行われるように製造現場を管理します。その過程で膨大な記録業務が発生し、紙帳票への手書きやエクセルへの手入力だと現場負担が非常に大きくなります。実際に、記録漏れやミスが頻繁に発生し、正しく管理できないと悩んでいる企業は少なくありません。
これらの手書きや手入力の業務をバーコードに置き換えると、大幅な工数削減が期待できます。
生産現場を取り巻くDXトレンドとバーコード再評価
バーコード管理は、製造業DXが必要視される中で、低コスト・高精度・短期導入という強みが再評価されてきています。
昨今では、多品種少量生産や品質要求の高まりに伴って、より高度な生産管理が求められています。製造現場での記録業務も、増加傾向にあります。今まで紙やエクセルで生産管理を行えていた中小・中堅規模の企業でも、限界を感じている方は多いでしょう。
しかし、初のDXの試みをする中で、予算が限られている企業も少なくありません。バーコード管理は安価に導入でき、シンプルでわかりやすい仕組みです。この点から、初めてIoTツールを使う企業にとって、DXの入口として再び注目されています。
バーコード管理の主な用途
製造業の生産管理業務において、バーコード管理の用途は主に以下5通りです。
- 入荷・受入検査:検品後に社内品番のバーコードラベルを貼付
- 入出庫・在庫移動の登録:製造現場への払い出しなどの移動を登録
- 完成品の在庫管理・出荷管理:完成品ラベルでトレーサビリティ・出荷管理
- 棚卸し:ハンディ端末によっては棚差を現場で修正
- 作業日報デジタル化:作業の開始・終了登録で工数集計
バーコードと他技術の比較
バーコードと比較されることが多いIoTツールに、QRコードとRFIDがあります。それぞれの特徴を比べると、以下のとおりです。
| 技術 | コスト | 読取距離 | データ量 | 特徴 |
| バーコード(一次元バーコード) | 低 | 2〜30 cm | 数十桁 | 接触型・安価・汎用 |
| QRコード(二次元バーコード) | 低~中 | 2〜30 cm | 数百文字 | 接触型・部品小型・多情報 |
| RFID | 高 | 0.1〜5 m | 数千文字 | 非接触・一括読取 |
バーコード管理は、最も低コストに導入できるIoTツールの一つです。扱えるデータ量は少ないものの、初めてのIoTツールの導入としては十分活用できます。より多くのデータを扱う場合は、QRコードがおすすめです。
対してRFID技術は、非接触で複数のデータを読み取れることが特徴です。わかりやすい例は、ユニクロの無人レジです。従来は商品バーコードを1点ずつスキャンしていましたが、全商品にRFIDタグを付け、カゴ内の商品の一括読み取りを可能にしました。導入費用が高価なこともあり、扱う点数が多い小売業界などで先行して普及しつつあります。
生産管理でバーコードを活用するメリット

生産管理でバーコードを活用するメリットは、記録業務の手間を軽減できるだけではありません。さらに以下3点のメリットがあります。
ヒューマンエラー・属人化を防止できる
バーコードの真価は、“誰でも・同じ手順で” データを拾える再現性にあります。わずかなスキャン動作で、作業者依存だった紙運用がルール化・自動化され、業務全体の標準化が進みます。
手書きや手入力での記録には、書き間違いなどのヒューマンエラーが発生しやすいという課題があります。しかし、バーコードを活用すれば人の手で記録する情報が少なくなり、ューマンエラーの発生を抑えられます。
また、バーコードの読み取り時にエラーチェックができる点も、バーコードを活用する大きなメリットです。
バーコードによるエラーチェック例
- 誤出荷防止:出荷時に間違った製品のバーコードを読み取るとエラーを出す
- 原材料の誤使用防止:生産時に間違った部品や期限切れの原材料を使おうとするとエラーを出す
転記や集計の手間がなくなる
バーコード管理は、データの読み取りだけでなくデータ入力にも活用できます。手書きや手入力の作業を、生産管理システムなどと連携したバーコード管理に置き換えると、転記や集計の手間をゼロにできます。
紙の帳票に記録した情報を活用するには、後でエクセルやシステムに転記したり、集計したりする必要があります。作業者の人数や作業量が多いと転記・集計に相当な工数がかかり、担当者の工数を圧迫しがちです。
バーコードを活用してシステム上に直接記録できる仕組みを構築すれば、転記・集計もシステム上で自動化できます。浮いた工数をより付加価値の高い業務に割り当てることで、製造現場全体の生産性向上が期待できます。
バーコードによるデータ入力例
- 作業日報のデジタル化:製造指示番号や品番、工程情報などが含まれたバーコードを事前発行→その工程が完了したらバーコードスキャンで生産実績を記録→システム上で工数を自動集計
リアルタイムに情報を反映できる
バーコードで読み取った情報は、連携しているシステムに即時反映されます。このリアルタイム性も、バーコード管理のメリットです。
最適な生産管理を行うためには、製造現場の状況をリアルタイムに把握する必要があります。生産実績や在庫情報を紙やエクセルに記録していると、確認したい情報を見つけるまで時間がかかり、対応が遅くなるリスクがあります。不具合発生時や欠品時など、スピード対応が求められる場面では大きな負荷になります。
バーコード管理でリアルタイムな生産情報の反映を実現すれば、必要な情報を即座に確認し、状況に応じた適切な対応ができるようになります。
バーコード管理のリアルタイム性が活きる例
- 在庫の入出庫記録:各品番ごとのバーコードで入出庫情報を更新し、常に最新の在庫情報を確認→正確な発注による欠品防止
- 工程進捗管理:各作業の開始・終了をバーコードで登録し、工場全体の工程進捗を見える化→納期遅延の防止
バーコード管理のコスト削減効果と投資回収シミュレーション

前述の通り、バーコード管理の導入コストはIoTツールの中でも、比較的安価です。そのため、1年以内に投資回収できる企業も多くあります。
以下に、コスト削減効果と想定回収期間の例をまとめました。中小〜中堅規模の工場で、初期費用をなるべく抑える想定で導入した場合をシミュレーションしています。
| 投資項目 | 概算費用 | 効果例 | 想定回収期間 |
| ハンディ端末×1~10台 | 約20万円 | 棚卸時間▲75% | 5 〜 6か月 |
| ラベルプリンター×1台 | 約15万円 | 誤出荷▲90% | 7~8か月 |
バーコード管理の導入事例では、棚卸工数50〜90%削減の成功例が多くあります。仮に、半期棚卸に6人x3営業日の工数をかける企業が、75%の工数削減を実現すると、1年で216時間の工数削減となります。これを製造現場の平均的な総労務費2000円で換算すると、半年ほどでハンディ端末の導入費をペイできる計算となります。
また、バーコードを印刷するラベルプリンターも同時導入すると、誤出荷防止の効果も期待できます。一例として、週1回ペースで誤出荷が起き、再送や再製作対応で1回5000円のコストが発生していたとします。それらを90%削減できれば、7〜8ヶ月で導入費用を回収できます。より高単価な製品を扱っている企業だと、さらに早くペイできます。
バーコード活用が効果的なパターン
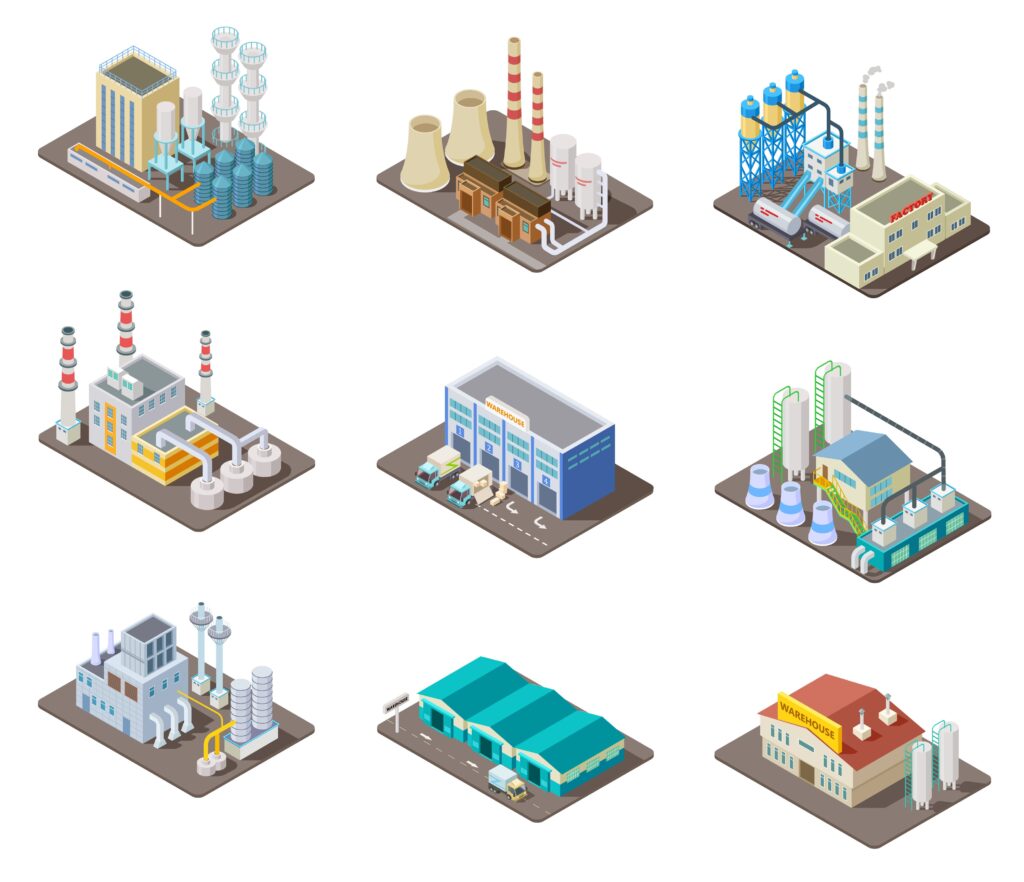
バーコードの活用は多くの製造現場で効果的ですが、以下のような業界や業種の生産管理では、特に大きなメリットが出やすくなります。
品質管理を徹底してトレーサビリティを確保したい
ロットトレースなどの品質管理に厳しい業界では、バーコード管理によるミスのない生産管理の実現はメリットが大きいと言えます。
食品・医薬品・化粧品などの業界では、適正な品質を確保するために厳しい品質管理が求められます。たとえば、有効期限切れの原材料を誤使用しないよう、厳重にチェックする必要があります。しかし、ヒューマンエラーによって不良品が発生してしまい、大きな損失がでるケースは少なくありません。
また、どの製品にどの原材料を使用しているのかをトレースするためにロット管理を行う必要がありますが、人の手による記録では手間やミスが発生しがちです。
バーコードを活用すれば、事前にロットや有効期限などの情報が含まれたバーコードラベルを発行し、記録やエラーチェックを行えます。人の手で行うよりもはるかに早く、ミスもなくなるため、品質向上に役立つでしょう。
上述した3つの業界以外にも、自動車、化学品、電子機器などのさまざまな業界でトレーサビリティは求められています。製造業の品質管理体制を強化する上で、バーコードの活用は欠かせません。
原価管理に取り組んで利益率を向上させたい
バーコード管理で実工数と材料ロットを集計し、紐付けると、原価管理にも役立ちます。原価をリアルタイムに見える化できると、利益率向上につながります。
製造業が利益率を向上させるには、実際にかかった原価を正確に把握し、原価低減に取り組まなくてはなりません。製造原価は大きく材料費・労務費・経費の3つに分けられますが、経費以外の実績を把握するためにバーコードが役立ちます。
たとえば、原材料や部品のロットごとに発注金額を記録し、生産時のバーコードスキャンで製品のロットに紐づけておけば、その製品に使用した材料費を計算できます。また、作業開始時と終了時にバーコードを読み取り、実際にかかった工数を記録・集計すれば、その製品を作るのにかかった労務費も計算することが可能です。
原価管理は製造業の基本ではあるものの、実際に細かく管理できている企業は多くありません。しかし、バーコードを活用すれば原価管理に取り組みやすくなり、利益率の向上が期待できます。
製造現場の状況をリアルタイムに見える化したい
バーコード管理を活用すると、仕掛品を含む工程進捗が把握できるようになります。同時進行する案件が多い現場や、作業量の多い現場など、生産遅延の影響が大きい現場では、非常に役立ちます。
具体的には、自動車や食品などのライン生産が中心のメーカーや、部品点数が多い産業機器メーカー、多品種少量生産でさまざまな工程のある加工メーカーなどは、リアルタイムに現場の状況を見える化するメリットが大きいと言えます。
また、工程別や作業別の工数も詳細に把握できるため、特に工数が膨らんでいるボトルネック工程を重点的に改善すれば、リードタイム短縮や原価低減につながります。
在庫点数が多く管理の手間を軽減したい
在庫点数が多く、煩雑な在庫管理の手間を減らしたい業界や企業は、まずバーコード管理から試してみることをおすすめします。
産業機械や基板実装など、取り扱う部品点数が多いメーカーでは、管理工数も膨大になります。「どこに何の部品があるか分からない」「いつの間にか在庫がなくなっていて組立できない」など、在庫に関する課題を抱えている企業の声も多く耳にします。
バーコードを活用すれば、最小限の手間でリアルタイム入出庫記録を実現し、記録漏れやミスを削減できます。在庫のロケーション管理も行えば、倉庫内で在庫を探し回るなどのムダな工数を削減できます。
また、バーコード管理で日頃から在庫差異のない状態を作り、循環棚卸を実現した事例も多くあります。
バーコード導入前に押さえるデメリットと回避策

生産管理にてバーコード管理を導入する際は、デメリットを知り、自社で導入した際に弊害が出ないよう注意する必要があります。バーコード管理のリスクと回避策は、以下のとおりです。
| リスク | 主因 | 回避策 |
| ラベル貼付工数の増加 | 手貼り作業が増える | 工程内貼付→自動貼付機ラベル貼付不要な品物を選定する |
| ラベル破損・汚損 | 油・熱・水分 | 耐熱/耐油ラベル・保護フィルム |
| 端末故障・紛失 | 落下・粉塵 | IP65以上の防塵防滴・ストラップ使用で落下防止 |
バーコード管理の導入を200社以上支援してきた当社が、最も頻繁に受ける相談は「すべての品物にラベルを貼る負担が大きいのでは?」という内容です。
解決策の一つは、ラベル自動貼付機の導入です。より安価に対策するなら、Bluetoothなどでハンディ端末と接続できるラベラーも検討できます。たとえば、仕掛品の完成後にバーコードで完了処理をすると、自動的にラベルが印刷され、工程内で貼付しやすくなります。
生産現場へのバーコード導入の6ステップ
実際に生産管理でバーコード管理を導入する際は、以下の6ステップで進めていきます。
- 業務フローの整理・可視化:品目・ロット・工程単位でデータ粒度を定義
- データの内容やラベルの設計:載せる情報や順序・桁数、フォーマット決定
- ハード/ソフト選定:ハンディ端末・プリンター・生産管理システム
- 現場テスト:読み取り角度・距離・照度を検証
- 作業者教育:標準作業書の作成・レクチャー・トレーニング
- 効果測定&横展開:誤読率・在庫差異・棚卸時間をモニタリング
自社にIT人材がいない場合は、生産管理システムなどのソフトウェアを先に選定するという方法もあります。サポートが手厚いシステムベンダーであれば、ステップ1から一緒に取り組んでくれる可能性があります。システム選定時から、サポート体制について確認しておくと安心です。
バーコード管理の導入に失敗しないためには、まずは小さく導入することが重要です。一部の原材料や工程、拠点から導入し、運用がうまくいったら横展開していくことで、現場の負荷なく導入を進められます。
生産管理でバーコードを活用した成功事例

ここでは、生産管理においてバーコードを活用し、実際に効果を得られた企業様の事例をご紹介します。
成型品業界:工数集計の手間を年間1200時間削減
あるプラスチック成型の企業は、手書きの作業日報をエクセルに毎日集計していました。工程数が多いこともあり、集計作業には毎日4時間かかり、大きな負担となっていました。また、進捗の把握がどうしても翌日になり、リアルタイムに進捗把握できないという課題感もありました。
そこで、生産管理システムとバーコード管理を活用し、ハンディから作業進捗を登録する運用を導入しました。システム上で工程進捗がリアルタイムに見えるようになったことで、エクセルへの集計作業はゼロになりました。その結果、月間100時間の工数削減、年間に換算すると1200時間の工数を毎年削減することに成功しました。
詳しい事例はこちら:手書き&エクセル入力がゼロに。1人の省人効果+迅速な生産調整で生産性向上
化粧品業界:原料の誤使用・誤投入をなくし、年間数千万円のロスもゼロに
化粧品製造業の企業は、紙での原料管理が属人化しており、類似原料の取り違いやロットミスに課題がありました。原料の誤使用・誤投入の頻度は年5回程度ではあったものの、1回のロットアウトによる損失額は数百万円となるため、年間数千万円のロスが発生していました。
この課題を受け、バーコード管理による原料チェック・工程飛ばしチェックの運用を導入しました。その結果、原料の誤使用・誤投入はゼロになり、数千万円のロスもなくすことができました。
詳しい事例はこちら:誤使用・誤投入0件、年間損失額の数千万円が0円に!ハンディ端末で工数削減・属人化解消も成功
組立品業界:外部倉庫含めたリアルタイム在庫管理を実現
家具組み立てメーカーでは、従来エクセルで在庫管理をしており、同じ情報を別システムにも手入力しなければならない運用を行っていました。管理が煩雑なうえに、最新の在庫数を知るには現場へ口頭確認するしかなく、複数の外部倉庫の在庫確認も電話する必要がありました。
生産管理システムとバーコード管理を導入し、ハンディ端末による入出庫登録を始めてからは、リアルタイムに在庫管理ができています。外部倉庫の在庫数もシステム上ですぐに把握できるため、生産計画や発注計画の精緻化に繋がりました。
詳しい事例はこちら:在庫管理の一元化と属人化の課題を一挙に解決!ミスほぼゼロで顧客満足度向上
22種類の生産管理システムをランキングで比較
初期費用相場や選び方のポイントをチェック
生産管理システムをそれぞれの特徴や初期費用相場などで比較したい場合は、「生産管理システムランキング」も是非ご覧ください。生産管理システムは、自社の製品・生産方式・企業規模などに適したものを導入しないと、得られるメリットが限定されてしまいます。事前適合性チェックや生産管理システムを選ぶ前に押さえておきたいポイントも解説していますので、製品選びの参考にしてみてください。



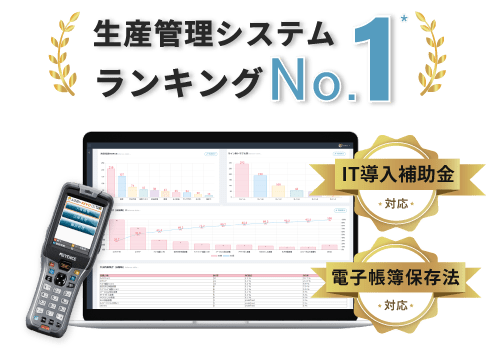





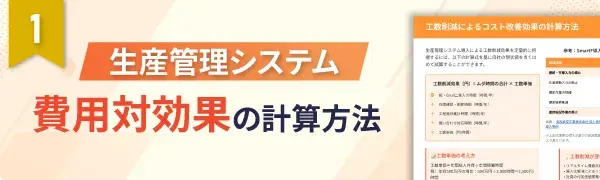






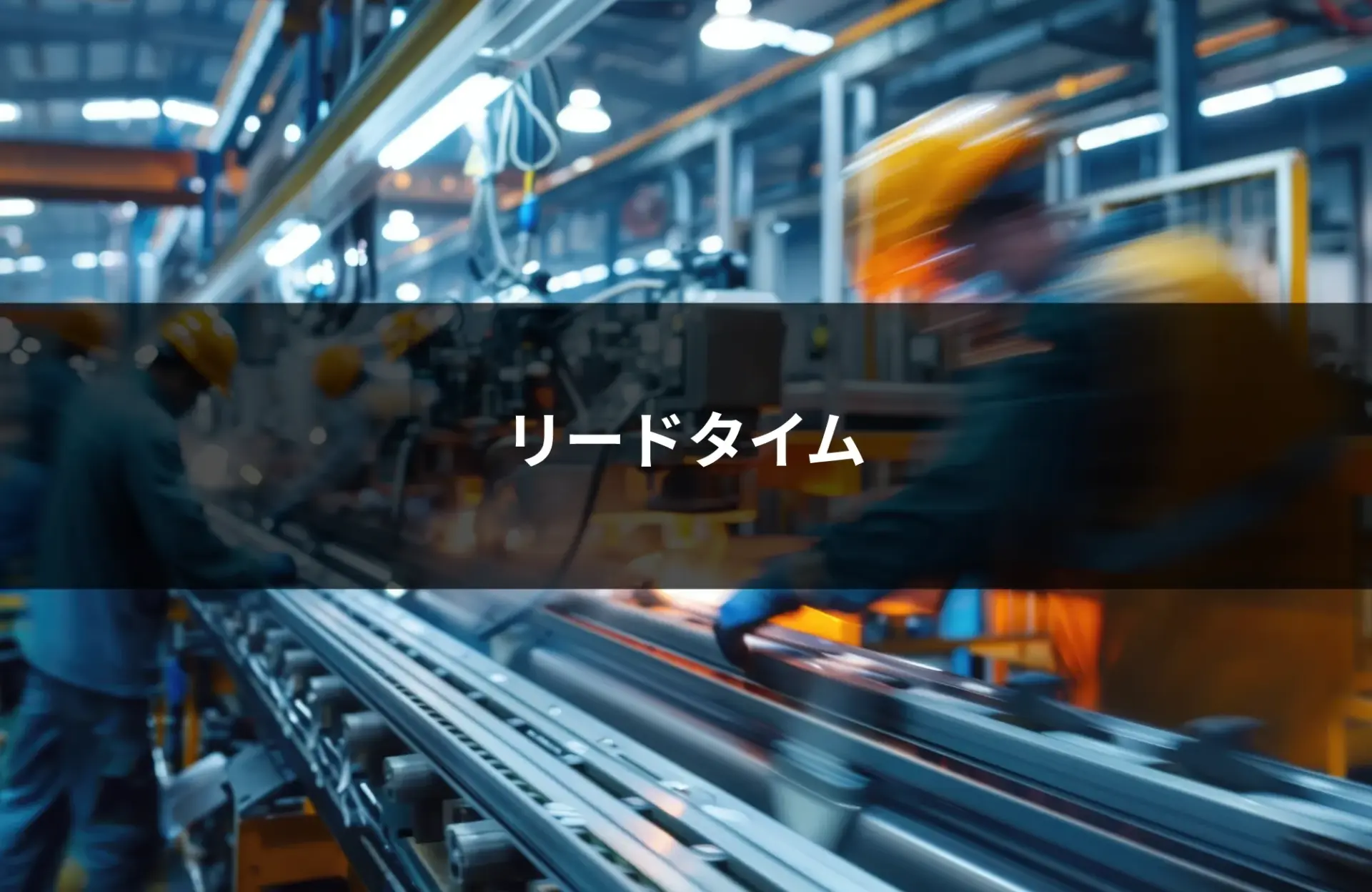


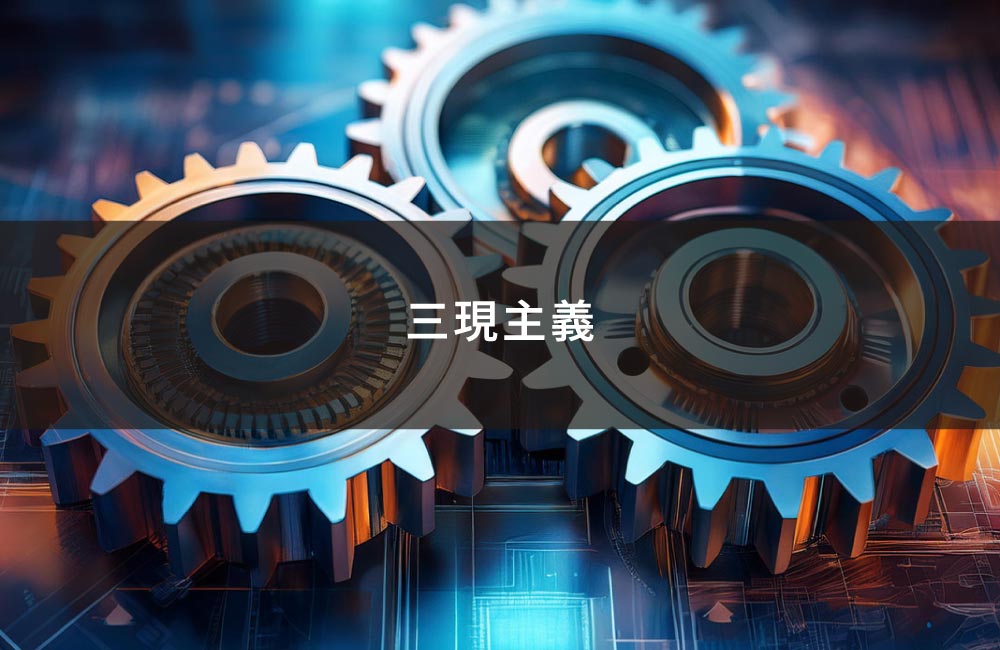
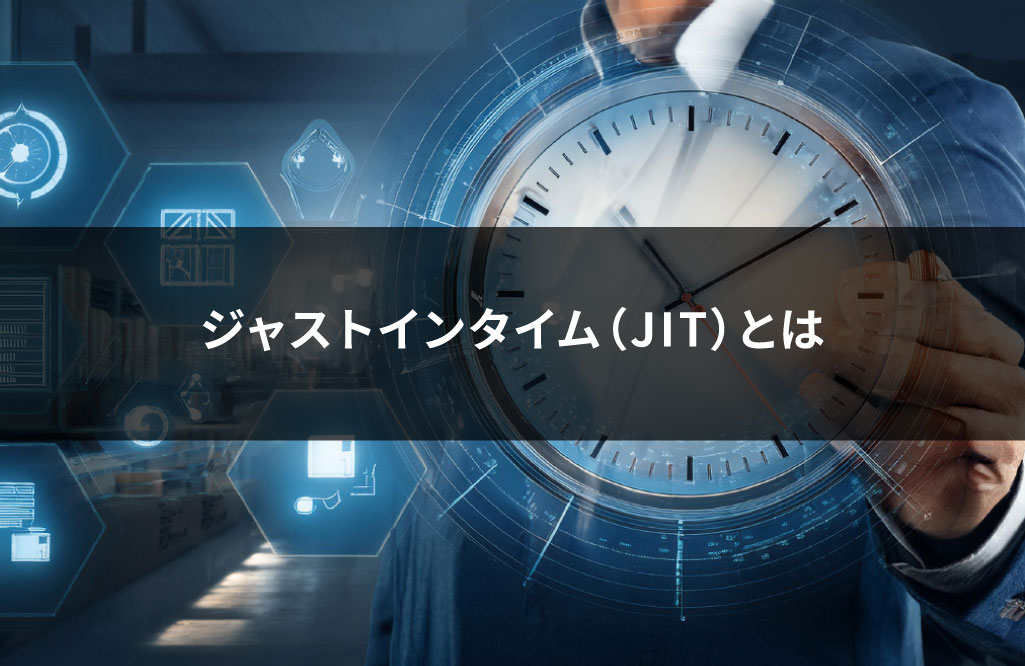







.jpg)











