稼働監視とは?現場のメリット、システム導入コストや失敗しない選び方を解説
公開日:2020年04月17日
最終更新日:2025年03月10日

生産設備の稼働監視を行うと、設備の停止やムダを減らし、生産性を最大化できます。さらに、稼働監視システムによるIoTモニタリングを導入すれば、設備の状態をリアルタイムで把握でき、トラブルの予兆検知やデータ分析も可能になります。
しかし、規模が小さい工場など、設備の監視までする必要があるか悩む企業もあるかと思います。本記事では、稼働監視の仕組みやメリット、導入すべき工場の特徴にくわえ、システム導入の選び方やコスト・効果性まで詳しく解説します。
稼働監視とは
稼働監視とは、生産設備や空調機の稼働データを収集し、稼働状況や稼働率を見える化することです。例えば、工場の設備が正常に動いているか、空調機やエレベーター、受電設備が問題なく運転しているかを監視します。異常が発生した際にすぐに対策を取りやすくなり、故障やトラブルを防ぐことができます。
稼働監視システムとは
稼働監視システムとは、設備の稼働状況を自動で監視するシステムです。設備を制御しているPLCやコントローラーから設備の情報を収集するほか、センサーやネットワークを活用し、設備の動作状況をリアルタイムでPCで監視します。
例えば、以下のような情報を収集・管理できます。
- 温度や振動のデータ(異常な温度上昇や振動を検知)
- 電力消費量の監視(無駄な電力使用や異常な電流を検出)
- 設備の稼働時間の記録(メンテナンスの最適化)
- 設備のトラブル履歴(過去の故障や異常の把握)
稼働監視システムを導入することで、設備の異常を早期に発見でき、無駄なコストを削減しながら、安全かつ効率的な運用が可能になります。
さらに、各設備の稼働時間や停止時間を円グラフや棒グラフで表示できる稼働監視システムもあります。視覚的に情報を見える化することで正確に把握し、ライン全体の生産状況を管理できるようになります。また、トラブル履歴が記録されるため、継続的な改善にもつなげられます。
これにより、単なる「見える化」にとどまらず、データを活用した分析や最適化も実現できます。また、近年ではAIやIoTを活用した高度な監視システムも増えており、さらなる効率化や自動化が進んでいます。
稼働監視システムの形態
稼働監視システムの形態には、オンプレミス型とクラウド型があります。メーカーや提供するサービスによって、どちらの環境に対応しているかが異なります。
オンプレミス型
自社のサーバーやネットワーク内にシステムを構築・運用する形態です。
- メリット:高いセキュリティ性、カスタマイズの自由度が高く、ネットワーク障害の影響を受けにくい
- デメリット:初期コストが高く、システムの管理・保守が必要
クラウド型
メーカーやサービス提供者のクラウド環境でシステムを運用する形態です。
- メリット:初期コストが抑えられる、導入が容易、リモート監視が可能、システムの自動更新に対応
- デメリット:インターネット環境に依存しやすい、カスタマイズ性が限定される場合がある、データのセキュリティリスクあり(※対策可能)
また、メーカーによっては、オンプレミスとクラウドの両方に対応した、ハイブリッド型のシステムを提供している場合もあります。例えば、日常的なデータはオンプレミスで管理し、長期保存データやAI分析はクラウドで活用するなど、用途に応じた柔軟な運用が可能です。
どの形態を選ぶかは、企業のセキュリティポリシーや導入コスト、運用体制、求める機能などによって決まります。
稼働監視をしていないと発生する問題

設備の稼働監視を行わないと、さまざまな問題が発生する可能性があります。ここでは、その代表的な5つの例を紹介します。
現場へ行かないと設備の稼働状態が分からない
稼働監視を行っていないと、設備が停止してもすぐに気づくことができません。そのため、確認を怠ると生産ラインが止まったまま放置されることがあります。問題を発見するためには、担当者が頻繁に現場へ確認しに行かなければならず、無駄な人件費が発生します。
停止回数や停止原因を記録できない
設備の監視をしないと設備の停止回数や原因を記録できないため、何度も同じ理由で設備が停止していることに気づきにくくなります。
その結果、適切な対策を取れず、稼働率が下がり、生産性が低下したままになります。
また、担当者がトラブル対応に追われ、通常業務に時間を割けなくなることもあります。
予期しない設備の故障による生産停止
稼働監視をしないと機械の異常を事前に把握できず、突然の故障が発生しやすくなります。その結果、修理や部品交換に時間がかかり、生産スケジュールが乱れることで納期遅れなどのリスクが増加します。
エネルギーの無駄やコスト増加
設備のモニタリングが不十分だと、設備が無駄に稼働していたり、異常な電力消費が発生していたりしても気づくことが難しくなります。その結果、電気代やメンテナンスコストが無駄に増えてしまいます。
さらに、デマンド(最大需要電力)が急激に上昇すると、契約電力を超過し、基本料金の増加につながる可能性があります。デマンドとは、一定時間内に使用された電力の最大値を指します。デマンドを適切に管理しないと、無駄なコストが発生してしまいます。
安全リスクの増大
設備の異常(振動や温度上昇など)を監視できないと、火災や事故のリスクが高まり、作業員の安全が脅かされる可能性があります。
さらに、異常に気付かずに設備を稼働し続けると、重大な故障につながり、生産ラインの停止や周囲への被害を引き起こす恐れもあります。
稼働監視システムを導入することで、これらの問題を未然に防ぎ、効率的な運用が可能になります。
稼働監視システムを導入すべき現場とは?

前述の通り、稼働監視システムは設備の稼働状況を把握し、効率化やコスト削減を実現するためのシステムです。
特に導入のメリットが大きくなるのは、以下のような現場です。
設備の台数が多い工場
多くの設備を持つ工場では、すべての設備状況を手作業で管理するのは困難です。どの設備が稼働しているのか、停止しているのかを把握する時間が膨らみ、管理者の負荷になりかねません。設備ごとの稼働率をシステムで可視化することで、ムダを減らし、効率的な運用が可能になります。
24時間稼働している工場
夜間や休日も稼働している工場では、トラブルが発生してもすぐに気づくことが難しく、対応が遅れるリスクがあります。稼働監視システムで設備の停止をリアルタイムで検知し、迅速な対応を可能にすることで、生産ロスを最小限に抑えられます。
突然の設備停止が大きな損失につながる現場
大規模なライン生産をしている工場など、設備停止による損失が大きい現場でも、システムによる稼働監視が必要でしょう。予防保全を強化し、突発的な故障防止や異常の早期発見することで、生産ライン停止による納期遅れや売上損失を防止できます。
人手不足で管理が大変な現場
作業員の巡回点検で稼働監視を行っていると、多くの時間がかかるだけでなく、トラブル発生時の対応が遅れやすくなります。また、目視確認に頼る点検作業では人的ミスをゼロにすることが難しく、点検モレによる設備トラブルのリスクもあります。
稼働監視システムを活用し、遠隔で設備の状態を監視することで、少人数でも効率的な運用が可能になります。
小さい工場でも稼働監視は必要か?
小さい工場でも、以下のような場合には稼働監視システムの導入が有効です。
- 少ない人数で複数の設備を管理している場合:監視の手間を減らし、作業負担を軽減
- 生産ロスを最小限に抑えたい場合:設備の異常をすぐに検知し、ダウンタイムを短縮
- エネルギーコストを削減したい場合:設備のムダな運転を減らし、電力消費を最適化
- これから設備を増やす予定がある場合:早めに監視体制を整え、規模が大きくなってもスムーズに管理
稼働監視システムを導入することで現場が得られるメリット

稼働監視システムを導入することで、現場の効率化と安全性の向上が期待でき、現場に大きなメリットをもたらします。具体的には、以下のことが実現できます。
設備の稼働状況が見える
稼働監視システム活用で、どの設備が稼働しているのか、どの設備が停止しているのかをリアルタイムで確認できます。これにより、無駄な設備の運転や、気づかないうちに止まっている設備を減らせます。稼働率のばらつきの原因を明確化したうえで対策を講じることで、生産性向上にも繋がります。
設備の稼働率・停止率が見える
設備の稼働時間や停止回数をデータで分析できるため、どの設備がどれだけ動いているのかを把握できます。これにより、効率の悪い設備を特定し、改善策を立てることが可能になります。
設備の異常をリアルタイムで把握できる
設備が停止した際にアラート通知が届くため、すぐに対応できます。長時間のダウンタイムを防ぎ、生産効率を向上させます。
設備の停止理由をデータで分析できる
どのような原因で設備が停止したのかを記録し、同じトラブルを繰り返さないように対策を立てることができます。これにより、設備の安定稼働が可能になります。
現場へ確認しに行く手間が減る
稼働監視システムを活用すると、設備の状態をPCやスマートフォンで確認でき、担当者が頻繁に現場を巡回する必要がなくなります。
また、最近では設置が容易なネットワークカメラ(IPカメラ)を設置し、設備の状態を映像で確認するケースも増えてきています。現場へ行くことも大切ですが、必要以上に手間を掛けずに監視できる体制を作り、業務効率を上げることも重要です。
突発的な故障を未然に防げる
センサーで温度や振動などのデータを監視し、異常の兆候を検知することで、計画的なメンテナンスや予防保全が可能になります。これにより、突然の故障による生産停止を防げます。
生産性が向上し、コスト削減につながる
設備のダウンタイムを減らし、効率的な運用ができるため、生産性が向上します。また、無駄な修理費用やエネルギー消費を削減でき、コストダウンにつながります。
作業者の安全性が向上する
稼働監視で設備の異常を早期に検知することで、火災や機械トラブルによる事故を防ぎ、現場の安全性が向上します。
遠隔監視が可能になる
稼働監視システムを導入すると、オフィスから設備の稼働状況を確認できます。また、導入コストは高くなりますが、稼働監視システムを外部のネットワークと接続し、自宅から監視することも可能です。これにより、夜間や休日でも迅速に対応できるようになります。
稼働監視システムを選定する3つのポイント

実際に稼働監視システムを選定する際、導入に失敗しないために重要なポイントが3つあります。
使いやすさ・メンテナンスのしやすさ
稼働監視システム選びで最も重要なことは、使いやすくメンテナンスがしやすいかどうかです。ドラッグ&ドロップで直感的に使えるなど、現場の担当者でも簡単に運用できるシステムが理想です。
また、社内にIT部門やシステムに詳しい担当者がいない場合は、ノーコード(プログラムレス)のシステムを選ぶことも重要です。ノーコードのシステムは、専門的なプログラミング知識がなくても設定や変更ができ、自社内でシステムの調整をしやすくなります。また、過度なカスタマイズで、一部の担当者しか使えないシステムになってしまう事態も防げるため、属人化防止というメリットもあります。
さらに、システム更新やメンテナンス時にもベンダーに依存する必要がなくなれば、コスト削減にもつながります。
データの可視化と分析機能
収集したデータをリアルタイムで可視化し、簡単に分析できる機能があるかを確認しましょう。稼働監視システムの中には、可視化しかできないシステムもあるため注意が必要です。
稼働データを確認するだけでは、稼働率の改善に繋げていくことは難しく、設備の異常や停止の原因を日々取得し、分析することで初めて改善に繋げられます。ノーコード環境でも、ダッシュボードのカスタマイズやレポート作成が簡単にできると、現場改善に活用しやすくなります。特に、異常検知アラートや履歴管理ができ、改善に活かせるシステムが理想的です。
拡張性と他システムとの連携
将来の設備増設への対応や機能追加についても、事前に確認しておくことをおすすめします。
導入後の機能拡張がしづらいシステムを選定すると、追加システムの導入が必要になるケースが多くなります。システム形態にもよりますが、追加費用が数百万円〜千万円以上かかる可能性もあります。
将来的な機能拡張の例として、既存の生産管理システムやIoTプラットフォームとの連携が挙げられます。稼働監視のシステム運用に慣れた後に、システム連携で生産情報や保守部品の在庫情報などの一元管理ができれば、より広範なデータ活用が可能になります。特に、API連携や外部データの取り込みが柔軟にできると、システム全体の最適化がしやすくなり、スマートファクトリーの実現に繋がります。
このような将来の機能拡張も目指す場合、システムベンダーとの打ち合わせ前に、自分たちの要求事項をしっかりまとめておくことも大切です。
以上の3点を重視すると、自社で管理しやすく、柔軟な運用が可能な稼働監視システムを導入できます。導入前には、資料を取り寄せたり、問い合わせをしたりして、システムの仕様をしっかりと確認することが重要です。
導入コストと期待効果

稼働監視システムの導入規模によって、導入コストも変わってきます。企業の成長フェーズや目的に応じて、適切な導入規模を選ぶことが重要です。
最初はスモールスタートで試験運用し、効果を見ながら徐々に拡大するのが理想的なアプローチといえます。
以下に、システム導入に関する導入コストや特徴、期待効果を説明します。
| 規模 | 導入コスト(目安) | 内容 |
| スモールスタート(試験導入) | 数10万円~ | センサーや小型端末を数台導入 1ラインや特定の設備 |
| 小規模導入 | 数100万円~ | 製造ラインの一部や特定の工場に導入 |
| 中規模導入 | 1000万円~ | 工場全体に導入 |
| 大規模導入 | 数1000万円~ | 複数工場・拠点に導入 |
スモールスタート(試験導入)
まずは小規模なライン、例えば1ラインや特定の設備を対象とし、それらの設備データを可視化します。まずは、限られた範囲で試験運用を行うことで、初期投資を抑えつつシステムの導入効果を検証できます。中には無料で体験できるシステムもあります。
例えば、既存の信号灯に付けるだけのIoTセンサであれば、取り付けが簡単、かつ安価に導入できます。工事費不要で数10分で作業完了するものもあります。テスト運用可能なものを試してみるのも良いでしょう。
小規模導入(特定エリアでの運用)
次に、製造ラインの一部や特定の工場に導入します。基本的な分析機能付きのシステムを活用することで、遠隔監視や異常検知、稼働率の改善が可能になります。また、記録作業の負担軽減や保守・点検の効率化にも繋がります。
中規模導入(工場全体での運用)
工場の部分導入に成功したら、工場全体に導入し、稼働状況を監視します。工場全体の稼働状況をリアルタイムで監視し、AIやビッグデータ分析、ERP・MESなどの他システムとの連携活用も検討できるフェーズです。この規模で稼働監視システムを導入できると、生産性向上、異常予測によるダウンタイム削減、さらにエネルギー使用の最適化が可能になります。
大規模導入(複数拠点・統合管理)
工場全体で設備監視が可能になったら、複数の工場や拠点のデータの統合管理に拡張します。高度なAI分析や自動制御、カスタマイズ可能な専用システムを導入することで、生産効率の向上や予知保全の精度向上を目指します。これにより、設備寿命の延長が可能になります。
まとめ:最適な稼働監視で現場を「見える化」し、生産性を向上

稼働監視とは、生産設備の稼働データを収集し、稼働状況や稼働率をリアルタイムで「見える化」することです。
稼働監視システムを導入することで、以下のメリットが得られます。
- ライン停止を最小限に抑え、都度の確認作業を削減
- 設備の稼働率を把握し、改善施策を的確に実施
- 生産性を向上させ、ムダを削減
導入の第一歩は、自社の要求を満たす稼働監視システムを選定することです。そのために、情報を収集し、仕様の事前確認が重要です。
次に、生産設備のデータを収集するための工事を行い、システムを現場に適用していきます。加えて、同業他社の導入状況や活用事例を把握することも、導入の判断材料として有効です。競合企業の動向を参考にしながら、自社に最適なシステムを検討することをおすすめします。

スモールスタートできる稼働監視システム
弊社ネクスタでは、既存の信号灯(パトライト)にIoTセンサを付けるだけで、手軽にスモールスタートできる稼働監視システムを提供しています。トラブル時の設備エラー通知や原因の記録、集計が全て連動して一気通貫で運用できます。
さらに、設備の事前保全ができる点検管理や、設備の保守部品在庫管理にも機能拡張できます。このように、設備のトラブル削減のために必要な機能が揃っています。
上記の機能は、いずれも導入支援付きトライアルが利用可能です。お客様が稼働監視のメリットを最大限得られるように支援していますので、お気軽にお問合せください。
22種類の生産管理システムをランキングで比較
初期費用相場や選び方のポイントをチェック
生産管理システムをそれぞれの特徴や初期費用相場などで比較したい場合は、「生産管理システムランキング」も是非ご覧ください。生産管理システムは、自社の製品・生産方式・企業規模などに適したものを導入しないと、得られるメリットが限定されてしまいます。事前適合性チェックや生産管理システムを選ぶ前に押さえておきたいポイントも解説していますので、製品選びの参考にしてみてください。





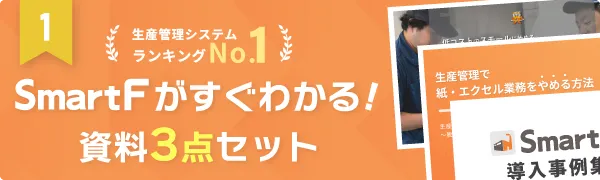








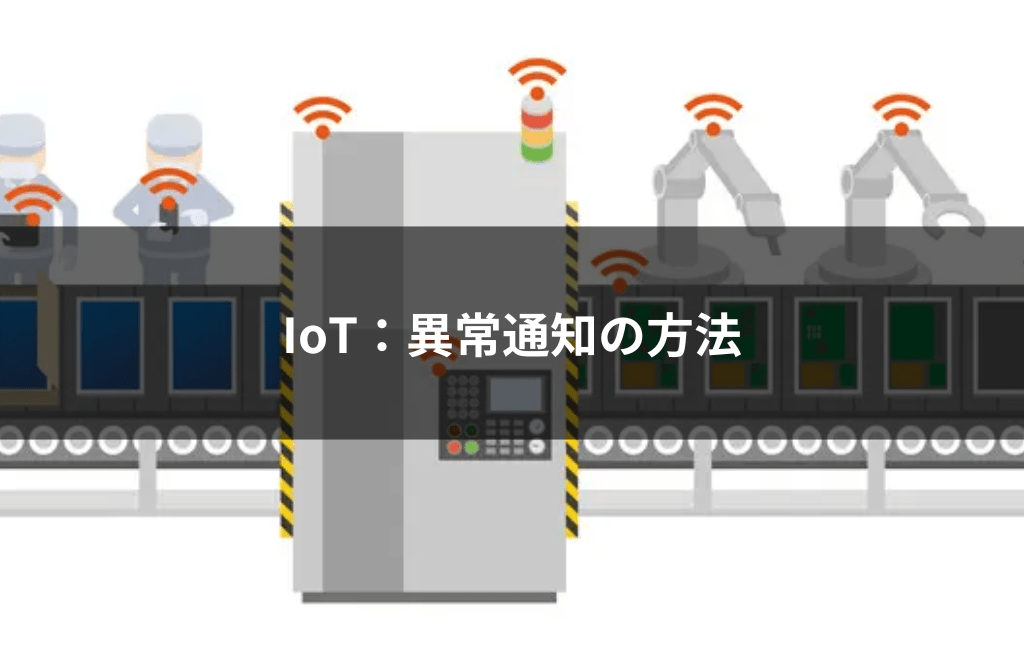
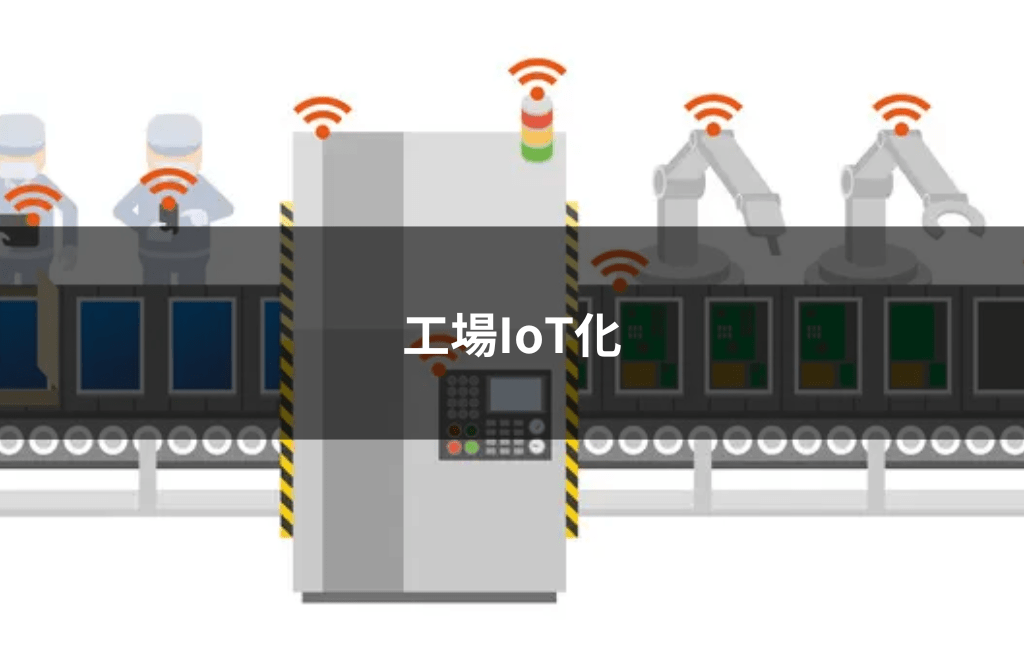



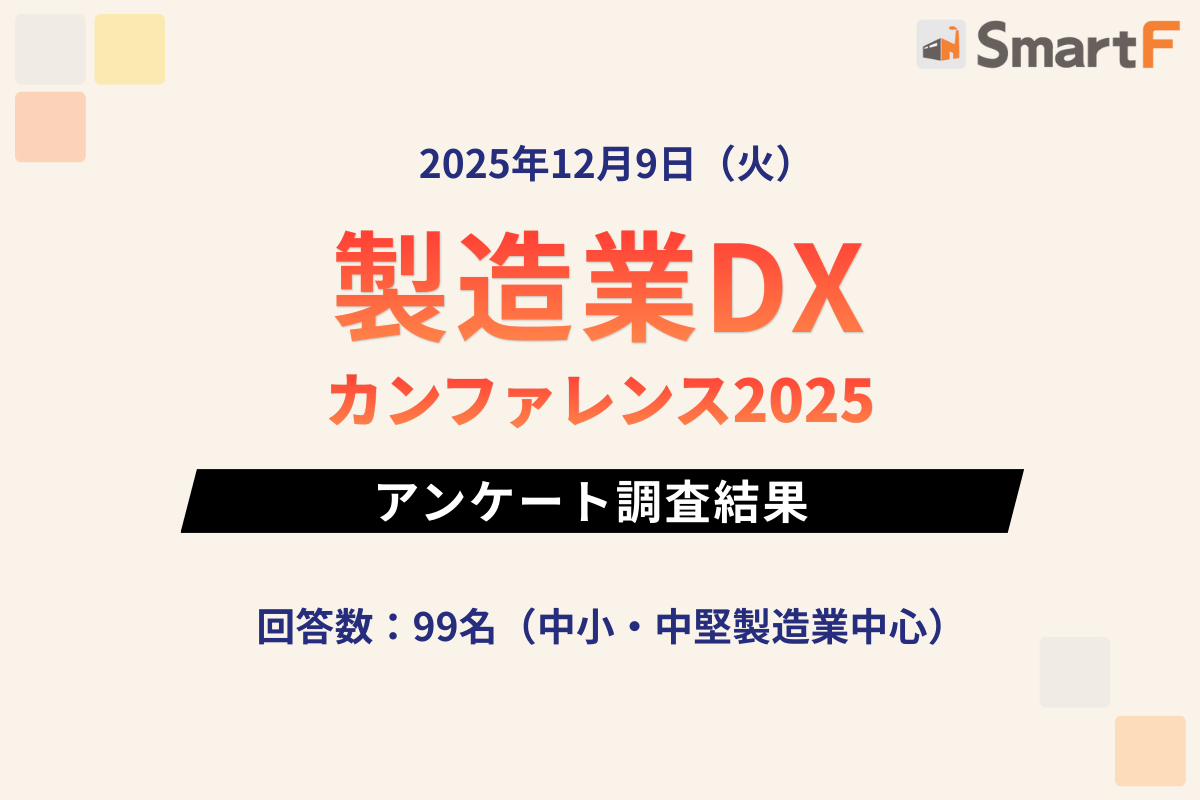




.jpg)









